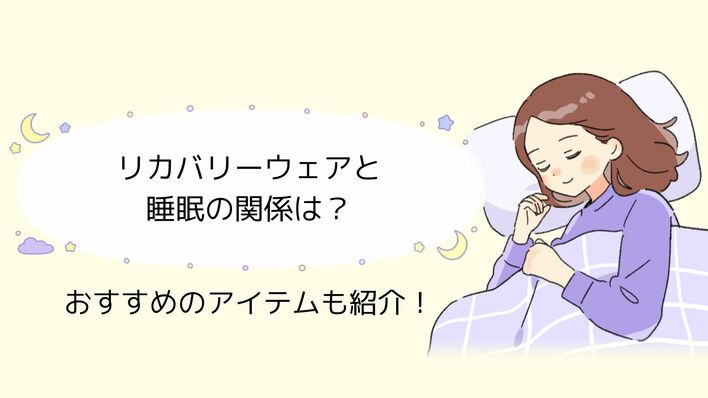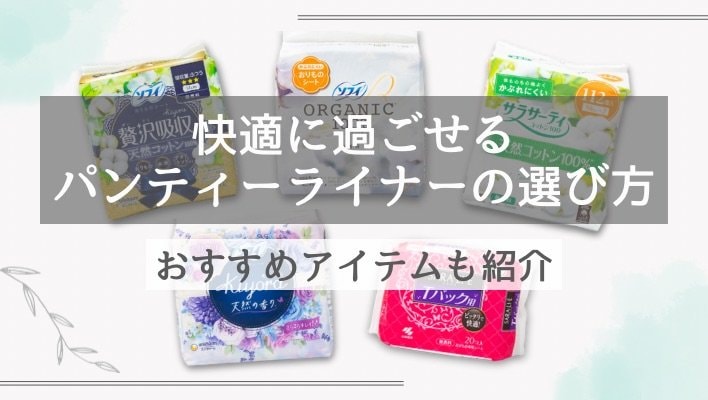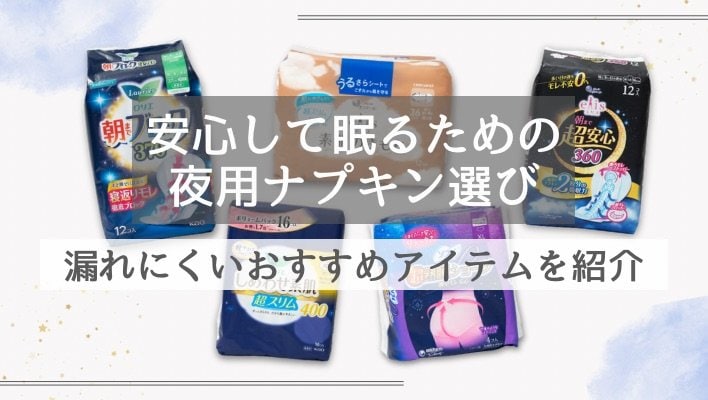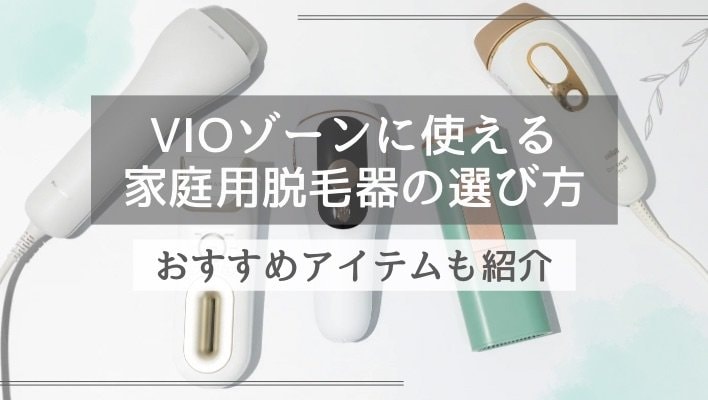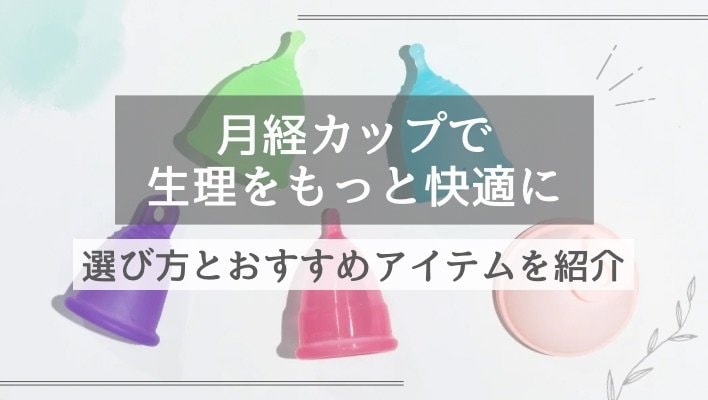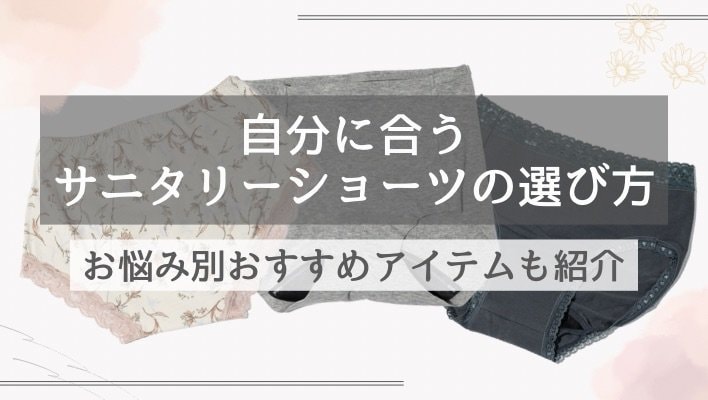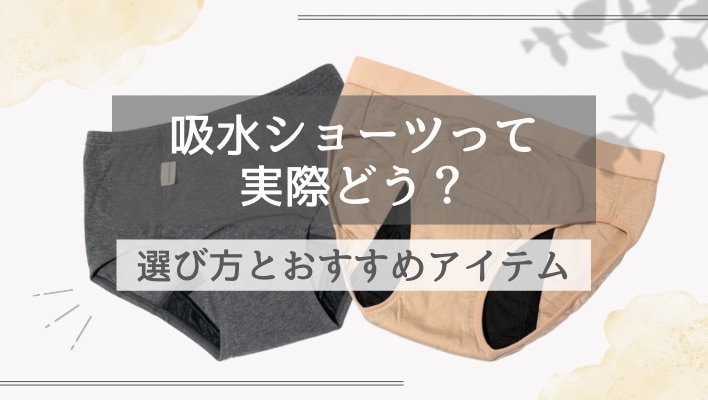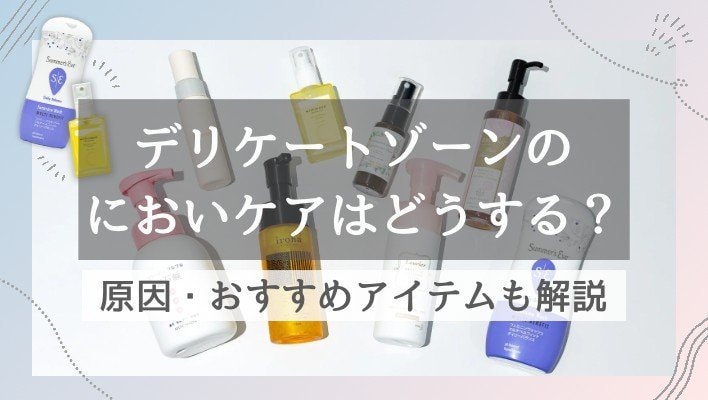毎月憂うつな気分になるPMS、もう終わりにしたいと思う人も多いはず。この記事ではPMSの原因と、快適に過ごすためのヒントをまとめました。PMSの原因や症状が重くなりやすい人の特徴を知って、自分に合う対策を見つけるヒントにしてください。
PMSとは生理前にあらわれる身体や心の不調のこと

多くの女性が悩まされるPMS(月経前症候群)とは、生理3〜10日前ごろからあらわれ、生理が始まるとともに軽減または消失する身体的・精神的な不調のこと。個人差はあるものの、腹痛や頭痛、胸の張りなどの身体的な症状のほか、イライラや感情の浮き沈みといった精神的な症状があらわれます。
PMSの原因として考えられること
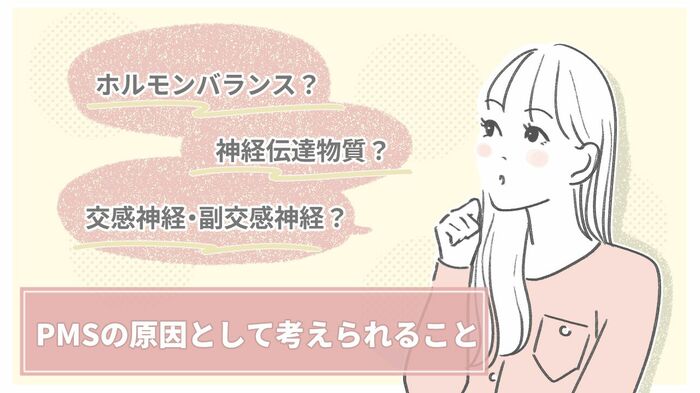
エストロゲンとプロゲステロンという2種類の女性ホルモン量の変動が関与していると考えられていますが、実はPMSの原因ははっきりと解明されていません。ここでは、PMSに関与しているとされる原因を解説していきます。
ホルモンバランスの変動
エストロゲンとプロゲステロンの分泌量は、排卵後から生理までの期間(黄体期)に増加し、生理前に減少。この急激な変化が脳内の神経伝達物質や自律神経に影響を与え、さまざまな身体的・精神的な症状を引き起こすと考えられています。
ホルモンの変化に敏感な人は、より重い症状が引き起こされることもあります。几帳面で完璧主義な人や、急な環境の変化があってストレスを感じている人などは症状が出やすい傾向があります。
神経伝達物質の影響
生理前になると気分が不安定になったり、イライラしたりすることがあります。これは、女性ホルモンのひとつであるプロゲステロンの変動が原因で、脳内の“落ち着きホルモン”であるGABAや“幸せホルモン”であるセロトニンの働きが弱まることが原因のひとつといわれています。
脳や脊髄に存在するGABAには、神経の興奮を抑える働きもあります。腸・血液・中枢神経系に存在するセロトニンのレベルが正常だと、感情が安定して幸福感を得やすくなるとされています。
交感神経・副交感神経の乱れ
交感神経と副交感神経がバランスよく働かないと、心身にさまざまな不調が現れます。交感神経の役割は、エネルギーを必要とする状況で筋肉への血流を増加させたり、消化器系の活動を抑制したりして身体にエネルギーを供給すること。副交感神経は体をリラックスさせ、心拍数を減少させる働きを担っています。
交感神経が優位になりやすい生理前の期間は、心身の緊張や不安感が生じやすい状態に。副交感神経が弱まることでリラックスしにくくなり、心身の疲労感が増すことがあります。
PMSになりやすい人や症状が重くなりやすい人の特徴

PMSの症状は、体質や生活習慣によっても異なります。PMSになりやすい人や、症状がひどくなりやすい人の特徴を見ていきましょう。
ストレスを抱え込みがちな人
ストレスは気分を安定させる神経伝達物質のセロトニンの分泌を減少させるため、イライラや抑うつ感といったPMSの症状を悪化させる一因になります。
完璧を求める性格の人や感情を抑え込む傾向がある人、負けず嫌いな人などは、ストレスによってPMSの症状が悪化しやすい可能性があります。また、仕事や家庭でのストレスが強い人も注意が必要です。
生活習慣が乱れている人
睡眠不足の人や食生活が偏りがちな人は体内のさまざまなホルモンバランスが乱れやすく、PMSの症状が強く出ることがあります。
睡眠不足はストレスを引き起こし、ストレスに関わるホルモンであるコルチゾールの分泌を増加させる原因になります。性ホルモンなどその他のホルモンの分泌にも影響を与えてしまうため、ホルモンバランスが崩れやすくなるという仕組みです。
偏った食事は、ビタミン・ミネラル・タンパク質などホルモンバランスを整えるために必要な栄養素の不足につながります。また、アルコールやカフェインなどを摂りすぎると、ホルモンバランスが乱れる原因になります。
ライフイベントが多い30代の人
仕事や家庭のストレス、妊娠・出産といったライフイベントが多い30代は、環境の変化やストレスによりホルモンが変動しがち。ストレスによりPMSの症状がより顕著になり、イライラや情緒不安定、攻撃的な感情の増加など、特に精神的な症状が強くなることが多い年代です。
みんなのPMSの症状は?

全国の15∼60歳の女性300人にアンケートを実施した、“生理前の症状に関する調査”では、半数以上の女性がイライラや怒りを感じています。また、気分の浮き沈みが激しくなると回答した人は約4割。むくみや腹部の張り、痛みなどの身体的な症状も、約3割の人にあらわれているようです。
PMSの対処法を4つ紹介
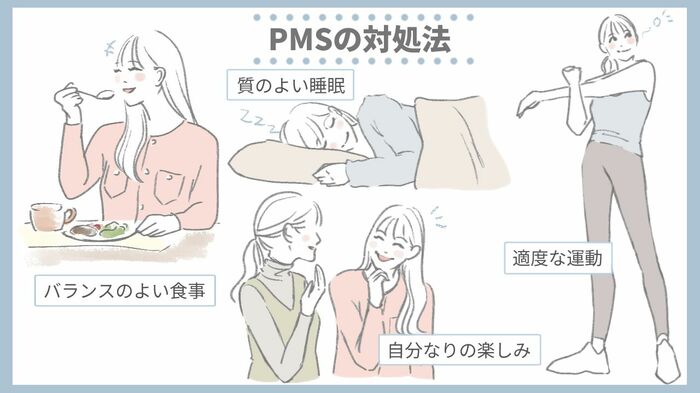
血行不良や冷えで症状が重くなることもあるPMSは、自分でも対策することが大切です。PMSに対するセルフケアを4つ紹介します。自分に合った方法を無理のない範囲で取り入れてみてください。
バランスのよい食事を心がけよう
バランスのよい食事を基本とし、PMS対策として特に意識したい栄養素は、カルシウム、マグネシウム、ビタミンB6です。カルシウムとマグネシウムは、神経の興奮を鎮めたり、筋肉の収縮をスムーズにするのに役立ちます。ビタミンB6は神経伝達物質の生成に関与し、精神的な安定をサポートするといわれています。
また食事を急いでとると、脳が満腹感を得る前に過食してしまうことが多く、血糖値の急上昇を助長してしまいます。血糖値が急激に上昇する血糖値スパイクは、食後の眠気やだるさの原因となるため、早食いは控えましょう。
適度な運動習慣を取り入れよう
ウォーキングやジョギング、水泳などの軽い有酸素運動は、ストレスを軽減して気分をリフレッシュさせる効果が期待できます。血液や体液のめぐりが促されることでむくみが軽減したり、腹痛や腰痛などが和らぐ可能性もあります。身体をリラックスさせて心身のバランスを整えるためには、ヨガやストレッチもおすすめです。
ストレス管理にも気を配ろう
上述の通り、ストレスはPMSの症状を悪化させる大きな原因。自分なりのリラクゼーション法を取り入れて、心を落ち着かせることが大切です。
アロマやマッサージを取り入れるなど、自分がリラックスできたり好きと思えることに取り組む時間を持つことが、ストレス解消への近道といえます。
質のよい睡眠を取ろう
できる限り毎日同じ時間に寝起きすることで体内時計が整い、質のよい睡眠につながります。生活が不規則な人も照明を暗くする、寝る前のスマホを控えるなどの意識を持ち、睡眠環境を整えましょう。
また、就寝の1時間ほど前にノンカフェインの温かいハーブティーなどを飲むのもおすすめ。スムーズな入眠をサポートします。
PMSの症状が気になるなら婦人科を受診しよう

多くの女性が経験するPMSですが、症状のあらわれ方は人それぞれ。PMSの症状がつらいと感じたら、1人で悩まず婦人科に相談しましょう
この記事の監修者
婦人科医・医学博士|鈴木 美香 医師

— プロフィール —
産婦人科医・医学博士。婦人科、女性医学、漢方医学を専門とし、予防医療や労働衛生にも精通。多数の専門医資格を持ち、聖隷健康サポートセンターShizuokaの所長として活躍。国際学会での受賞歴もあり、共著書「フローチャート女性漢方薬」を出版。静岡県立大学客員教授も務め、女性の健康管理と予防医学の普及に尽力している。
— 経歴 —
浜松医科大学医学部卒業
浜松医科大学大学院修了
米国カリフォルニア大学サンディエゴ校医学部がんセンターなどの勤務を経て
現在、聖隷健康サポートセンターShizuoka所長
特定非営利活動法人くすり・たべもの・からだの協議会副理事長も務める