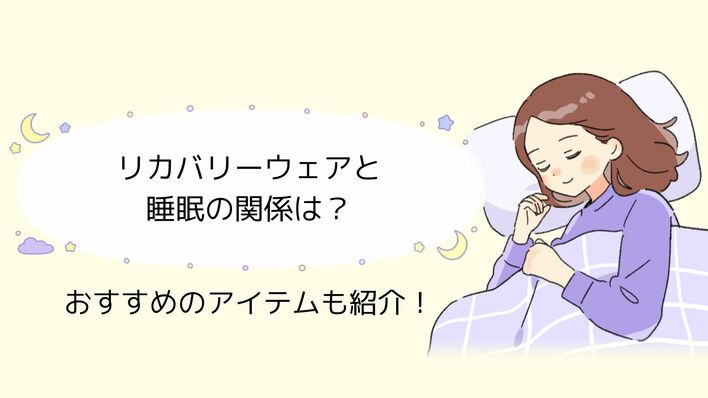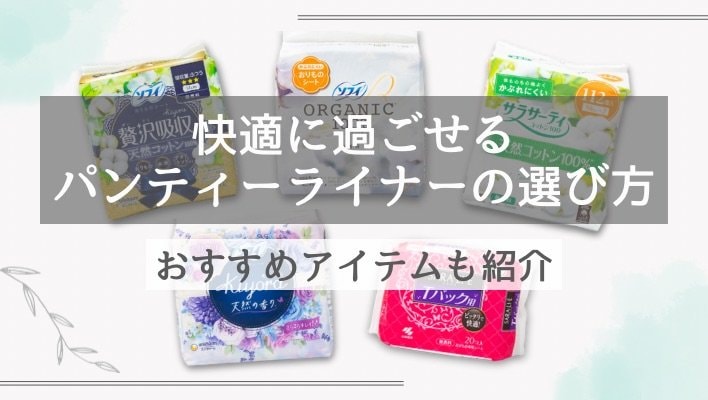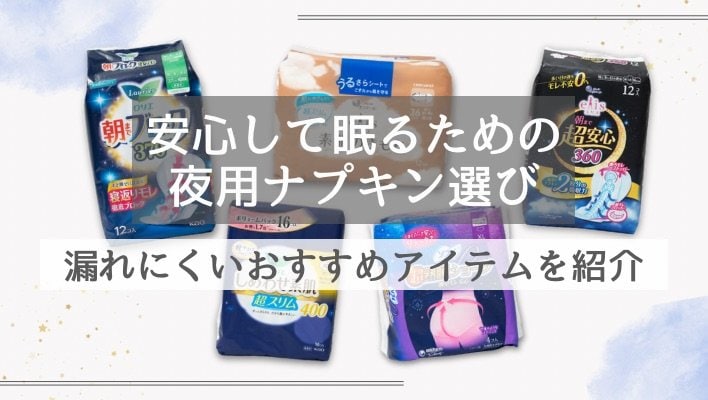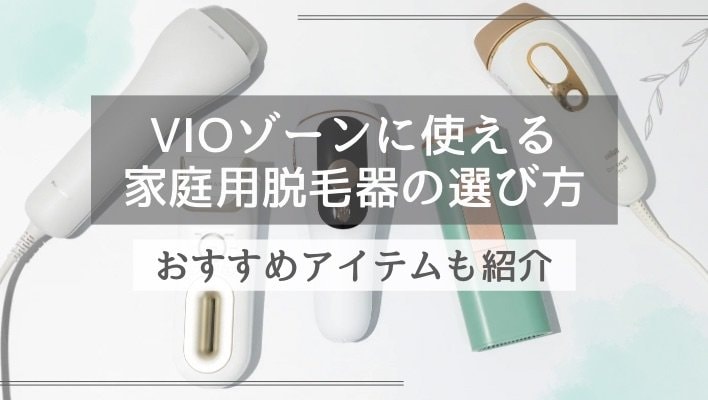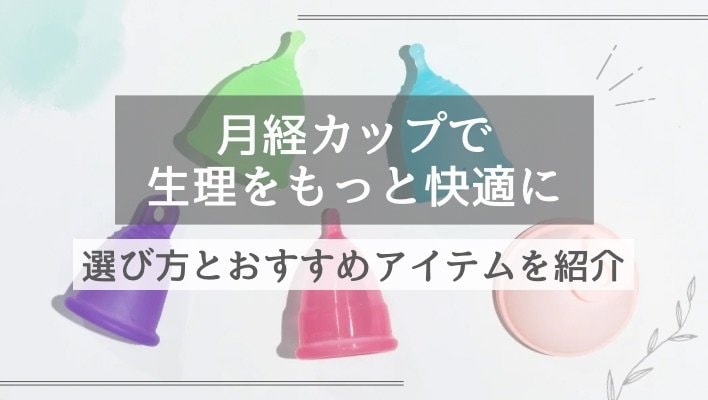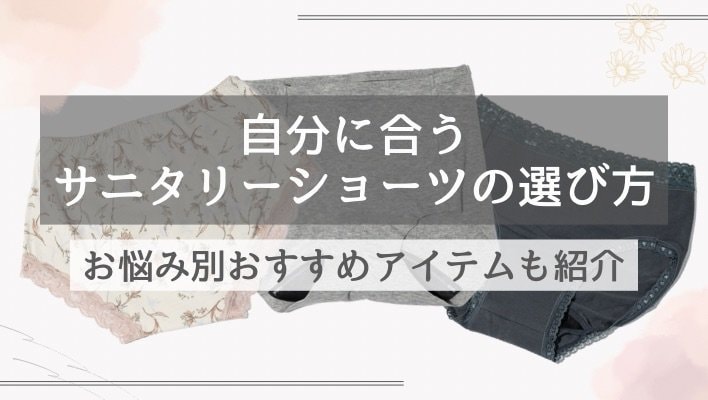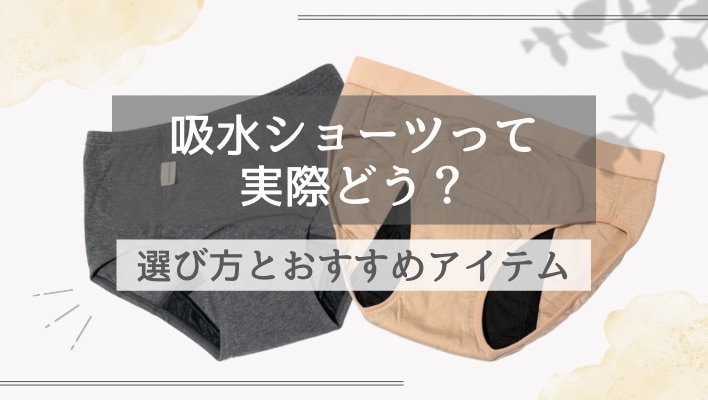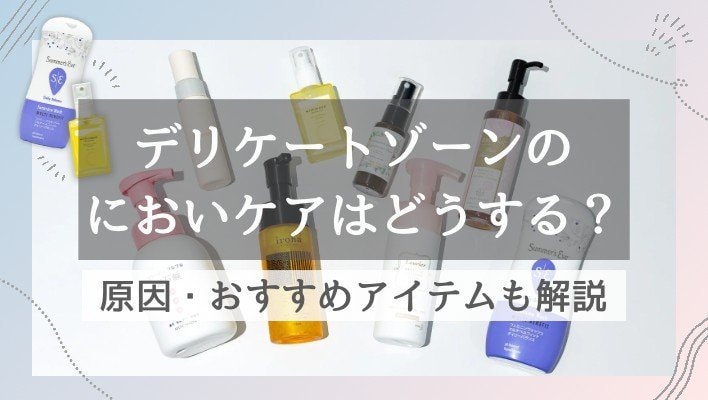ピルを使ってPMSの症状を改善したい、でも効果が感じられない。そんな悩みを抱える人へ、PMSの症状改善のポイントと正しい知識をお伝えします。
PMSとは

多くの女性が経験するPMS(月経前症候群)について、症状の仕組みから対処法まで詳しく解説します。
PMSとは生理1週間前から始まるさまざまな不調のこと
生理開始の約1週間前から始まる心身の不調は、PMS(月経前症候群)と呼ばれています。生理の開始とともに自然と和らぐことが特徴で、女性の70~80%が経験する一般的な症候群です。
実際に行ったアンケート調査(※)では約6割の女性が乳房の張りや痛み、下腹部の違和感、腰の重さなどの不調を自覚していると回答しており、PMSが多くの女性に共通する課題であることがわかります。
ホルモンバランスの変動がPMSの原因
PMSは女性の体にとって自然な周期の一部。卵巣から分泌されるホルモンの変動、特に排卵後から生理開始までの期間に起こる急激な変化が主な原因です。この時期、卵胞ホルモン(エストロゲン)の急激な低下は気分の変化や頭痛の原因となり、黄体ホルモン(プロゲステロン)の変動は水分貯留を促してむくみを引き起こします。そのほか、セロトニンの変動もPMSの原因になります。
生活習慣もPMSの症状に密接に関わる要素のひとつです。食事の影響は特に大きく、ビタミンB群が不足すると疲れやすさが増加します。カフェインの過剰摂取は不眠やイライラを強め、アルコールや塩分の取りすぎは水分バランスを崩してむくみを助長することもあります。ストレスもさまざまな症状を全般的に悪化させます。
このようなホルモンバランスの変動に対して、医療機関では主に低用量ピルによる治療が行われています。エストロゲンとプロゲステロンという2種類の女性ホルモンを適切な量で補充し、体内のホルモン変動を穏やかにすることで、PMSの症状緩和につなげる仕組みです。
PMSは人によって症状が異なる
PMSの症状は人によってあらわれ方が大きく異なります。身体面では、下腹部の張りや痛み、腰の重さ、乳房の張りといった症状が一般的に見られ、頭痛やむくみに悩まされる人も多数。精神面では、イライラ感や不安感の増加、集中力の低下といった変化を感じることも少なくありません。
症状の出現時期と持続時間にも個人差があります。生理の3~10日前から症状があらわれ始め、生理の開始とともに徐々に和らいでいくのが一般的です。アンケート調査(※)では、2~3日前から症状が始まると答えた人が約4割と最も多く、次いで4~6日前から症状を認識する人が多い結果となりました。なかには、より早く症状が出始める人や、症状の変化が緩やかな人もいます。
同調査によると、精神症状では“イライラや怒り”を感じる人が約6割と最も多く、次いで“気分の浮き沈みが激しくなる”が約4割強、“眠気”が約4割。身体症状では“乳房の張り”と“肌荒れ・ニキビ”がそれぞれ約4割を占めました。これらの結果から、PMSによる身体的および精神的な影響が広範囲に及び、多くの女性の日常生活に影響を与えていることがわかります。
このような個人差は、個人のホルモンバランスの特徴に加えて、日々の生活環境も大きいもの。特に仕事や人間関係などのストレスは症状を強める要因になりやすく、また几帳面な性格の人や感情を抑え込みがちな人は、より強い症状を経験する傾向があることもわかっています。
PMS改善にピルは役立つ?注意点も解説

ピルによるPMSの治療に関して、保険適用についてと注意点を説明します。
PMSにピルは保険適用されない?
PMSの治療としてピルを処方してもらうには、婦人科での診察が必要です。
ピルで保険適用となるのは、月経困難症や子宮内膜症などの治療目的の場合のみのため、PMSの可能性が高いと判断された場合には、他の婦人科系の病気がないか検査などで確認します。
基本的にPMSの治療のみで処方されるピルは保険適用にはならないため、注意が必要です。
PMSの治療としてピルの処方を希望する場合には自費となりますが、保険診療薬のLEP(低用量エストロゲン・プロゲステロン配合剤)は自費治療薬のOC(経口避妊薬)の約3倍の値段のため、実際の支払い価格はあまり変わりません。
ピル服用時に知っておきたい注意点
低用量ピルの服用開始から2~3ヵ月の間は、吐き気や頭痛、不正出血といった体調の変化を経験することがあります。これらの症状は体がピルに慣れていく過程であらわれるもので、時間とともに自然に落ち着いていくことがほとんど。ただし、急な胸の痛みや強い頭痛を感じた場合は、血栓症などのリスクの高い副作用の可能性があるため、すぐに医師に相談しましょう。
また、安心して服用を継続するためには、副作用への対処法を知っておくことが大切です。吐き気が気になる場合は服用時間を就寝前に変更することで症状が軽減されることもあります。不正出血に備えて、生理用品を持ち歩くなどの工夫も効果的です。
漢方薬や生活改善などピル以外の選択肢も
他の治療法との組み合わせで、ピルによりPMSの症状を改善することができます。体質や症状に合わせて処方される漢方薬は、ピルとの併用も可能です。ただし、漢方薬やサプリメントを併用する際は、必ず医師に相談してから始めましょう。
生活習慣の改善もPMSの症状をやわらげるために重要な要素です。規則正しい生活リズムを保ち、バランスのよい食事を心がけ、適度な運動を取り入れることが効果的といえます。ストレス管理も症状の改善に大きく影響するため、自分に合ったリラックス方法を探してみてください。
症状の管理と記録

PMSの症状は、月によっても変化します。記録をつけることで、自分に合った対策が見つけやすくなるでしょう。
スマホで毎日簡単に記録
スマートフォンのアプリやカレンダー機能を活用すると、PMSの症状を手軽に記録できます。ピルを服用中の人はもちろん、これから服用を検討している人も、記録をつけることで体調の変化がより明確に把握できるでしょう。
記録する内容は、その日の症状の種類と程度です。頭痛やむくみなどの身体症状、イライラなどの精神症状は、“軽い・中程度・つらい”というシンプルな3段階で評価すると継続しやすくなります。睡眠時間、食事内容、運動の有無、ストレスの程度といった生活習慣も記録しておくと、症状との関連性が見えてきます。ピルを服用中の人は服用時間も記録することで、飲み忘れの防止にも効果的です。
記録は毎日同じ時間帯、特に就寝前の数分間で行うと習慣化しやすくなります。スマートフォンが苦手な人は、手帳への記入でも十分。大切なのは、自分に合った方法で続けることです。
3ヵ月の記録から分かる改善のヒント
毎日の記録を3ヵ月程度続けることで、生理開始の何日前から症状があらわれ始めるのか、どんな症状が強く出やすいのかといった、自分のPMSの特徴が明確になってきます。睡眠時間や食事内容、運動習慣などの生活習慣と症状の関連性も把握できるようになるでしょう。特にストレスが強い時期に症状が悪化するといった傾向も、記録から読み取れます。
記録は、予防的な対策を立てる重要なヒントです。症状が出やすい時期が分かれば事前に対策を始められ、生活習慣との関連が分かれば日常生活の中で工夫できるポイントが見つかるでしょう。
ピルの効果が感じられない人へ

ピルを服用しても思うような効果が得られないときは、まずは原因を探ることから始めましょう。
ピルが効かない原因は症状や服用方法にある
実際のアンケート調査(※)では、約3割の人がPMS治療でのピルの効果を実感できなかったという結果に。ピルの効果を実感できない理由は、主に症状の個人差と服用方法の2つの要因に分けられます。
腹痛や頭痛などの身体症状が中心の人もいれば、イライラや不安感といった精神症状が強い人もいるなど、PMSの症状は人によってさまざま。特に精神症状が重篤な場合はPMDD(月経前不快気分障害)の可能性もあり、通常のピル治療だけでは十分な効果が得られにくいことがあります。
また、服用方法も大きな要素のひとつ。ピルは服用開始から効果があらわれるまでに2~3ヵ月程度かかりますが、飲み忘れや不規則な服用は効果を減少させるので、毎日同じ時間に服用することが重要です。また、十分な睡眠が取れないことや偏った食事、運動不足といった生活習慣の乱れも、ピルの効果を妨げる要因になります。
医師との相談で必ず伝えたい3つのポイント
ピルの効果が感じられない場合、医師との相談が重要です。より適切な治療につなげるため、以下の3つのポイントを伝えましょう。
まず、現在の症状と体調の変化について詳しく説明します。痛みの程度や症状が出現する部位、持続時間、精神症状の頻度や強さなど、これまでの記録を基に伝えましょう。気になる症状や以前と比べて変化した点があれば、特に詳しく説明します。
毎日同じ時間に服用できているか、飲み忘れはないか、服用を始めてからの期間など、ピルの服用状況も正確に伝えましょう。効果の判定には最低でも3ヵ月程度の期間が必要なため、その間の記録があると正確な判断が可能です。
既往歴や現在の健康状態についての説明も忘れずに。安全で効果的な治療法を選ぶため、高血圧や糖尿病などの持病の有無、他に服用している薬の情報も大切です。
これらの情報を医師に伝え、十分なコミュニケーションを取ることが適切な治療法を見つける第一歩になるでしょう。
※
アンケート調査内容:生理前の症状に関する調査
調査期間:2025年1月16日
調査対象:全国の15~60歳の女性300人
調査方法:インターネット調査
この記事の監修者
クレアージュ東京 レディースドッククリニック 婦人科顧問|大島 乃里子 医師
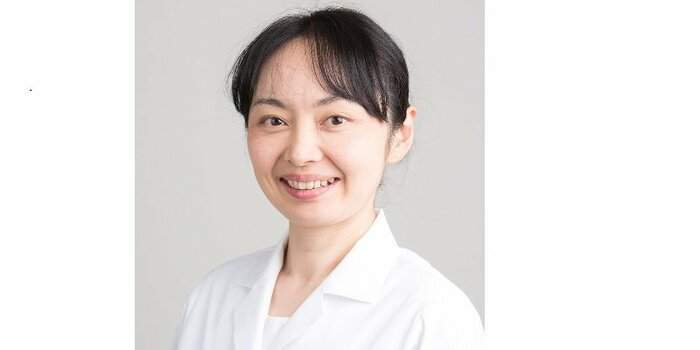
— プロフィール —
婦人科腫瘍のほか女性医学の専門医でもあり、思春期から老年期までの女性の生涯におけるヘルスケアを担う。一人ひとりの患者さんに向き合った治療を行っている。
— 経歴 —
医学博士
日本産科婦人科学会専門医
日本婦人科腫瘍学会専門医