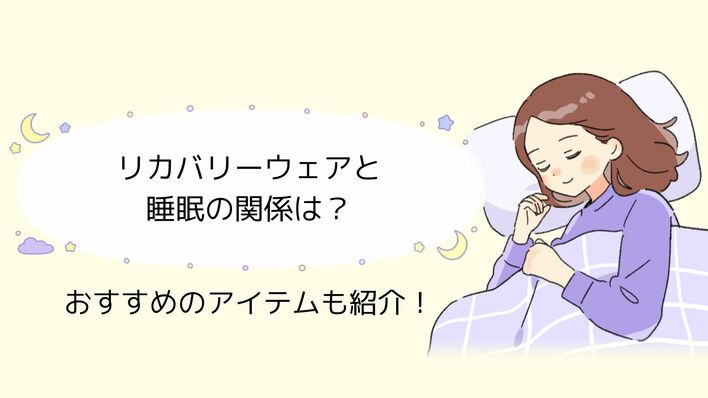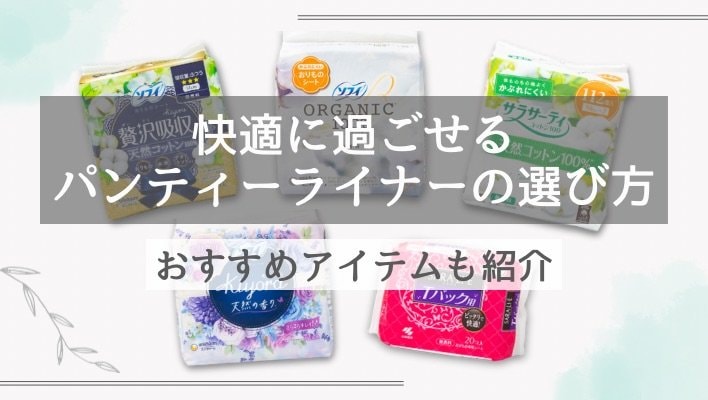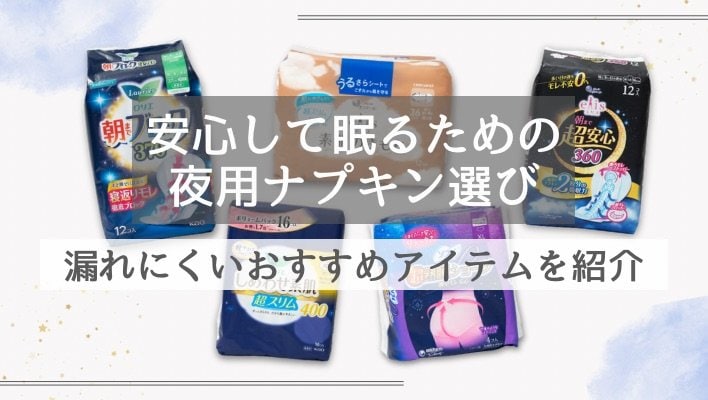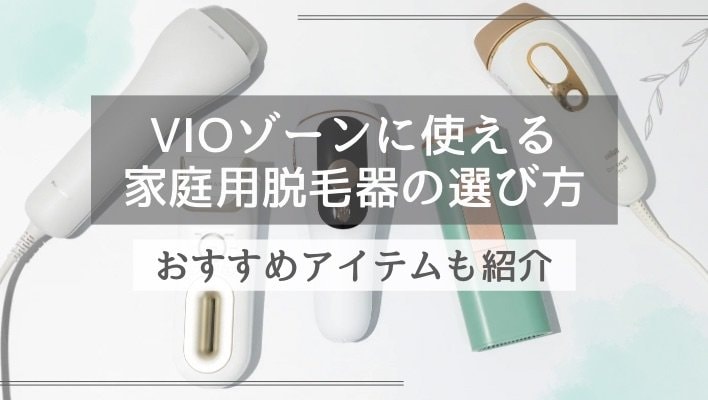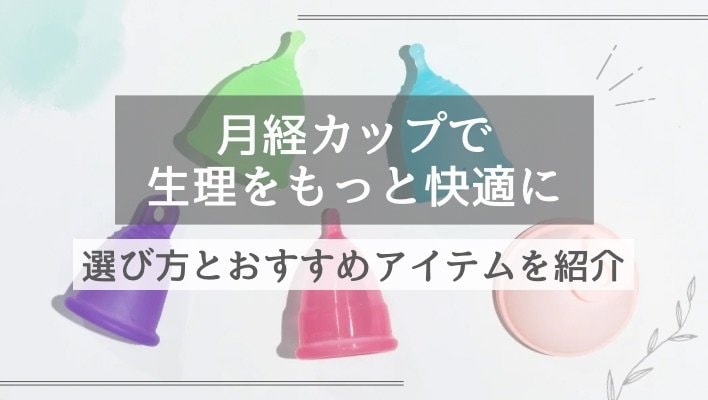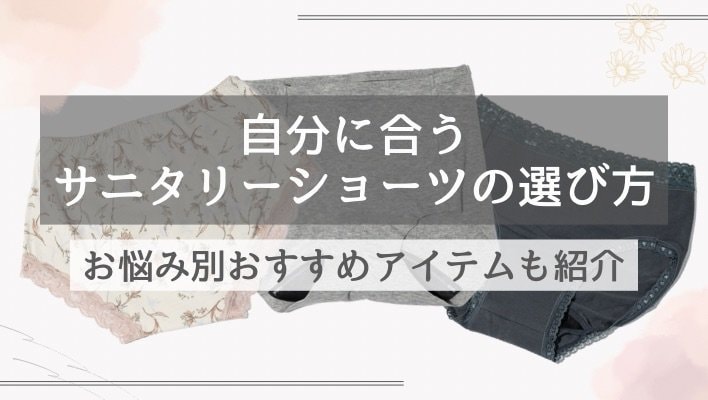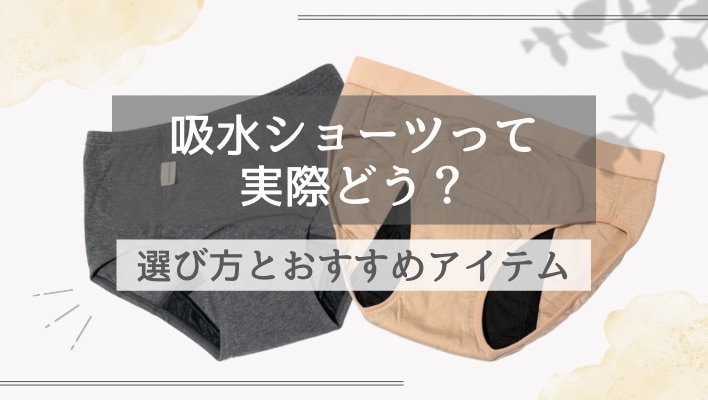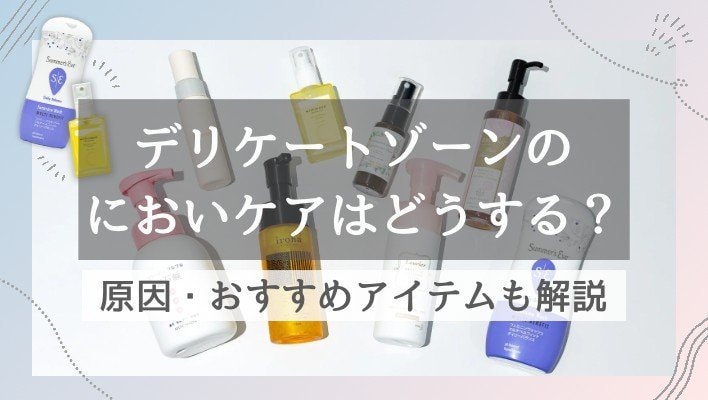出産後は休む間もなく赤ちゃんのお世話が始まります。特に新生児のときには夜中の授乳や夜泣きなどで、どうしてもまとまった睡眠時間が確保できません。睡眠時間を確保するためのアイデアや、睡眠不足が長期間続くことによるリスクを解説します。
産後の睡眠不足の理由

産後のママは、女性ホルモンの変化や赤ちゃんのお世話によって、まとまった睡眠時間がなかなか取れません。産後、睡眠不足になってしまう具体的な理由を解説します。
睡眠不足が続くと、十分な睡眠時間が確保できても眠れなくなる“睡眠障害”に陥ることもあります。また、肌荒れや体調不良、メンタル面への悪影響を引き起こす可能性があるため、早めに対策することが重要です。
女性ホルモンの急激な変化
出産すると女性ホルモンが急激に減り、体は出産前の状態に戻ろうとします。急激に女性ホルモンの分泌量が変わることで、体は疲れているのに眠れないこともあるでしょう。
ただし、産後は徐々に妊娠前の状態に戻るため、過度に心配する必要はありません。授乳していない場合で2ヵ月程度、授乳している場合で6ヵ月〜1年程度かけて妊娠前の女性ホルモンのバランスに戻ります。
赤ちゃんの夜泣きも落ち着いてきて、寝る時間があるのに眠れない場合には抑うつの可能性も考えられます。医療機関の受診を検討しましょう。
赤ちゃん中心の生活になるため
産後は赤ちゃん中心の生活になってしまい、自分のことを考える余裕がなくなってしまうことも少なくありません。特に新生児のうちは昼夜を問わず、頻繁に授乳やミルクの時間が発生します。
生後間もない赤ちゃんは長時間は寝てくれず、数時間おきに目が覚めてしまうため、ママはまとまった睡眠時間が取れません。特にママが1人で育児と家事を行っている場合には、さらに睡眠不足になってしまいます。
慣れない育児の緊張感
初産の場合は、何もかもが初めて。おむつや授乳などの基本的なお世話だけでなく、きちんと呼吸しているか、熱は出ていないか、肌荒れはしていないかといった心配ごとが多く、気がつかないうちに常に緊張状態になってしまうでしょう。
この緊張感がストレスとなり、疲れているのに眠れないという状況に陥ることもあります。
産後の睡眠不足はいつまで続く?

この睡眠不足は一体いつまで続くのか、心配な人も多いのではないでしょうか。少しでも安心できるよう、産後の睡眠不足がいつまで続くのか解説します。睡眠不足のピークを知り、今からでもできる対策はないか考えておきましょう。
生後3ヵ月頃までがピーク
生後間もない赤ちゃんは、長時間は眠れないことがほとんどです。日々成長していく中で睡眠時間も伸びていき、昼夜の生活リズムが整っていきます。
赤ちゃんに体力が付き始めると、母乳やミルクを一度に飲む量も徐々に増えていきます。次第に授乳の間隔が空いていくため、ママも睡眠時間を確保しやすくなるでしょう。
ママの睡眠不足は新生児期から生後3ヵ月頃までがピークと言われています。それ以降は徐々に睡眠時間がとれるようになってくるので、可能な限り周囲を頼りながら乗り切りましょう。
生後6ヵ月以降は落ち着くことが多い
生後6ヵ月を過ぎると、赤ちゃんの授乳回数や睡眠リズムが整い、ママも睡眠時間をとりやすくなります。
ただし、赤ちゃんの個人差も大きいため、1歳になるくらいまでは夜泣きなどで起こされてしまうことがあるでしょう。米国の研究では、夜泣きしたときにしばらく様子をみる方が赤ちゃんが眠ってくれることが増え、夜泣きが減るとも報告されています。夜泣きしてもあわてずに、近隣に迷惑にならない程度にそっと見守るのも1つの方法です。
つらい睡眠不足は1人で抱え込まず、限界を迎える前に家族や行政など、周囲の協力を得ることも大切にしていきましょう。
産後の睡眠不足の解消法

産後はどうしても長時間寝るのが難しい時期。家庭の状況にもよりますが、できるだけ睡眠不足を解消できる方法を試していきましょう。
赤ちゃんが寝るときに一緒に寝る
赤ちゃんの寝るタイミングに合わせて、ママも一緒に寝るようにするのがおすすめ。赤ちゃんが寝ている間に終わっていない家事をしたくなりますが、このタイミングが最も休息しやすいので、思い切って一緒に寝てしまいましょう。
自分の寝返りで赤ちゃんを押し潰すようなことがないように、安全を確保してから寝ることを忘れないでください。
細切れにでも睡眠をとることで、疲れをとって楽になりましょう。
睡眠の質をあげる工夫をする
産後の短い睡眠時間でも、睡眠環境を整えて睡眠の質をあげることが大切です。次の方法から、手軽にできるものを実践してみましょう。
・隙間時間の軽い運動・休息でストレスを解消する
・寝るときには部屋を暗くする
・寝る直前のカフェイン摂取を避ける
・寝る直前の入浴を避ける
・ベッドにスマートフォンを持ち込まない
・寝具にこだわり快適な睡眠環境にする
赤ちゃんと一緒に昼寝をする場合には、遮光カーテンをつけるのもおすすめです。
周りを頼ってみんなで育児をする
妊娠と出産による体の変化や出産時の体力の消耗がある中で、休む間もなく育児が始まり、生活環境が大きく変わります。
そんなときに家事を完璧にこなそうとすると、体の回復が遅れるばかりか余計なストレスを抱えてしまい、十分な睡眠がとれません。
可能であれば、育児や掃除、洗濯、料理などの家事はパートナーや家族と分担して行い、ほどよく手を抜きましょう。家電や家事代行サービスなどの利用もおすすめです。
赤ちゃんやママの健康が第一なので、家事は完璧でなくてもよいという意識を持つことが大切。ストレスを減らして、よく眠れる環境を整えましょう。
赤ちゃんの生活リズムを整える
赤ちゃんは新生児のときには昼夜の区別がつきません。物理的に生活リズムを整えていくと、少しずつ夜しっかりと眠ってくれるようになります。
ママも赤ちゃんも規則正しい生活を心がけ、昼夜の区別をつけていきましょう。
例えば、朝は決まった時間にカーテンを開けて朝日を入れる、朝食をしっかりとる、お風呂の時間や就寝時間を決めて、寝るときは部屋を真っ暗にするなどがおすすめ。赤ちゃんと一緒に規則正しい生活を送ることが、ママの睡眠不足解消の近道になります。
この記事の監修者
勝どきウィメンズクリニック院長| 松葉 悠子

—プロフィール—
これまで周産期センターでの勤務を中心に産婦人科診療に研修、従事。東京大学医学部付属病院、日立製作所日立総合病院、恩賜財団母子愛育会 愛育病院などの勤務を経て、2015年に勝どきウィメンズクリニックを開業。2024年には晴海ウィメンズクリニックも開業し、理事長に就任。
— 経歴 —
金沢大学医学部医学科卒
東京大学医学部付属病院・日立製作所 日立総合病院・東京都保健医療公社 豊島病院・恩賜財団母子愛育会 愛育病院などに勤務