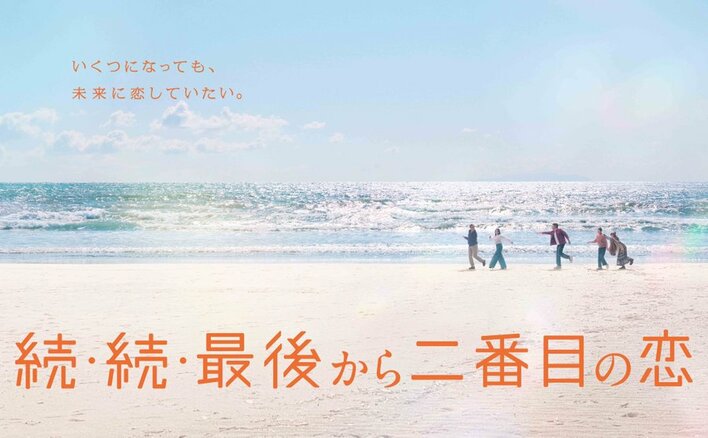――中井家に伝わる小津イズムとはどんなものですか?
総体的にいうと“粋”であるということですね。今の時代って資本主義社会だから当然ですが、人間の内面より数字で表されるもの、視覚で理解できるものが優先されがち。だけど、小津先生は目に見えない人との縁やつながり、心のもちようをとても大切にされていたんです。
このエピソードは今回の劇中にも登場するのですが、ある日、小津先生がうちの母に鰻を食べに行こうと誘って、当時は電車が今ほど便利ではなく、さらに、小津先生はお酒をたしなまれるから車で行くわけにもいかなくて、タクシーで行くことを提案されたと。
タクシーで何千円もするところへ行くことをためらった母が、「それは贅沢ですよ。うちの近所にも鰻屋はありますから」と言ったら、「わかってないね。近所でお腹を満たす為だけに、そこそこの鰻を食べるのを無駄遣いというのであって、心を豊かにするものにお金を払うこと、それは贅沢ではない」とおっしゃったそうなんです。
そして、「人間は“わざわざ行く”という労力を使ったことで、得ようとするものが倍にも3倍にもなる。時間とお金をかけてでも美味しい店へ行くことで、一口食べたら『うわ、美味しい!』と思うだろう?そういう気持ちが大事なんだよ」と。つまり小津先生は贅沢をお金という数字ではなく、心の裕福度で考えていらっしゃったんだと思います。
デビュー当時に撮影所で体感した、父・佐田啓二の肌感

――そんな小津監督をモデルにした役柄を演じるにあたって、意識しているのはどのようなことですか?
僕は3歳になる前に父を亡くしていて、父のことをあまり覚えていないのですが、まわりから「お父さまって素敵ね」と言われ、蝶ネクタイをしていた、いわゆる“俳優・佐田啓二”のイメージで、僕としてはあまり実感がありませんでした。
そして、19歳で映画界に入り、松竹の撮影所へ行ったときに小津先生や父の世代のスタッフさんが訪ねてきてくださって。
そこで皆さんから、「お父さんと飲みに行ってね」とか、「楽屋の扉を開けたらサングラスとマスクとマフラーで出かけようとしていたから、『佐田さん、そっちのほうが目立ちますよ』と指摘したんだよ。あれは絶対、これ(女性)だね(笑)」といった人間味のあるエピソードを聞き、そのときに父の肌感みたいなものが伝わってきて、すごく嬉しかったんです。
ですから、僕は今回、神格化されていない「人間・小津安二郎」の部分を “小田”として演じ、伝えられたらいいなと思って臨んでいるのですが、いつか僕が死んで“上”に行ったとき、小津先生に会ったら怒られるかもしれないので(笑)、失礼のないようにやらせていただきたい、と思っています。