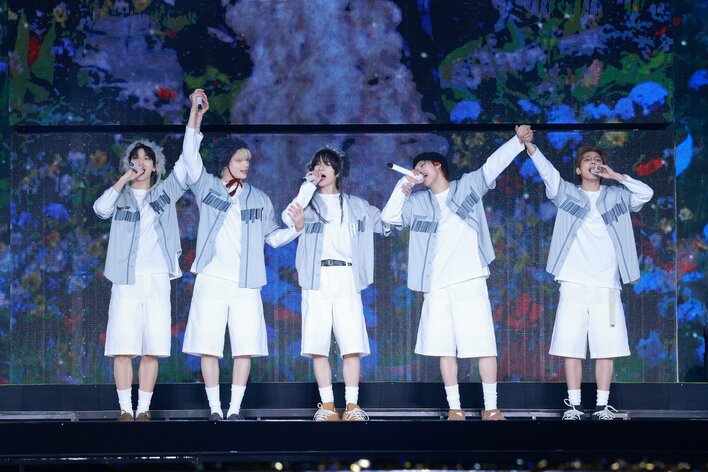“muqueらしさ”の一つともいえるのが、エレクトリックな打ち込みに合わさる、“生”のサウンド。ライブに定評があるバンドらしい“人間味”を意識してのことだそう。
また、作詞を担当するAsakuraさんは、自身が手掛けた『The 1』の歌詞で「一番好き」だというフレーズを明かします。
打ち込みサウンド+Lenonの“生ベース”で温かみやなじみやすさを創出
小山内:続いての“推しポイント”はどこでしょうか?
Lenon:(「♪また誰も守れないの」からのAメロが)イントロと違って音数が少なくなってドラムとベースが主軸になるんですけど、ここのベースもtakachiが打ち込みで作ってくれていたんです。でも、やっぱりちょっと無機質だね、ということで、生のベースを入れて空気感というか、“生感”を出しました。
小山内:やっぱり“生感”というのは大事ですか?

Kenichi:そうですね。打ち込みのトラックに、いかにバンドサウンドを融合させるか、みたいなところが一つのmuqueらしさにつながっていますので、そこの意識はどの曲にもあります。
takachi:打ち込みが多いからこそ、生のものを入れることで、「人間味を足す」じゃないですけど、無機質なものが温かみのある、なじみやすいサウンドになっていく。その塩梅は気にしながら作っています。
小山内:細かく考えていくのですね。もうありがたくて、普通に聴けないです(笑)。
Asakuraが原作を読んで泣いて感情移入しながら書いた歌詞
小山内:続いてはいかがでしょうか?

Asakura:「♪掌(てのひら)につく砂利の跡」という歌詞を書いたんですけど、自分としては全体の中で一番好きなポイントです。
戦いに敗れる様と壁にぶち当たる様を、直接的じゃない表現で入れたくて。“砂利”という、海の砂浜を匂わせるような感じと、“跡”では「砂利がずっとついていた」という(時間経過)を表現したくて。それが結構うまくできたなと、自分的には思っております。
小山内:歌詞はどういうところから生み出すのですか?
Asakura:「♪掌につく砂利の跡」は、最初なかなかメロディにハマる歌詞ができなくて、スタッフさんと車の中で「なんか良いフレーズないかな」とずっと考えて、出てきました。
小山内:今回の歌詞作りは苦労しましたか?

Asakura:(顔をしかめながら小声で)…そうですね。めちゃめちゃ(時間が)かかりました。(原作コミックも読んで)イメージしながら作りました。泣いて感情移入して(笑)。
小山内:ちなみに、みなさんは歌詞と曲、どちらを先に作るのでしょうか?
takachi:僕たちの場合は、まず僕が先にトラックを作って、そこにAsakuraがメロディと歌詞を乗せます。トラックとは(楽曲の)土台になるサウンドやドラムのことで、メロディは歌の部分になります。
小山内:Asakuraさんは、歌詞だけではなくメロディも作るんですか?
Asakura:そうですね。メロディラインと歌詞の両方を作ります。(takachiさんが)リズムが重要なトラックを作ってくるので、そこにハマるメロディを作って、あとから歌詞を当てていくという感じです。メロディはガッツリPCと向き合って「やるぜ!」って感じで作ります。
Kenichi:たまにメロディと歌詞が同時に“降りてくる”こともあるって言ってなかった?
Asakura:そうですね。考えまくって難産なときと、メロディと歌詞が同時に降りてきてそのまま使えるときもあります。
takachiさんによるトラック作りの緻密さ、作詞に加え、メロディも作るというAsakuraさんの話に、小山内アナは興味津々。
さらに「難産だった」という『The 1』のメロディメイクについて聞いていきます。