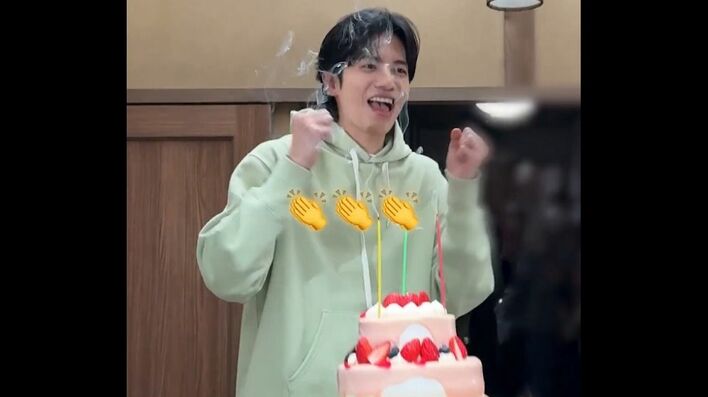地上波民放ドラマの可能性はまだまだある
――ひまり(増田梨沙)の実の父・康太(奥野瑛太)が登場した6話もとても見ごたえのある回でした。
令和に入って放送されたホームドラマとしては、トップクラスの出来ではないかと、キャスト全員のお芝居のクオリティが素晴らしかったと思っております。
繊細でやさしく誰も傷つけない、すべての登場人物への愛を感じる蛭田直美さんの圧倒的な脚本に触発され、香取さん、志尊さん、奥野さんが最高の芝居をみせてくださいました。

僕も担当の谷村(政樹)監督も脚本段階から手ごたえがある回でしたし、まだまだ配信でも見られるので、もっと多くの方に見ていただきたいです。一平の「死んで嬉しいなんて、そんな社会は間違っている」というセリフに救われる人もたくさんいるのではないでしょうか。
――北野さんはNHKの報道記者出身ですが、以前からドラマを制作してみたいという願望があったのでしょうか?
ドラマ業界を目指すきっかけになったのが、『北の国から』(1981年~2002年)や山田太一さんの『早春スケッチブック』(1983年)、岡田惠和さんの『彼女たちの時代』(1999年)、坂元裕二さんの『わたしたちの教科書』(2007年)など、もとからフジテレビのドラマ好きだったことで。
※上記人名はすべて脚本家。作品はすべてフジテレビ放送のもの。
大学時代はジャーナリズムを学んだり、短編映画やドキュメンタリーを撮ったりしていて、報道にもドラマにも興味がありました。NHK入局後は報道記者からスタートし、ドラマ部では大河ドラマで助監督などを経験しました。
その後、運よくプロデューサーになり、NHKエンタープライズに出向した際には、WOWOWに企画を持ち込んで、連続ドラマW「フェンス」を作らせてもらったりしました。ドラマは子どものころからずっと好きなものでした。

――『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』がフジテレビで初めて手がけた作品となりましたが、手ごたえや今後の課題など聞かせてください。
制作的なことで言うと、予算規模とスケジュールの問題は感じました。これはNHK時代から思っていることは同じですが、制作費を増やして、もっと時間をかけて台本作りや撮影準備、ポストプロダクションを丁寧に行わないと、日本のドラマは海外ドラマに追いつくことが難しいのではと危機感を抱いています。
今後は、良質な作品を作ることと視聴率を取ることの両方ができて、初めて民放のプロデューサーだと思うので、その両方が実現できるプロデューサーを目指したいと思っています。