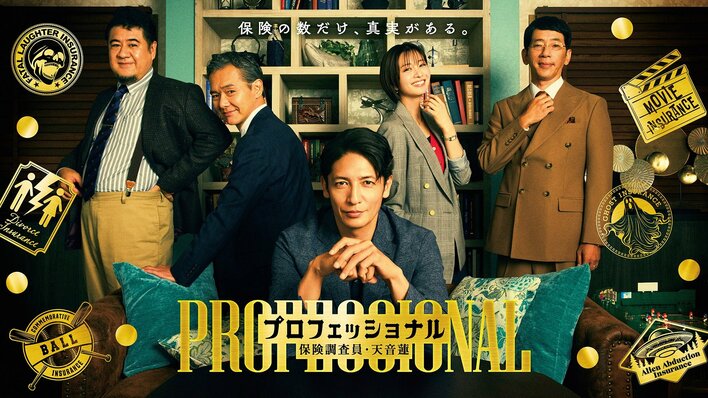“フジテレビの医療ドラマ”の新しさを考えてみる
っというわけで、僕、一応、宮藤官九郎世代ですし(『池袋ウエストゲートパーク』も『木更津キャッツアイ』も青春時代の高校生だったし!)、人並み程度には、宮藤さんのドラマは一通り、見てはいる…つもり…なんですが、“宮藤官九郎作品”とはなんぞや!?という視点で語って勝てる自信はないので(誰に!?)、『新宿野戦病院』が、“フジテレビの医療ドラマ”として、どう語れるか?で勝負してみたいと思います!(勝負!?)
僕が思う、“面白い医療ドラマ”、それは、“新しさ”にあると思います。なぜなら、ドラマ好きの方なら当然ご存じ、医療ドラマは、毎年数多の作品が作られていて、だからこそ、“新しさ”がなければ、視聴者の琴線には触れない=面白くない、からです。
そこで、フジテレビにおける、医療ドラマの歴史を振り返ってみると、そのパイオニアは『救命病棟24時』(1999年~2013年まで5シリーズ制作)でしょう。
なぜなら、“天才医師”が主人公というその後の医療ドラマの基本ともいえるフォーマットができあがっていったのはもちろんのこと、今作から劇的な進化を見せたのが“映像”です。
この作品は、本物さながらのリアルなセットを組んで撮影し、これを境に画的にも本格志向な“医療ドラマ”が増加していきました。だもんでこれが、日本の医療ドラマの“新しさ”の原点といっていいでしょう。
また『白い巨塔』(2003年)は、原作ありのリメイク作とはいえ、医療ドラマに“権力闘争”の構図が加わったことが新しく、『Dr.コト―診療所』(2003年~2006年までに2シリーズ制作され、2022年に映画化)は、島民たちとの人間ドラマも交えた点も新鮮でしたが、それまでの医療ドラマには見られなかった“大自然”が新しさでした。
そして『コード・ブルー-ドクターヘリ緊急救命-』(2008年~2017年まで3シリーズ制作され、2018年に映画化)は、まさに“ドクターヘリ”という当時の最先端医療と、群像劇をかけ合わせた点が新しく、変化球でいうと、『医龍』(2006年~2014年まで4シリーズ制作)は、それまではほとんど映し出されることのなかった手術シーンの詳細(内臓まで)を、つまびらかに映し出す視点が新しく、直近の『PICU 小児集中治療室』(2022年~)は、天才ではない若い医師の成長とホームドラマを融合させた点が新しかったり…と、特に、フジテレビが作ってきた医療ドラマはどれも“新しさ”が満載で、だからこそ、名作が多いとされているのです。