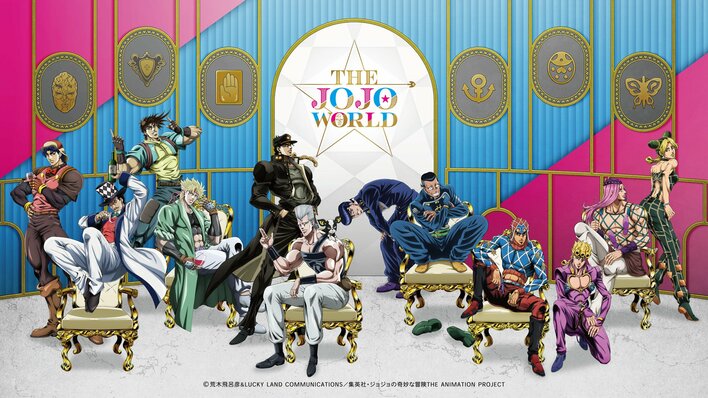第33回東京国際映画祭と国際交流基金アジアセンターによる共同トークイベント『アジア交流ラウンジ』。
11月7日(土)の回では、「ジャ・ジャンクー×黒沢清」が開催され、映画「スパイの妻」(2020)で第77回ヴェネツィア国際映画祭銀獅子賞(監督賞)を受賞した黒沢清監督が登壇。
ジャ監督が体調不良で欠席となったため、モデレーターであり、ジャ監督作のプロデュースも手がけてきた東京フィルメックスのディレクター・市山尚が、代わりに黒沢からの質問に答えることに。
映画の作り手ならでは黒沢の視点が、中国映画界の「第六世代」として知られるジャ・ジャンクー作品の核心を浮かび上がらせた。
黒沢監督がジャ監督の映画の作り方に切り込む
黒沢:ここ数年で急激に中国映画のレベルが格段に上がっていると感じます。その最大の理由はロケ場所ですね。ここで面白い映画が撮れる、という強い確信のもとに撮られているのをひしひしと感じる。
そういう場所は、古くもなく新しくもない開発途上の場所ですが、ジャ・ジャンクーは中国のそうした場所で一貫して映画を撮っていらっしゃる代表。
カメラポジションを含めて、よくこんなところ見つけてきたという驚くべき場所が多々見受けられるんですが、探しに探して、あの場所にたどり着いたのか。あるいはその場所を見て、そこから物語を考えていらっしゃるのか…。
市山:黒沢さんがおっしゃったとおり、ジャ・ジャンクーの映画でロケーションは非常に重要な要素。全体のストーリーが決まったあとで、ロケーションを探しに行っていると思います。
主要なロケーションを決めて、そこから脚本を書き始めているので、第一稿を見るとどこで撮るかはっきりわかる脚本をいつも書いてきています。
一番極端な例は、ベネツィア映画祭金獅子賞を獲った「長江哀歌」(2006)です。もともとは三峡ダム建設で沈んでいく町でドキュメンタリーを撮るつもりでした。ところが、そこでさまざまなドラマを目撃して、突然閃いてドキュメンタリーと並行して劇映画を撮ろうということに。ロケ地から完全にインスパイアされた例です。
黒沢:ジャ・ジャンクー作品に限らず、1980年代とか2000年とか、ちょっと古いような時代設定も日本だと大変。「ちょっと古い」に見える場所がないからです。ジャ・ジャンクーはそうした時代設定をあえて選んで、その時代に見せるためにどれぐらい苦労してらっしゃるのでしょうか。簡単にそういう場所も見つかってしまうのですか?
市山:「山河ノスタルジア」(2016)と近作の「帰れない二人」(2019)は、両方とも2000年くらいから始まって20年ぐらいの長い時間にわたる作品なので、苦労はありました。
ただ、北京や上海ではなく山西省の話。「山河ノスタルジア」の商店街の通りやディスコなど、何も変える必要がない場所が、まだ山西省には残ってるんですよ。
黒沢:とはいえ、「少し古い」という時代設定にすると、なかなか撮影は簡単ではない。それでも、少し古い時代から現在に至るような物語を好んで取り上げる理由といいますか。近代史みたいなものに興味があるから、開発中みたいな場所に興味を示されているのでしょうか。
市山:ジャ・ジャンクーが映画を撮り始めたのは、1997年の「一瞬の夢」。20年ちょっとのキャリアの間に、経済的にも大発展した中国の変化を、彼は映画を撮りながら目の当たりしてきた。
「山河ノスタルジア」を撮る前に作られた、ウォルター・サレス監督のドキュメンタリー「ジャ・ジャンクー フェンヤンの子」(2014)で、「中国はこの20年でものすごく豊かになった。ただ、「プラットホーム」(2000)や「世界」(2004)に出ていた若者たちが今の中国を見たときに、果たしてこれは彼らの理想としたものだったのだろうか」という疑問を言った。
つまり、豊かになればなるほど失われていくものは大きいと。それが「山河ノスタルジア」に向かわせたひとつだと思います。
黒沢:物語についても聞いてみたいんですが、「帰れない二人」もそうですけども、近年の作品は非常に独特な映画であると同時に、一組の男女が出会ったり別れたりするメロドラマの構造が骨格となっている。つまり、一種のジャンル映画的な物語。
「罪の手ざわり」(2013)もジャンル映画的な要素を持っていた。キャリアを重ねていくうちに、自然に一般の人にわかりやすい構造を選ぶようになったのか。それとも、何かがきっかけで取り入れようとされたのですか?
市山:ジャ・ジャンクーの、最初のジャンル映画的なものは、「罪の手ざわり」のライフルで撃ち殺す男の話ですね。ジャ・ジャンクーは香港のギャング映画の大ファンなんです。
「一瞬の夢」の映画館のシーンで聞こえてくる音声は、ジョン・ウー監督の「狼 男たちの挽歌・最終章」。「帰れない二人」がチンピラの抗争から始まってメロドラマになっていくのは、80年代の香港映画が影響を与えているのは間違いないですよ。
黒沢:ジャンル映画的なバイオレンス表現は、開発途上の場所に住む人間を撮る作品とは違う難しさがあると思います。そのへんはたやすくやってらっしゃるのか。あるいは相当苦労してバイオレンスシーンを撮っていらっしゃるのか。
市山:「罪の手ざわり」の第1話のライフルで撃つストーリーは、香港からアクション監督を招いてワイヤーを使うなど、伝統的な香港アクションの作り方をして、彼のリアリズムで撮るものとはちょっと違った撮り方をしていた。
その一方で、「帰れない二人」の殴り合いシーンでは、アクション監督のつけた振りは本人の作家性から言ってちょっと違うと、「もう少しリアルにしろ」と、自分でやってみせていて。役者はもしかしすると、本当に(パンチが)当たってるところもあって、痛い撮影をしていたかもしれないんですけど。
黒沢:そういった方向を、今後もっと進んでいこうとしていらっしゃるのでしょうか。中国でも完全なアクション映画みたいなものもどんどん作られていますし、可能なら香港やハリウッドで撮ってみたいというような思いがあるのかどうか。
市山:実はそういう企画も、いくつか待機してる中にありますね。「罪の手ざわり」の前に、義和団の若者たちを描いた「在清朝」という武侠映画を撮ると中国では大々的に発表されていました。
ジョニー・トーが香港のスポンサーに頼まれて、ジャ・ジャンクーにコンタクトをとって、製作費も全部香港が出す大アクション。シナリオも書いて全部準備してたんですが、キャスティングがうまく決まらず、中止になって、いまだに撮られていないんですけど。
西洋と戦うために武術を訓練するんだけど、結局、それが役に立たないと気づいて、中国が列強に占領される道をたどるという非常にジャ・ジャンクー的な題材を扱ったものですが、構えとしてはすごいでかい娯楽映画を企画していたことはありました。
黒沢監督がジャ監督作品がキッカケで“あの曲”が大好きに
ここで、オンラインで鑑賞していた観客から黒沢が質問を受けることに。「印象に残っているジャ・ジャンクー作品」を聞かれ…。
黒沢:どれもいいですが、デビュー作「一瞬の夢」は最初に見たということもあって、強烈に印象に残っています。
意外と忘れられないのが、「プラットホーム」で若者たちが演劇の準備をするシーン。70年代にヒットした「ジンギスカン」の中国版が延々かかっていて。あの曲に何の思い入れもなかったんですけども、あのシーンを見て以来、大好きになって。強烈に覚えてます。
「帰れない二人」の冒頭の「Y.M.C.A.」とか、すごく通俗的な曲がガンガンかかるっていう。ああいう使い方、好きですよね。
黒沢監督が興味を持っているロケーションとは?
トークの話題となったロケーションにちなみ、「『ここで撮ってみたい』と思う場所はあるか」という質問への回答も興味深かった。
黒沢:「ここで撮ってみたい」という素直な欲望はなくはないんですが、それは封印することにしています。そんなこと言っても、そこで撮れるわけがないと。ですから、制作部が「ここなら撮れますよ」と見つけてくれた場所を見て、「なるほど、ここなら撮りたいな」と思えるかどうか。そこがスタートだなというふうにやってきましたので。
ただ、本当に何やってもいいって言うんでしたら、今、渋谷で撮れたらどんなに楽しいだろう。
今、渋谷の街は大改造の途中で、のちのち一体どうなるのか想像つかないぐらいまったく新しいビルが建つ一方で、これまであったビルや街並みがすべて破壊されていてですね。非常に興味深い状況になっていて、「あそこを使えば相当面白い映画が本当は撮れるんだよな…」といつも思いながら、「いやいや、そんな欲望を持ってはいけない」と自制しながら、渋谷の街をいつも通過しております。