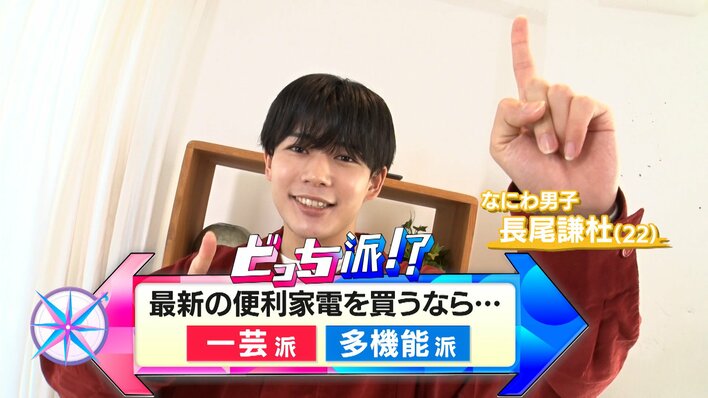ソニー損保の「安心ってなんだ?研究所」プロジェクトの活動の一環として、安心についてのノウハウメディア「安心研マガジン」第4号が公開された。今回のテーマは「コロナ禍、安心につながったデザイン(※「企画」「設計」などの意)」。脳科学者・中野信子が「新時代のデザインと安心」を語った。
<中野信子 コメント>
――コロナ禍、多くの社会課題が浮き彫りになりましたが、見つめ直すべき課題についてお聞かせください。
結論から言うと、私たちの能力に見合った社会を作るしかない、と思っています。人間が処理できるコミュニティサイズを大きく超えた「軋(きし)み」により、コロナ禍ではさまざまな社会課題が浮き彫りになってしまった。個人的に問題だと思うのは、処理できる人数を超えると人間を記号として処理してしまうことです。はるかに超えた人数を記号として処理するとどうなるのか。記号は「傷つけていい」ものにされてしまいます。アメリカのヘイトクライムの問題がそうだったし、日本でもきっかけさえあれば起こりえます。集団心理の視点でみると、日本でもお店や個人への攻撃が多くありました。
その一方で、素敵なサービスだなぁと思うものはありましたよね。「Smile Food Project」(最前線で闘う医療従事者に喜びを届けたいと、寄付によりシェフが作った食事をデリバリーする取り組み)のように、感謝の気持ちを分かりやすい形で届ける仕組みはその代表例かもしれない。見える形で感謝を表現するのってなかなか難しいもの。
「おてらおやつクラブ」(全国のお寺にお供えされる「おそなえ」を、仏様からの「おさがり」として頂戴し、経済的に困難な状況にあるご家庭へ「おすそわけ」する活動)も素晴らしくて、グッドデザイン賞の受賞に相応しい取組だと思います。人間の個人の意思というより、社会全体の意識が人を活かす方向に働いている。これぞデザインの力でしょう。
©︎ソニー損保の「安心ってなんだ?研究所」
https://www.sonysonpo.co.jp/anshinken/article/006.html#inbox03