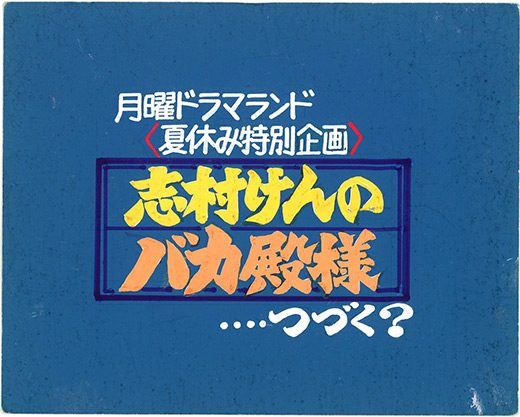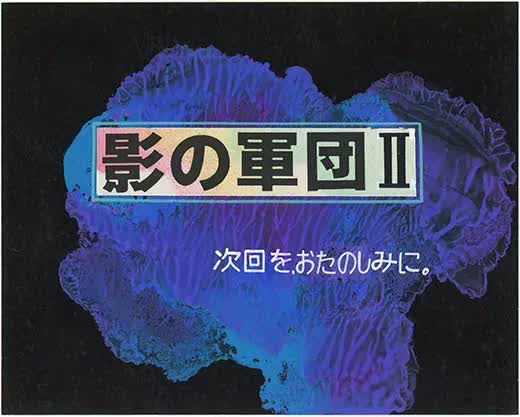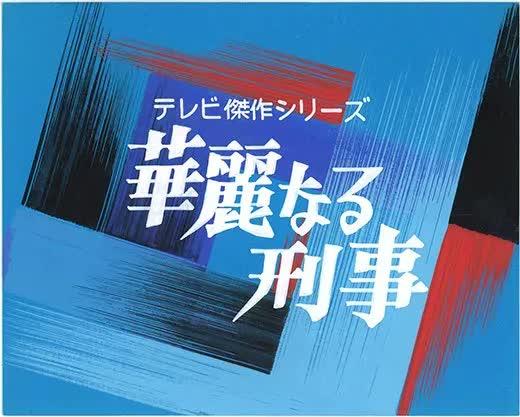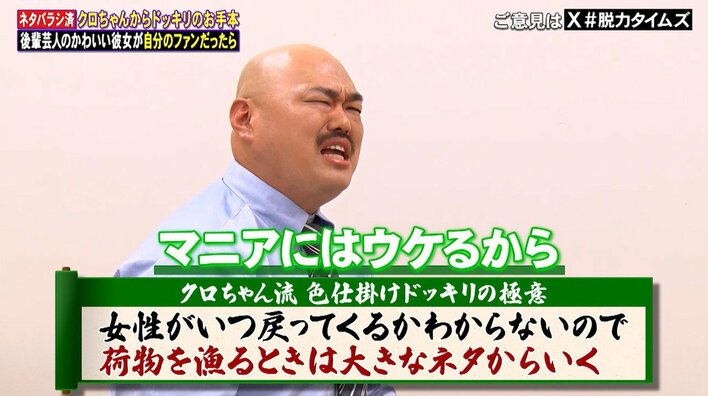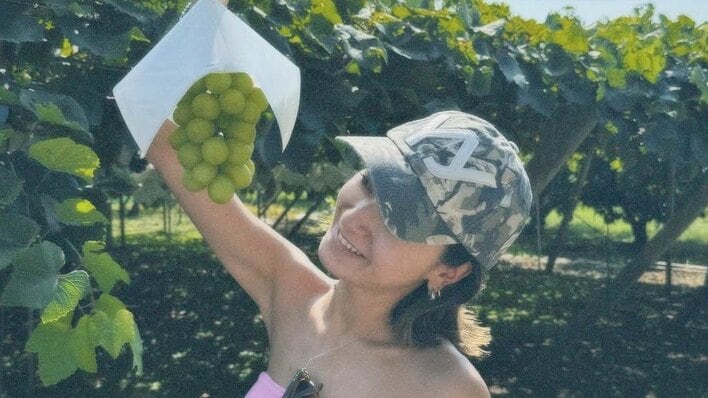テレビ放送開始から’80年代まで全盛だった、テロップ制作の様子を紹介します。
この記事は、フジテレビジュツのヒミツ「はい!美術タイトルです」vol.1から引用し、構成したものです。
岩崎光明
タイトルデザイナー
<プロフィル>
1982年よりフジテレビタイトルデザイン室でタイトルデザイン、イラストなどの制作を担当。代表作は『邦ちゃんのやまだかつてないテレビ』、『ウッチャンナンチャンのやるならやらねば!』、『ダウンタウンのごっつええ感じ』、『世にも奇妙な物語』など。
題名の「美術タイトル」(略称は美タイ)は、河田町フジテレビ時代の名称。美術タイトルは、報道以外の全番組を担当。
報道番組の写植などを制作する「報道タイトル」は報道部にあり、役割はまったく違っていました。
「はい!美術タイトルです」vol.1
① テロップ・フリップの種類と制作道具
テロップとは、画面に表示される文字情報のことをいいます。現在ほとんどのテロップ制作にはコンピューターを使ったテロップシステムが使われていますが、テレビ放送開始から’80年代までの約30年の間は、手書きテロップが全盛でした。
ここでは、そのころのテロップ制作の様子を紹介したいと思います。
アナログ時代のテロップは、黒く塗られたハガキ大の紙で、“スーパーテロップ”とか“テロップ”と呼ばれていました。
テロップには、筆とポスターカラーで白い文字を書きますが、情報番組では6mmくらいの文字を画面下位置に2行程度で表示するものがよく使われました。
白い紙に書けばいいものを、なぜわざわざ黒い塗料を塗った紙に書くのかよく聞かれたものですが、理由の一つはハレーション防止のため、もう一つはポスターカラーの定着を良くするためです。
粒子が細かい塗料で塗られたテロップの表面は、非常に平滑で、普通紙に書いたときに比べポスターカラーの描線はとても滑らかなものでした。
当時の生放送時の制作状況です。15時オンエアのワイドショーの場合、テロップ原稿は、10時ごろから出始めます。
一回の放送で数十枚のテロップと数枚のサブタイトル(コーナーの見出しタイトル)の発注がありました。
多いときには、100枚を超えるテロップ発注もありました。テロップ書きは各曜日の担当者が基本的に一人でやっていました。
現在のコンピューターによる制作システムでは、500枚以上のテロップを出す情報番組も珍しくないようですが、人間が筆で書く枚数には限りがあり、テロップ一行の文字数制限もあったので、当時の番組制作者は今以上に言葉選びと文章作成に気を遣い、文字数やテロップ枚数を抑えていました。
テロップ制作と併せてフリップ制作というのもあります。テロップ書きと並行してフリップ発注があったときは、とても慌ただしい作業となりました。
フリップは、B4サイズの厚紙のボードで、文字情報が多くテロップサイズに収まらないときや、イラストやグラフ表示があるときに使われました。
スタジオで出演者が手持ちで使用したり、固定したフリップを取り切り撮影で使ったりしました。
数は少なくなりましたが、現在もバラエティや情報番組で使われています。もちろん手書きではなく、コンピューターとプリンターを使っての制作になっています。
テロップの種類
スーパーテロップ
カメラの映像に白く文字だけが合成されるもの。生放送やバラエティ番組など、内容に合わせたデザインの手書き文字が必要なときに使われました。
ライブテロップ
背景込みで書かれたもので、そのままがテレビ画面に映ります。洋画劇場の声優テロップ、告知、番組の扉など’90年代半ばまで使われました。
スーパーテロップ(黒)とライブテロップ(カラー)があります。
どちらも125mm×100mm の紙に水性塗料が塗られているもので、この上にポスターカラーで文字やイラストを描きました。
ライブテロップの色数は豊富でしたが、テレビでの発色がよい青系がよく使われました。
ロールテロップ(縦と横の2種類あり)
横や縦にスクロールする文字が映像に合成されます。エンディングのスタッフロールや番組中のお知らせなどに使われました。
ロールテロップは、巻紙状のスーパーテロップです。
文字が縦方向や横方向に移動していくもので、スタッフロールやお知らせなどに使われました。
巻きぐせがついているのでしごいてのばし、さらに文鎮で両端を押さえながら書いたものです。テロップカードに比べて紙質が悪いせいか、表面がざらざらしていて書きにくかったのを記憶しています。
ドラマのエンドロールなどでは、数mになる長いものもありましたが、鉄筆で下書きの罫線を引き細かい文字を筆で書くのには、高い技術が必要でした。
紙のロールテロップは、手書きも写植(写真の原理を用いて印字する方法)もありましたが、90年代中ごろにはほぼ使われなくなりました。
倍フリップ 540mm×387mm
スーパーフリップは、356mm×270mmの、テロップカードの大きなものです。
用途は
・テロップカードに書くには情報量の多いものやグラフなどの複雑なもの
・ワイドショーのサイドマークをスタジオの生カメで撮影し合成
・メインタイトルのデザイン(スーパーフリップに大きく書き、それを写真撮影してテロップサイズに縮小したものを使っていました)
ライブフリップは、今でもパソコンとプリンターで作られたものが使用されていますが、当時は紙のボードにポスターカラーやマーカーを使って書いていました。
生カメラで取り切り撮影したり、出演者が手持ちで使用したりするのは現在も同じです。
ライブテロップにも、塗料が塗られたタイプとラシャ紙の貼られたイラストボードタイプがありましたが、マーカーで手軽に書けるイラストボードタイプがよく使われていました。
色もテロップと同じくらいの種類がありましたが、マーカーで書く都合上、クリーム色などの薄い色のフリップ用紙がよく使われました。
写植テロップ(スーパーテロップ)
写真植字で作られたスーパーテロップ。写真のシステムを利用したもので、露光・現像・乾燥の工程が必要で制作に時間がかかるため、レギュラーで使うものや制作時間の余裕があるものに使われました。映像に文字がスーパーインポーズされます。
番組エンディングのスタッフクレジット
写植テロップ(ライブテロップ)
提供テロップ、告知テロップなど単純なブルー背景のテロップ。ブルー背景がそのままテレビに映ります。
スライド
テロップやフリップの原画は、紙と絵具で作られているため傷や汚れがつきやすく、耐久性が低かったので、静止画のCMや何度も使用するものは、テロップやフリップに描いた原画からスライドフィルムが作成されました。
スライド作成のための原画として描かれたもの
テロップ、フリップ制作の道具紹介
・テロップ制作定規
テロップにセーフティゾーンを鉄筆で書き込みます。
・筆
文字を書くのには、ゴチック面相を使いました。筆の太さは、6段階ほどあり、文字の大きさによって使い分けていました。
広い面の着彩には平筆。荒々しい掠(かす)れ文字を書くのに、筆の先端をカッターで断ち落としてバサバサにすることもありました。
・三角定規直
線定規と合わせて平行線を引くのに使います。12cmほどの小さいサイズ。
・直線定規(溝引き定規)
溝引きというのは、筆で直線を描く技法のこと。箸(はし)を持つようにガラス棒と筆を持ち、ガラス棒の先端の丸い部分を、定規の溝に滑らせて直線を描きます。
・ディバイダ
コンパスのような製図用具。テロップに二本の平行な罫線を描くために使います。
・鉄筆
昭和の時代にはよく使われたガリ版印刷で原稿を書くのに使われたものです。テロップ制作では、罫線引き・文字割り・下書きなどに使います。テロップ制作の必需品でした。
・文鎮
ロールテロップを書くときに、両端において巻紙のカールを抑えます。
・ポスターカラー
スーパーテロップには、白い絵具で文字を書き、修正には黒い絵具を使います。テロップ専用のものではなく、市販の不透明水彩ガッシュ。
・マーカー
フリップに文字やイラストを描きます。
・国語辞典、漢和辞典
あやふやな漢字は、必ず調べるようにしていました。昔も今も文字の間違いは厳禁です。
懐かしい番組タイトルが続々!テロップ作品紹介
② 表現法とテロップの作品群
実際に使われたテロップの数々を紹介します。
アナログ時代の動くタイトル
現在のコンピューターベースのテロップシステムでは、テロップの動きも自由自在。3D表現も珍しくありません。しかし、アナログ時代にもありましたよ、動く文字演出!
前述のロールテロップは、横や縦方向に文字が動くものでしたが、ほかにも「起こし」「回転」 「引き抜き」 というものがありました。
「起こし」は文字がこちらに起き上がってくるように現れるもの。
「回転」は、高速回転する文字が現れ静止するもので、昔の映画では新聞の輪転印刷機にオーバーラップするようにスクープの見出し文字が回転して現れるなんていうシーンでよく見かけました。
どちらも、テロップには特に仕掛けはありませんので、テロップを起こしたり、回転させたりする装置がついたテロップマシンがあったのだと思います。
この機械の話になると、私は送出を担当する部署に自由に出入りすることができなかったので、詳しいことはわかりません。
「引き抜き」は、文字一行がワイプして現れるものです。これは、タイトルデザイナーがテロップに仕掛けを作りました。
テロップに窓をくりぬき、重ねたもう一枚の方に文字を書きます。短冊状の引き抜きが通るレールを作り貼り合わせて完成。短冊を引き抜く様子をカメラで撮影し、文字だけ合成するのが引き抜きのスーパーテロップです。
「引き抜き」は、テロップだけでなくフリップでもよく使われました。ランキング形式やクイズの解答などで利用されましたが、中には十数段になるものもあって、建具スタッフさながら厚紙のフリップを切って精度の良い引き抜きの仕掛けを作るのは、大変な作業でした。
出し入れが固い場合は、滑りを良くするために引き抜き部分にロウを塗ったり、カッターで削ったりするなどの苦労もありました。
そんな手間のかかる引抜きフリップは、手軽に制作できる「めくり」というものに変わっていきました。
これは、今でもワイドショーのパネル演出でおなじみの方法で、隠しておきたいところに貼っておいた目隠しの紙をペリッと剥がしながら説明するものです。
「めくり」はお手軽な分、少し安っぽい感じがしたのでしょうか、’80年代には「引き抜き」にこだわるディレクターも少なくありませんでした。
スタジオカメラマン大活躍のフライングテロップ
バラエティ番組の多くはスタジオ収録、編集所での編集作業を経てオンエアされます。
編集所では、文字に色をつけたり動きなどのエフェクトをつけることができます。今では編集所に行かなくとも、通常のテロップシステムで文字を動かすことはできるようになっています。
80年代は、編集所で文字を動かすことはできましたが、生放送で文字を動かすようなシステムはまだありませんでした。
私が担当していた情報系バラエティ番組『TVグラフィティ』では、とても面白い方法で「フライングロゴ」を実現していました。
通常、テロップはテレシネという送出の部屋に持っていくのですが、この番組では芸能コーナーのサブタイトルのみスタジオに置かれた黒いパネルにテロップを貼り、それを生カメで撮影していました。
ここからは、カメラマンの腕の見せどころ。
なんと、カメラワークでテロップの文字をフレームイン、フレームアウト、ゆらゆらと揺れたと思ったらビヨーンとジャンプしたりと、自由自在に動かすのです。
編集所でなければ文字は動かせないと諦めていたら出てこない発想です。アナログ時代のテレビマンの知恵と技に、タイトルデザイナーになったばかりの私は感動してしまったのでした。