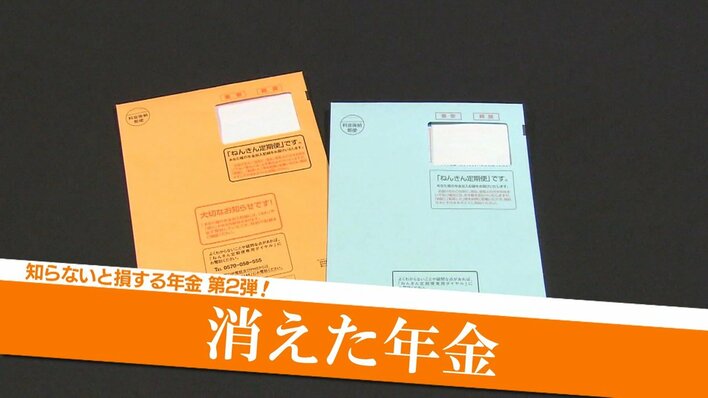2000年11月に日本で発売された、スペンサー・ジョンソン氏の著書『チーズはどこへ消えた?』を知っているだろうか。
全世界2800万部、日本国内だけでも400万部も売れた、Amazon史上最大のベストセラー作品だ。
アメリカでは1998年の刊行当初から、世界を代表する企業や官公庁で研修用のテキストに採用された書籍。最近では、メジャーリーグの大谷翔平選手が、日ハム時代に愛読していた本としてテレビ番組内で紹介されて話題になった。
「チーズ」をあなたの大切なものに置き換えて…
読んでいない人にとって『チーズはどこへ消えた?』というタイトルだけでは、なぜ様々な企業や人に影響を与えているのか想像しにくいだろう。
物語は、2人の小人と2匹のネズミが迷路の中からチーズを探すというもの。
小人の「ヘム」と「ホー」、ネズミの「スニッフ」と「スカリー」は日々、迷路をさまよい歩き、ついにチーズのある場所「ステーションC」を見つける。これまでの努力が報われたと喜び、チーズを頬張っていたのだが、ある日突然、チーズが消えてしまう。
そんな時、どんな行動を起こすことができるか。
各々の性格や考え方の違いが顕著に表れる。小人の「ヘム」は悲観して過去にとらわれて前へと進めない。小人の「ホー」はチーズを失ったことにショックを受けるが悩んだ挙句に再び前を向く。ネズミの「スニッフ」と「スカリー」は、すぐに別のチーズを探そうと前へと歩き出せる。
それぞの違いはあるものの、誰もが「ヘム」「ホー」「スニッフ」「スカリー」それぞれの面を持ち合わせていることに気づく。
チーズを自分の仕事や恋人、人生のあらゆる選択肢に置き換えると、また違う見え方ができる。
勝間和代さんが語る「ヘムと私の共通点」
『チーズはどこへ消えた?』から19年。「チーズ」の続編として、『迷路の外には何がある?』が発売され、話題となっている。
『チーズはどこへ消えた?』は、変化に適応していくホーを中心とした物語だったのに対し、『迷路の外には何がある?』は変化を受け入れないヘムの物語だ。
アメリカでは、2018年11月に初版10万部で発売されると、その直後にウォールストリートジャーナルのベストセラーリスト10位にランクイン。その他、ワシントンポスト、フィナンシャルタイムズなどにも紹介された。その勢いで、2019年2月に日本でも発売となった。
著書のジョンソン氏は、病床で続編を書き続け、2017年7月に亡くなってしまう。
『チーズはどこへ消えた?』 のファンでもある経済評論家の勝間和代さんは「“チーズ”は、いかに私たちが過去の信念に迷宮のように閉じ込められているか、という意味で表現されています。著者の凄さは、誰でも薄々わかっていることをシンプルな寓話で、『なるほど、そういうことだったのか』という腹落ちをさせることです」と話す。
一番の魅力は、ヘムの心や行動の変化だ。
「ヘムはなぜステーションC(過去の成功)にこだわるのか。それはステーションCがヘムのこれまでの人生のすべてであり、ヘムのアイデンティティーであり、そこを出ることは、自分のこれまでの人生を否定するかのように思えていたからです」
「幸いヘムは良き友人の行動やホーが残してくれていたヒントにより、自分の何が原因でチーズを見つけることができなかったのかという理由に気づき、前に進んでいけるようになりました」
ヘムの心境の変化は、勝間さん自身に重なる部分があるという。
「私もヘムと同様、『LGBTであることを公開すると、自分にとってマイナスのことしか起きない』と迷路の中で信じ込んでいました。また、チーズは既になくなったにもかかわらず、テレビ出演のような前のスタイルの仕事にこだわり続けていました」
「しかし、カミングアウトをしても、テレビ出演をなくしてみても、マイナスはまったくないばかりか、迷路の外には新しい世界が広がっていました。誰もがヘムのように様々な自分の過去の信念に囚われていると思います。人はどうやって過去の信念を自分と切り離すのか。この本は読者にとって、ヘムを助けた友人のような役割を果たしてくれることでしょう」
前作では「変化に対応していく」ことが素晴らしく、正解のように思えたが、続編では「あえて立ち止まることももう一つの生き方である」と示している。
変化の波に乗った方がいいのか、留まるのか。どちらを選択するにも勇気がいるが、 どちらが正しくて間違っているということではないことに気が付かせてくれる。