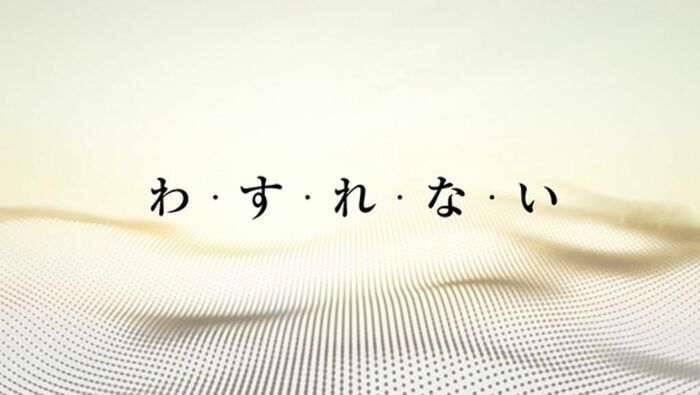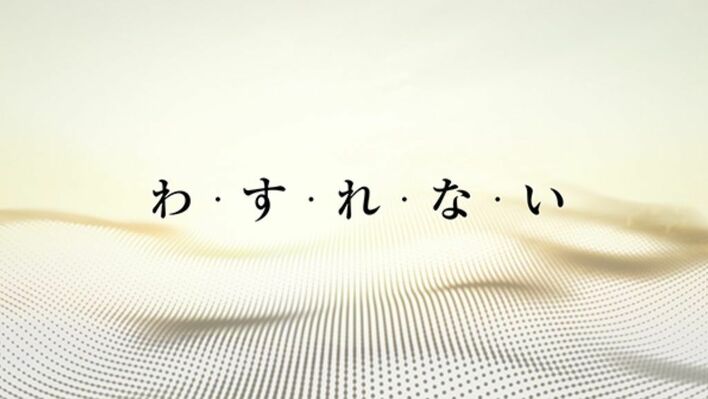2011年3月11日に発生した東日本大震災から今年で12年。改めて、当時を思い、“知り続ける”ことの大切さが見直されています。発災当時、取材・報道の現場で「伝え続けた」テレビ局のアナウンサーたちは今、知り続けることの大切さについて何を思うのでしょうか。
島田彩夏フジテレビアナウンサーは、発災当時、ヘリコプターから被災地を見て「何ができるのか」と苦悩しながら被害状況をレポートし続けたと語ります。
当時の状況、震災報道を経て思う「伝え手」としての次のフェーズ、知り続けていることについて聞きました。
<島田彩夏アナウンサー インタビュー>
――2011年3月11日、震災発生時のご自身の状況を教えてください。
お昼のニュースを担当し終わって、フジテレビの15階にあるアナウンス室で資料の整理をしていたら大きく揺れて、「これはただごとじゃない」と思いました。報道のアナウンサーは、揺れたらまず報道センターに行くというのが習慣になっているので、すぐに報道センターに向かいました。途中の渡り廊下の先に先輩の境鶴丸元フジテレビアナウンサーが歩いていたのですが揺れのせいで廊下も境さんもグニャッと大きく曲がって見えるほどでした。
なんとか報道センターに到着したら、怒号が飛び交うすごい騒ぎで、「誰か飛べるやつはいるか!?」という声が聞こえたので、「います!島田です!」と返事をしたらすぐに報道のヘリコプターに乗ることになりました。詳細がまだわからない中、「北のほうがひどいことになっているらしい」という情報のもと、羽田空港のヘリポートから、私、機長、整備士、カメラマンを乗せたヘリコプターはとにかく北に向かって飛び立ちました。
途中、千葉の海岸線上を通るとあちこちで火災が起きていたのでそのリポートをしながら、スタジオからの中継にも対応していましたが、まだ春になる前なので陽が落ちるのが早くあっという間に真っ暗になってしまって。「まだ飛ぶか、戻るか」と相談していたときに、無線から離陸予定だった仙台空港が「壊滅です」という言葉が聞こえてきましたが、そのときはまったく意味がわからなかったのを覚えています。
そして、着陸許可が降りた福島空港に着陸して一夜を過ごしましたが、空港には留め置かれた人たちがいっぱいいる状態で、ロビーにあるテレビにはNHKが映っていたのですが、そこには本当に目を疑う光景、見たこともない映像が映っていました。そこにいる皆で言葉もなく見ていましたね。
「どなたか見ていたら伝えてください」必死の思いで見えることすべてをリポート
次の日になり許可も下りたので、朝日と同時にまた飛び立ちました。当時は今みたいに詳細なナビが搭載されていなかったので、手持ちの地図を参考に簡単なナビと照らし合わせて現在地を確認するのですが、機長に「ここに集落があるから、この海岸線沿いを飛んでほしい」と伝えても、「そこを飛んでいる」と。何度も確認したら、集落は津波で流されてしまった後で、どこからが海でどこからが陸なのかまったくわからない状態の上を飛んでいるのだとやっと理解しました。
海はキラキラと朝日を浴びて波一つないのに、確かにここにあった集落がない。何かが見える場所を探しても、かろうじて建物のコンクリートの土台だけが残っていることを確認できるような状況でした。自分の頭に、「これは現実なんだ」と信じ込ませることを苦労したのを覚えています。
「ここに住んでいた人たちはどうなったのか、皆どこかに避難していて」と必死に祈りながらも、どこかで冷静な“伝え手”としてとしての自分がいるわけです。当時の放送を見ると、ちゃんと伝えている自分がいますが、実は何をしゃべっていたのかはあまり覚えていません。
上から見ると、広いところまで見えるのですが、手に持っている地図にはあるはずの集落がない。入社してからそれなりに現場に出させていただいて、レポートの経験もそれなりにありましたが、この状況には人として打ちのめされてしまったんです。
「何ができるんだろうか」「こんな風に伝えていいのだろうか」「手を振ってる人たちは寒さに震えているのではないか」「もしかしたら意識もないような方も中にはいらっしゃるかもしれない」…と報道しながら、具体的な救助を実行することができないことが苦しかったです。我々が今できることを機長やカメラマンと相談して、「レポートしている場所を細かく正確に伝えよう、そうしたら消防や警察、自衛隊とか誰かが来てくれるはずだから」となりました。
今だったらSNSが役に立つのかもしれませんが、そのときの私たちにはそういう手段がなかったので、「〇〇町、〇丁目付近です、今見る限り〇人の方が残されています」というようなことを繰り返していきました。見えることすべてをリポートし、「どなたか見ていたら伝えてください」という必死の思いでした。取材活動は救助活動を絶対に邪魔してはいけないので、救助のヘリとは干渉しないところから伝えていましたが、未だに「何が正解だったのか、何ができたのか」と苦しくなりますし、「私たちの役割とは何なのだろうか」と考えます。
変化していく被災地と共に歩むのが“新しいフェーズ”の伝え方
――震災から12年経ち、当時のことを伝える特番も減ってきた状況があります。この12年間で変化を感じることはありますか?
さらに時が経ち、もっと意識が薄まっていくであろう中で「どうやって伝えていくか」を考えるのは報道者としての責務だと思っています。 報道に関わる者として、「突き詰めると災害報道って何?」ということを考えると、何が正解なのか、正解があるのかどうか、私にも分かりません。でも、報道者としてのスタンスを考えると「人の命の確保」が命題だと思っています。
「じゃあもう1回同じことが起きたとき、自分はどうするか?」と問われると、そこにまた迷いは生じるけれど多分同じようなことをしてしまうと思うんです。伝えることで知ってもらう、知ることで助かる命もある、知ることで何かが起きたときの防災や減災に繋がるかもしれない。だから私は伝えるんだって。
フジテレビでは震災から10年を機に、3月11日に『わ・す・れ・な・い』という特番を放送しています。去年、一昨年と私が担当していましたが、今年は木村拓也アナウンサーに引き継ぐことになりました。これからは、発災当時にはまだ若かった人たちが伝える“担い手”になっていき、史実として災害を伝えていくフェーズに変わってきていると思います。
振り返って、ちゃんと分析して、変化していく被災地と共に歩むのが新しいフェーズの伝え方なのではないでしょうか。それこそ一人ひとりの物語があるのに、“被災地”と一括りで語ってしまうことは難しい。それをこれから若い取材者たちが、自分たちで考えて伝えていくことになるのだと思いますね。
――この12年でインターネットやSNSも普及し、自分で「知ること」を取捨選択する難しさもあると思います。
私は期待したいところが大きいんですよね。アルゴリズムで自分の好きなものしか目に入らないから、震災に関心がなかったら目に入らないという話にも繋がるかもしれませんが、私はそんなに捨てたものじゃないと思っています。
若い世代って、そういうものを冷静にとらえているところもあるので、我々よりもすごく上手に使いこなすことができるんじゃないかと思うし、これからの時代を生きていく人たちを信頼したいと思います。 私も震災報道の経験や反省を経て、単に見せるとか伝えていくだけではなくて、そこにいる人たちと関わりながら伝えていくということが報道の課題になってくると思っています。それがこれからの報道のあり方なんじゃないかなとも。人と関わることは、自分を見ることにもなりましね。
――島田アナが意識的に“知り続ける”ようにしていることはありますか?
仕事とは関係なく個人的に、虐待に関すること、子どもの命を守ることについて継続的に取材しています。自分で電話して取材にも行きますし、解説員として『FNNプライムオンライン』にも記事を執筆して掲載しています。
子どもって“家”がすべてで、表に出てこない叫び声を上げていても気づかれないことが多い。食べものが与えられなかったり、殴り続けられていたり、そういう子どもたちがいるという現実があります。せっかく報道機関に勤めた以上、微々たるものではありますが誰かの役に立って終われたらと思っています。
島田彩夏
アナウンス室部長職チーフアナウンサー
兼報道局解説委員