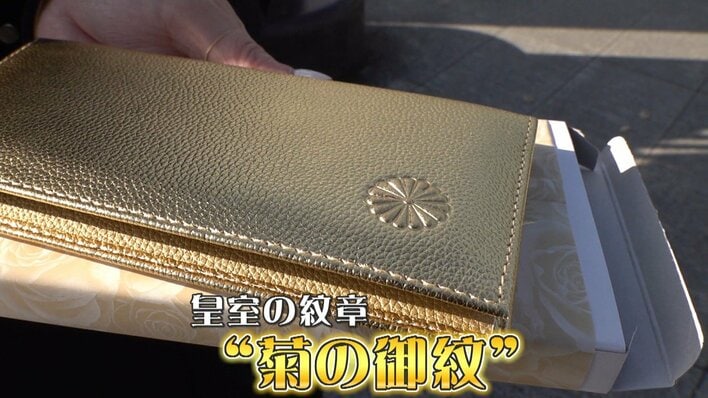10月30日(金)公開の映画「罪の声」の完成報告会が9月29日(火)に都内で行われ、主演の小栗旬と星野源、土井裕泰(どい・のぶひろ)監督と、原作者の塩田武士(しおた・たけし)氏が登壇した。
原作の小説「罪の声」は、未解決のまま時効となった実際の事件をモチーフとしたフィクションで、2016年に「週刊文春 ミステリーベスト10」で第1位を獲得、第7回山田風太郎賞を受賞し、現在累計70万部を突破している。
未解決事件の真相と、謎の犯人グループを追う主人公の新聞記者・阿久津英士を小栗が演じ、幼少期の自分の“声”が事件に使われていたことを知ってしまう、もう1人の主人公・曽根俊也を星野が演じる。
コロナ禍でのイベント開催とあり、本来1500人を収容する客席は全て空席にし、そちらに“あえて”背を向ける形で進行された。
普段とは違った会場の仕様に、小栗は「ある種すごく贅沢な使い方ですよね。でも、やっぱりお客さんが入っている客席を見たいです」とコメント。
星野も同様に「こうやって見ると、劇場ってすごく良い景色ですよね。だけどやっぱり、僕もお客さんがいる客席を見たいです」と、コロナ以前の会場の姿に思いを馳せつつ、「ですが、今回こういう風に集まれただけでも感激しています。1年半くらい前に撮影して、公開できるかも不安だったので。今はただ嬉しいです」と、胸の内をポジティブに明かした。
完成した映画をいち早く鑑賞したという小栗は、「自分が出演している作品ではありますが、いろんなことを考えながら、飽きることなく楽しめる作品だなと。中盤に僕がすごく好きなシーンがあるんですが、そこでは本当に心を鷲掴みにされました。とても有意義な時間を過ごせる映画です」とPR。
そして、「台本をいただいた時にも、原作を読んだ時にも感じたのが、『情報量があまりに多い』ということで。どうやって一本の映画にするのかと思っていたんですが、完成したものを見たらきちんと収まっていて、面白いし飽きない、映画にしかできないメッセージが込められていました」と語る星野。
続けて「見終わってすぐ小栗くんに電話して、土井さんすごいねって話をしました。土井さん、すごいっす!」と監督を称賛すると、原作者の塩田氏もやはり「重厚感がすごかったです。よく2時間にまとめたなって。監督すごい!」と、土井監督へ拍手を送った。
「映画にするのは無理ちゃうかと思った」と、映画化の話を受けた当時の心境を率直に明かす塩田氏。
「でもキャスティングを聞いたときに、ヨーク(本作の舞台の一つとなったイギリスの地方都市)を歩く小栗さんと、テイラー(紳士服の仕立て屋)の星野さんのイメージがパッと浮かんだので、『これはいけるかもしれない』と思いましたね」と振り返った。
オファーを受けた当初について聞かれた小栗は、「原作を読んで、この作品に参加しない手はないなと思うくらい、原作の持つエネルギーと、実際にこういうことが起きていたんじゃないかと思わされるような緻密なストーリーに感動しました」と絶賛。
そして「『曽根役は星野源さんで考えている』と言われたときに、ぴったりだなと」と語る。しかしそんな小栗に対し、星野は「原作を読んでみると、小栗くんがこの役をやるんだっていうのが新鮮な感じが…」と、予想外のコメント。
「と、いうのも…小栗くんの役、普通のおじさんなんです」と理由を明かして笑いを誘うと「記者というキャラクターは、もっと正義感に溢れているイメージで。小栗くんが演じた阿久津という人は、挫折を経験していて、人の気持ちをちゃんと見られる人、でもぱっと見くたびれている、という。そんな役を小栗がやるのを早く見たかったですね」とフォローした。
それを受けた小栗も納得したように頷き「ちょこっとお腹も乗っかってるくらいの感じでした、撮影の時は」と付け加えた。
そんな“普通のおじさん”を描いたはずの塩田。小栗と対面した際は、「こんなかっこいい新聞記者おらへんやろ」と思ったとか。
テイラーを演じた星野は、「数時間だけ、作業を実際に習う機会があったんですが、あとは映像を見ながら、ダイニングテーブルの上に型を広げ、チョークで描いてハサミで切ってという自主練を重ねました」と、役作りの苦労を明かす。
さらに星野が演じたのは京都生まれ京都育ちの役柄ということもあり、京都弁の扱いに苦心したという。「セリフに感情が乗ると、ついイントネーションが変わって、テレビでよく耳にする「関西弁」に流れてしまうんですよね。関西弁と京都弁は違うんだな、一概に「関西弁」くくってはいけないなと」と、新たな学びを明らかにしていた。