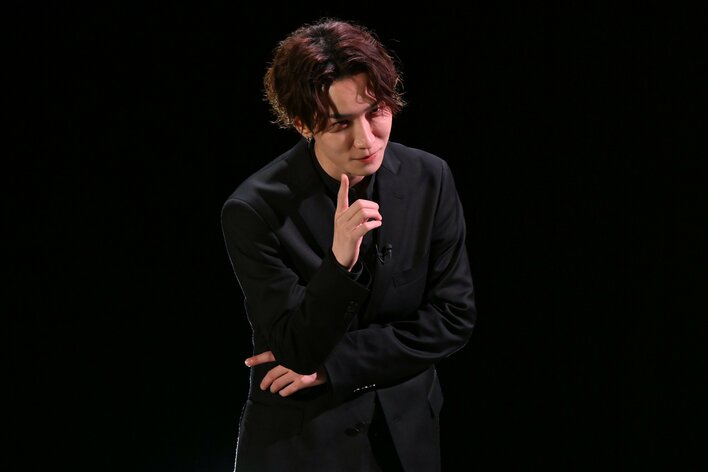毎回さまざまなジャンルで活躍するゲストが集い、多彩な話題や事象を取り上げていくフジテレビのトーク番組『ボクらの時代』。
7月18日(日)の放送は、岩合光昭、立川志の輔、さかなクンが登場。
動物写真家の岩合と、岩合が初めて監督した映画「ねことじいちゃん」で主演した志の輔。そしてその2人が「会いたかった人」として東京海洋大学名誉博士・局員准教授のさかなクンを指名し、この鼎談が実現した。
それぞれの「一生の友」との出会い
岩合にとっては高校生のときの猫との出会い、さかなクンにとっては小学2年生でのタコとの出会いが「一生の友」となり、今につながっていることが明らかに。
岩合:僕が猫が好きになったのは、高校生になってから。友達の家に行ったら、友達が肩に三毛猫を抱えて。僕の目の前で、顔を見せてくれたんです。
さかなクン:三毛猫ちゃん。
岩合:そのときに、こう、ここ(目の下)がぶわーっと熱くなってきて。涙がこう、自分自身で涙が流れて。
志の輔:それで、すぐに猫を飼おうと思ったんですか?
岩合:思ってたら、雨の日の電信柱の下に段ボールが置いてあって、子猫が2匹入っていて。もうそれを見た瞬間に家へ連れて行って、その子たちを育てて、みたいなことがあったり。
志の輔:猫は、自分と同じ空間にいる動物、生き物じゃないですか。(でも)魚は、一緒に水槽の中に入ったりとかするわけではない。(さかなクンに)これだけ愛でて、「一生の友」になるっていうきっかけは何でしたか?
さかなクン:タコが好きになったんですね、最初。
志の輔:一番最初に好きになったのは、タコ(笑)!?
さかなクン:小学2年生くらいのときに友達が描いたタコを見て、「うわ、なんだこの生き物!」って思って、「タコを見てみたい」と魚屋さんに通って。魚屋さんのタコは、茹でダコだったんで、本物のタコに会いたいと水族館や海に通って。「あ、タコだ!」って初めてタコを手にして、「すギョい、こんな力で吸い付くのか、うわー、海に引きずり込まれそうだ」って。でも、そのタコちゃんをどうしても家で飼いたくて。でも、お家に連れて帰ってもすぐ死んじゃったんですね。
志の輔:え、家で飼うことはできるんですか?
さかなクン:脱走しないようにフタをしたり、水の温度が上がらないようにしてあげたり、1個1個クリアすれば、意外と飼えるんですね。懐くんですね、本当に。
さかなクンは「(タコは)ちゃんと飼い主の顔を覚えて寄ってきたり、ちょうだい、ちょうだいってスキンシップしてくれたり」するが、「寿命が1年しかないので、意外と別れが早い」と解説し、志の輔を驚かせた。
志の輔:つまり(さかなクンは)魚、(岩合は)猫ちゃんじゃないですか。で、俺は何の専門なのかなって。専門っていうか、「何をずっとやってきたかな」と思ったら、動物の中でも、やっぱ人間なんですね。
さかなクン:ああー!
志の輔:落語っていう文学に、人間ってこんなに面白いでしょう、変でしょう、利口でしょう、ばかでしょうっていうのが込められていて。僕、18歳のときに劇場に行って、落語家、プロの方の噺を聞いて、夫婦の噺だったんですけど「ああ、なんかうちの親とよく似てるな」とか、「近所にああいうおじさんいる!」って。
志の輔は「人間を描いている落語を、一生懸命しゃべっているんだな」と、噛みしめるように語った。
学術書にない例外だらけの現場
また、岩合とさかなクンは、“例外だらけ”の動物の世界についても言及した。
岩合:僕は、雄ライオンが雄ライオンを殺すところを撮影したことがあるんですけど。それを大学の先生に話したら「同種間で殺し合うのは…」と(取り合ってもらえなかった。まあ(オーストリアの動物行動学者)コンラート・ローレンツも「同じ種を殺す動物は人間だけ」という説を…。
さかなクン:私も「アナハゼが、アナハゼ食べてました」って言ったら「そんなもん、あるわけない」「同種が同種を食うわけない」と、やっぱり同じようなことを言われました。
岩合:そうですよね。「例外を言ってはいかん」と言われたんですよ。でも、そしたら、世の中例外だらけですよね。
志の輔:うん。
岩合:実際に動物たちを見ていると、それを日々感じるんですよ。「これ、誰も何も言ってないよね」という動きを、猫でもしている。「え?猫でもこういう動きするの?」っていう。それが、(自分が)カメラを向ける最大の理由かもしれないなと思って。動物そのもの、しいて言えば、人も含めて「生きる」っていうことを見せてくれているような気がするんですよね。
2人の話に、志の輔は何度もうなずき聞き入っていた。
人の興味が移っていくのは自然なこと
また、大人になるにつれ、今まで興味のなかった物に目が行くようになってきたという話題では…。
岩合:それは、人は動物だってことですよ。
さかなクン:あぁ、動物。
岩合:そういうふうに興味が移っていくっていうのは、自然だと思いますね。小さいときは、激しく動くもので、だんだんおとなしい動きに惹かれて、今に師匠、石に興味を持たれると思います。
志の輔:あら!でも、持つかもしれないですよね。でも、ちっちゃいころから石に興味を持つ子がいるじゃないですか。
さかなクン:いますよね。お子さん、ちっちゃいときって、「わあ、これ面白い」でも「こっちも面白い」って気がどんどん移りますよね。
志の輔:ええ。移ります、移ります。
さかなクン:飽きっぽいと。でも、飽きっぽいから、成長できるってなんか聞いたことがありまして。例えば、磯魚のイシダイ。イシダイちゃん、ちっちゃいときって、もうすギョく好奇心が強くて!泳いでる人にさえ、噛みつきに行くんですね。海藻とかフジツボとか、動くエビやカニとか、なんでもついばんで食べるので、小さめなイシダイを食べると、磯の香りが強すぎてあんまりおいしくないんです。ところが、大きくなるとその好奇心が薄れてきて、もうアワビとかウニとか、おいしいものばっかりを狙って食べるようになるので、おいしくなるんですね~。
志の輔は「イシダイも大人になるにつれ落ち着いてくるんだ!」と、さかなクンの話に感心した様子。
続けて「子どもなりに、いろいろなものにちょっかい出すのは、もうそれはそれで本当はとても素敵なこと。だから、子どもが何を言い出しても驚かないような心持ちでいれば良かったな、なんていうのを、本当に今ごろになって思う」と、自身の子育てを振り返った。
子どもたちの興味や関心の芽を摘み取らないために
この話の流れから、岩合は「親御さんが、子どもの立場になって考えるっていうのはとても難しいこと」と語った。
岩合:例えば、美術館に行くと子どもが「絵がよく見えない」って言う。で、あらためてこう膝を折って(子どもの目線に合わせて)見ると、照明が大人向けで展示してあって、子どもからすると照明しか見えなくて、光って見えないとか。動物園に行くと、とても興味深いんですけど、親御さんは、すべて見て回ろうと思うんだけど、お子さんは何かすごくとても惹かれる動物がいたら、そこから動かなくなるんです。
岩合は「そのときに、お子さんと同じように動物を見てもらって、『キリンのしっぽってこうだったんだね』とか『サイってこんなに大きかったの!』とか感じてもらったら、そこで新たな発見がある」と語った。
志の輔:監督が、ものすごくその、カメラの位置が低いんですよ。
さかなクン:猫ちゃん(の目線)に。
志の輔:そう。その動物の目線にすぐになって撮るっていうことをおっしゃったんだけど、それは(今回の映画の)現場で本当に常にそうだったんですよ。もし、ここに猫がふいにやってきたとしたら、この衣装のまんまでも、たぶんこのまんま腹ばいになって寝転んで、猫を迎えるんですよ。
さかなクン:ギョギョ(笑)!
志の輔:『岩合光昭の世界ネコ歩き』(NHK)を見せてもらって、一番思うのは、猫が岩合さんの前で「見てくれよ、俺の芸」といって、岩合さんに撮ってもらいたくなっちゃって、というふうふうにも見えるぐらい。だから、仲間だと思われてるんじゃないですか、と思うぐらいに距離がなくなるんですよね。
岩合:(笑)。
志の輔:その技、すごいなと思うのは、僕はやっぱり一応、高座に出ていって、頭を下げて、一応お義理も含めた拍手をいただきながら「ようこそお越しくださいました」っていうふうに始めるわけじゃないですか。お客さんとの距離を、どうやって縮めるかっていうのが全落語家の、もっと言うなら全お笑いの、いや、もっと言うと全エンターテインメントの仕事じゃないですか。
さかなクン:はい。
志の輔:だから、それが一番ある意味で、うらやましいって変ですけど、すごいところ。いろいろなことを渡り歩いてきたから、そうやって距離をきゅっと縮められるんでしょうけど。
志の輔から、その距離の縮め方を絶賛された岩合は、すぐさま反応する。
岩合:最初にね、高座に上がられたときに、一言目に「ん、今なんて言ったの?」って。「ようこそおいでくださいました」って、聞こえるか聞こえないかの声でおっしゃるんですよ。
さかなクン:はい。
岩合:そうすると、会場のみんながもう“聞き耳ずきん”になって、聞こうとするんですよ。ご本人に「なんであんな小さい声を出すの?」って聞いたら、「だって、みんながそうやって聞いてくれるじゃないですか」とおっしゃって(笑)。
暴露された立川は「営業妨害みたいな話はやめてもらえますか」「明日から、大きな声で出なきゃいけなくなる」とぼやき、講演活動の多いさかなクンも「参考になります」と、笑顔を見せていた。