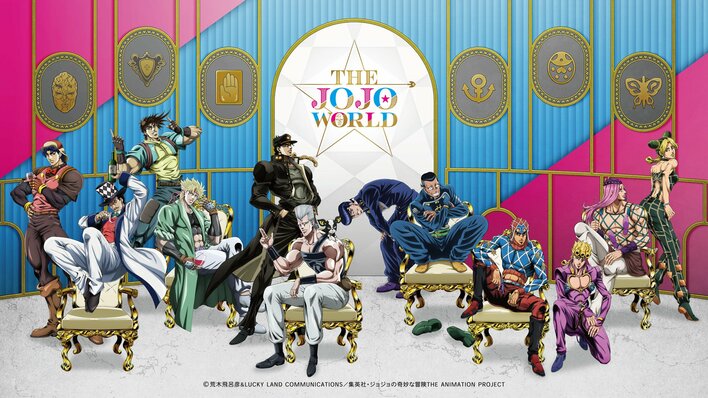11月16日(月)、新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行に備える「上手な医療のかかり方」特別対談イベントに、デーモン閣下と赤江珠緒が登壇した。
新型コロナウイルス流行下における「上手な医療のかかり方の啓発」のために厚生労働省が企画した本イベントでは、“上手な医療のかかり方”大使に任命されたデーモン閣下と、自身もコロナウイルスに罹患した経験を持つ赤江のトークセッションが行われた。
コロナ禍でどのように生活が変化したかを聞かれた赤江は、「この病気は人によって症状に違いがあり、防御の仕方にも個人個人で温度差がある」と前置きをし、「生活するうえで、どう向き合っていけばいいのか本当に難しい」とコメント。
「コロナに罹患した人に初めて会った」というデーモン閣下に対し赤江は、「まず夫、私、そして娘という順に罹った」と説明。「夫は肺炎になり入院するほどの重症に、そして私も濃厚接触者ということでPCR検査を受け、陽性が判明した」と経緯を明かした。
自身は“中等症”と呼ばれるレベルで、「から咳と37度5分前後の微熱が続いた」と説明し、「その時、娘は陰性だったので親子で陰陽分かれてしまい、親子を分離したほうが良いと言われました。でもまだ2歳ということもあり、預ける先がなかったので、自分の症状が悪化しない限りは家での隔離生活をしたいと保健所の方に相談した」と当時を振り返った。
「罹患したら完全に隔離の闘病生活となってしまう。育児や介護等、もし自分がいなかったら生活が回っていかないとなる場合、この病気とどう向き合ったらいいのか」と不安を露わにした。
かかりつけ医の重要性、受診控えへの懸念
赤江が罹患した4月は、増加する問い合わせに対し保健所の業務がひっ迫して連絡が繋がらない状況が問題となっていた。赤江もなかなか連絡がつかなかったため、「まず、かかりつけ医の耳鼻科にかかり、そこから保健所に連絡をしてもらった」という経緯を語った。
迫井医政局長は赤江の経験を受けて、「個々の日常生活や病歴を知っているのは普段かかっている医者になる。そういった状況の時こそかかりつけ医から的確なアドバイスをもらえる」と、かかりつけ医を持つことの重要性を説いた。
また、自身が身を置くエンターテインメント業界も打撃を受けたと語るデーモン閣下は、「35周年ツアーを予定していたが断念したと」明かし、スタッフの雇用を生むために「1/2ずつしか観客を入れられないので、昼夜公演を開催。ビデオで撮影したミサ(コンサート)を見てもらい、我々はその後に生で出てきてトークをする」という全国ツアーを行ったと語り、「これがゲラゲラと笑いが起こって意外と評判がいい(笑)。しかし、来年はどうなるのか」と先が見えない状況への不安を滲ませた。
そして、これから年末年始を迎え、インフルエンザの流行も懸念される季節となることについて、迫井医政局長は「感染リスクが高まる“5つの場面”」を例に挙げ、人と集まる機会があっても工夫をしてほしいと促した。
<感染リスクが高まる5つの場面>
・飲酒を伴う懇親会
・大人数や長時間におよぶ飲食
・マスクなしでの会話
・狭い空間での共同生活
・居場所の切り替わり
※新型コロナウイルス感染症対策推進室(内閣官房)サイトより
また、コロナ禍において病院への受診、検診控えが増えていることが問題だと警鐘を鳴らし、「コロナの診療している病院、または病院自体に怖くて行かないという人が増えている。特に小児科、耳鼻科で大きく受診が落ち込んでいて、まだ戻り切っていない」と現状を分析。
「医療機関は感染防御をしているので、安心して医療にアクセスをしていただきたい。過度な受診控えは疾患のリスクを高め、病気の早期発見の機会も逃してしまう恐れがある」と呼びかけた。
赤江は、「先日、娘のインフルエンザワクチンを接種しに行ったら、『まだ受けていない日本脳炎のワクチンを先に受けて』と医師に言われました。自分も無意識のうちにコロナに気を取られていた」と本来受けなければいけないワクチン接種を失念して反省したというエピソードを語った。
“広島県がん検診啓発特使”も担当するデーモン閣下は、「コロナによる受診控えで、がんの早期発見を遅らせてしまう場面もある。冷静に他の病に対しても見直していかないといけない。コロナの“第3波”に向けての意識を持つことが重要」だと注意喚起をした。