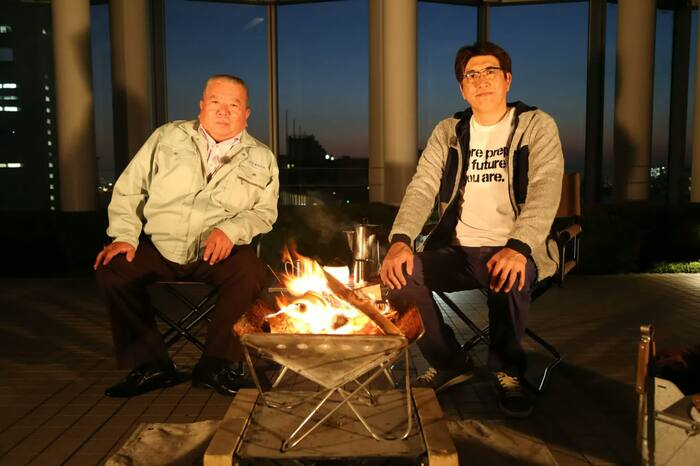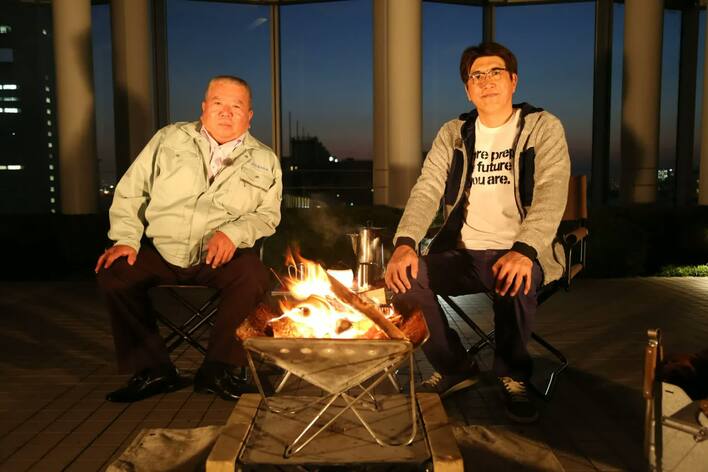石橋貴明が文化人、ミュージシャン、タレント、アスリートなどジャンルを問わず“話してみたい”ゲストを迎え、焚き火の前でじっくり語り合うフジテレビ『石橋、薪を焚べる』。
12月1日(火)の放送は、佐賀県有明海漁業協同組合の代表理事組合長・西久保敏氏が登場。販売枚数、販売額が17年連続で日本一となっている佐賀海苔について、自然相手の海苔作りの面白さ、難しさなどを語った。
豪快に佐賀弁を話す西久保氏。佐賀海苔が17年連続日本一となっているのは、「徹底した集団管理の賜物」と語る。
西久保:組合員さん、七百何十人おるばってん、集団管理が佐賀は徹底しとるけん。どっかで「病気が出ましたよ」っていうと、本所から各地に「どこどこで病気が発見されました。みなさんすぐ手入れをしましょう」と、一斉に。1日、2日で、すぐに作業ば終了するけんが。それで、病気の蔓延化を防ぐけんがですね。
石橋:それを、組合員七百何十人でやってるわけですか。そこの組合長なわけですか。
西久保:はっはははは。はい(笑)。
石橋:「病気が出たぞー!」って?
西久保:(笑)。
石橋は「組合長、迫力あるからみんなやるよね」と声を上げた。
「自分たち漁師が、夏に山に行って植樹」おいしい海苔はまず森から
その佐賀海苔のおいしさの特徴を聞くと、意外な答えが返ってきた。
西久保:自分たち漁師が、夏に山に行って植樹して。
石橋:まず、山から!?山に木を植えに行って?
西久保:はい。山に降った雨が、自然に栄養分となって有明海に流れ込んでですね。
石橋:じゃあ、春先や夏は山に。
西久保:はい。山に行って、下草刈りとか枝落としとか、漁師が手伝いに行って。
西久保氏は「山を育てる人がいなくなったけん、恵みの雨をもらうために自分たちも植樹している」と明かした。
有明海での海苔の養殖は、海に竹を立てて網を張る「支柱式」。有明海は、満潮時と干潮時で6メートルほどの干満の差が生まれるといい、海中からの恵みと、太陽からの恵みで栄養が凝縮され「細胞の詰まったおいしい海苔が採とれる」という。
一番高価な海苔は「1枚300円」。西久保氏が「刺身に巻いて食べる」というその海苔を試食した石橋は「1回噛んだだけでパーンと海苔の香りと…そして、見事に溶ける!」「これは、うまい」と、パリパリと音を立てながら試食が止まらない様子。
安いものは「1枚5円」。西久保氏は、高価な海苔とそうでない海苔は、栄養素的には大差はないが「歯切れやくちどけの柔らかさが違うけん」と説明した。
おいしい海苔を子どもたちの食育に!そして今年は医療従事者も激励
石橋:組合長は、このおいしい海苔を、地元の幼稚園児のみんなに。
西久保:はい。毎年、1回摘みのおいしい海苔ば選別してですね、地元の幼稚園生に配って食べてもらいよるです。やっぱり小さか子どものときに、「海苔の本当の味はこれですよ」というのを植え付けとけば、その幼稚園生が大人になったときに「あのとき食べた海苔、おいしかったよね」と思ってもらえるように頑張ってですね、毎年配りよるです。
石橋:感性がいいときにそういう味覚を植え付けるのは、絶対必要ですよね。
今年は新型コロナウイルスの影響で、3割ほど消費が落ちた。「コロナが収束してくれないと自分たちも困る」と、激励の気持ちも込めて、医療従事者にも海苔を配ったそうだ。
地球温暖化が海苔の成長に影響…有明海のバランスが崩れている!?
また、地球温暖化が海苔の収穫量に影響してきているという。
石橋:今、海苔がそんなにとれないと?
西久保:地球温暖化でですね、水温が下がるのが毎年毎年、後ろの方に来ていて。水温が22度台まで下がらんと、かき殻の中から海苔の胞子が出ても、網への付着率がめちゃくちゃ悪かですもんね。10年、15年前までは10月1日には種付け、採苗しとったですもん。それがだんだん地球温暖化で遅れて、昨年は10月28日くらいに種付けばするくらい、水温が下がらんとですよ。
海を浄化する貝類も年々減っている。有明海再生を目指し、あさりの稚貝など二枚貝が定着するように努力をしているが、うまくいっていない。「有明海の海のシステムの、何かどこかでバランスがずれている」と考え、専門家に調査も依頼しているが、現状は「何が原因かわからない」と嘆く。
石橋:ひょっとしたら、今年もまた不作になっちゃう可能性もあるんですか?
西久保:今年はたまたま水温が早よ冷えるけんちゅうて、10月18日、去年より10日間くらい採苗ば早うしたけれど、有明海の栄養不足の関係で、成長が2日3日遅れとるですよね。
石橋:何が原因なんですか?
西久保:「梅雨どきの雨量が1000ミリを超せば、今年の有明海の海苔は豊作ですよ」っちゅうデータを試験所が出すですよね。今年は、7月の豪雨でめちゃくちゃ雨も降ったけど、有明海全域、佐賀、福岡、熊本まで栄養分が落ちたけん。
石橋:その原因はわからないんですか。
西久保:わからない。試験所に聞いても「原因がわかりません」っちゅう見解ですよね、今のところでは。
ところが数日後には「急展開して平常通り戻った」と話し、石橋は「日々チェックしておかないと、水温が下がったからOKということではないんですね」と、自然相手の海苔作りの厳しさを知った。
海苔漁師の信念…自然との闘いは「難しい部分であって、面白い部分」
「親父が海苔漁師だった」ことをきっかけに、海苔漁師の道に進んだ西久保氏。仕事をしていてうれしいのは「海苔が自分の思った通りに育って、審査で良い等級がついたとき」と話す。
西久保:自分たちには大体の信念があるけん、「こういうふうにしてとっていこう」と考えるばってん、自然相手ですから、毎日同じ気候が続くかっていうと、続かないけん。
石橋:自然との闘いもあって。
西久保:はい。そこが難しい部分でもあって、面白い部分ですよね。
と、海苔漁師の魅力を語った。
「後継者不足の歯止めを」そして「おいしさを追求」
石橋は、17年間日本一の海苔を作り続ける西久保氏の今後の目標にも迫った。
西久保:やっぱし、生産者もまだまだ、年間に10人ずつくらい減っていきよるんですよね。
石橋:やっぱり、ちょっと減ってるんですか。
西久保:後継者不足でですね。そこら辺の歯止めと、この海苔業界で最後まで生きていくには、誰が食べても「佐賀の海苔はおいしいぞ」というところ(が必要)。おいしさを突き止めんでいけば、海苔の生産だけを考えれば1.5倍くらい伸びしろはあるとですよ。ばってん、いくら量をとっても生産者が食べてまずい海苔をいくら作ってもですね。
石橋:ダメなんですね。
西久保:今後、生き延びていかれんと思うけん。
石橋:毎年、1枚300円くらいの値段がつくようなものを作っていくと。
西久保:はい、そうですね。本当の海苔の、おいしい海苔の本当においしい味を消費者のみなさんにわかってもらうようにと思っております。
石橋から「組合長の人柄の良さが、佐賀県の海苔に出てますよね」と言われ、西久保氏はニッコリ。「とにかく、おいしい海苔にこだわって作っていく」と誓った。