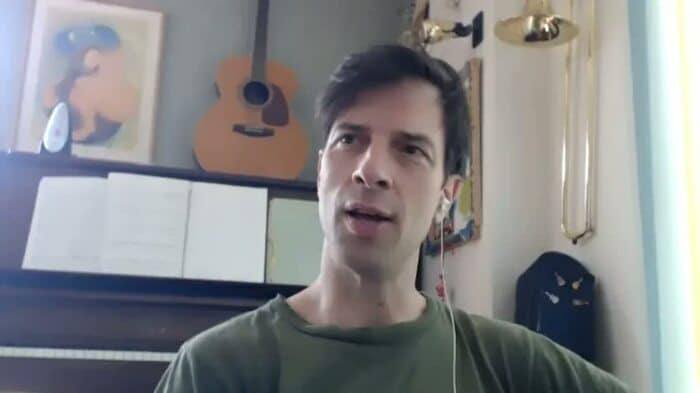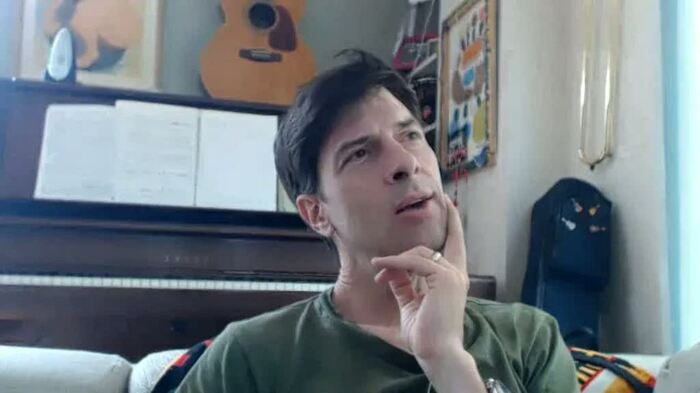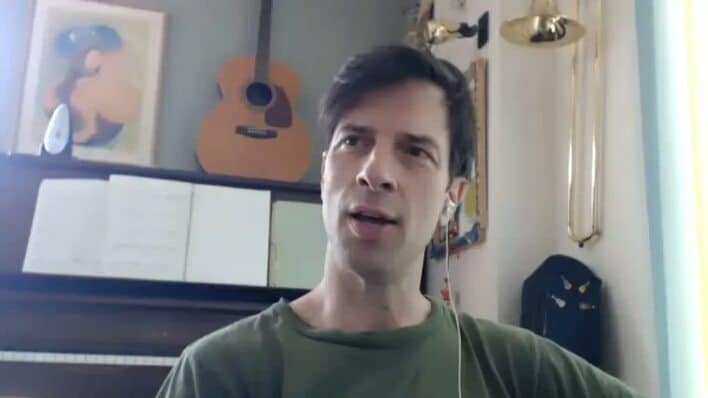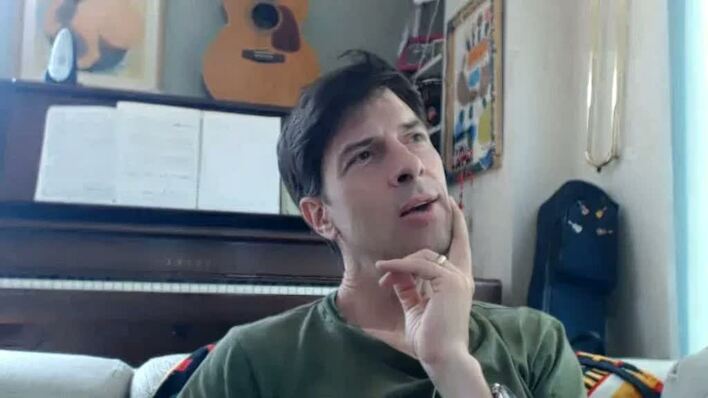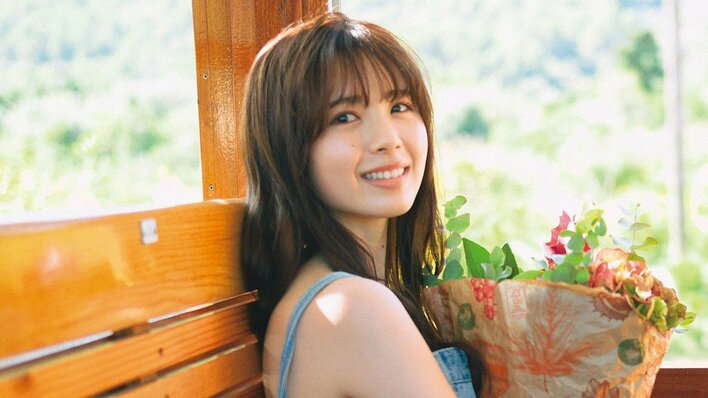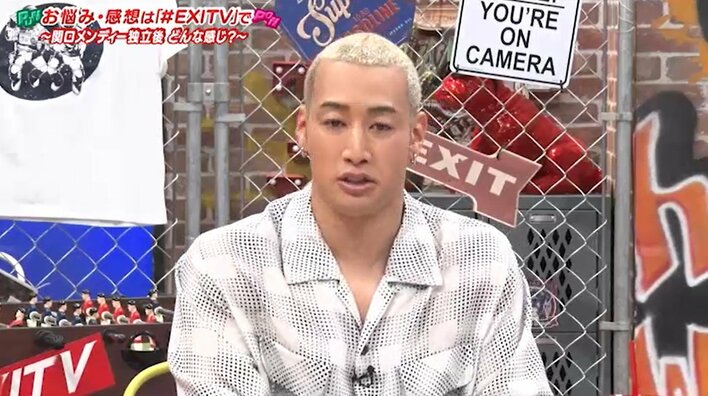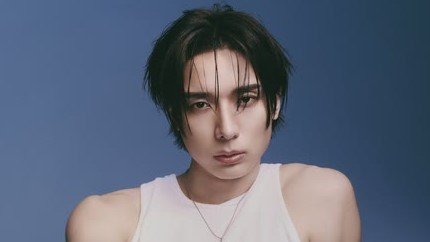幼少時代は国から食料支援を受けるような貧困家庭に育った、お笑い芸人のパックン。
日本の子どもの貧困の現状を取材しつつ、自らの生い立ちを振り返った著書『逆境力』(SB新書)を出版した。フジテレビュー!!では、1年以上にわたってパックンの取材に同行。その内容を連載でお届けする。
前回は、当時の暮らしぶりや、周囲に対していつも感じていた「恨めしい気持ち」について話を聞いた。パックンはどうやってそれを乗り越えてきたのだろうか。
>>>【vol.1】両親の離婚がきっかけで貧乏になった。
新聞配達をがんばった勲章
何不自由なく育った人と比べると、僕は「自分でお金を稼ぐ」ということをずいぶん早く始めたのではないかと思います。
新聞配達のアルバイトは10歳くらいから始め、高校卒業まで続けました。同級生たちが、スキー合宿に行っている間も、お泊まり会やホームパーティで遊び疲れて朝寝坊している週末にも、雨の日も雪の日も、1日も欠かさず。
朝5時くらいに起き、営業所から届けられた新聞に広告を折り込んで輪ゴムでパチンと止める(雨の日には、さらにビニール袋に入れる)。それを自転車に積み込み、1時間ほどで配り終えてから学校に行っていました。
ちなみに自転車は、母がクリスマスプレゼントとして買ってくれたもの。それでもいい自転車でしたが、正直少しダサかった。当時はE.T.にも登場したスポーツタイプのBMXの自転車がブームとなっていて、近所の先輩が自ら組み立てた、超かっこいいやつにものすごく憧れていました。
僕は2年かけて新聞配達で一所懸命貯め込んだ貯金でその憧れの自転車を先輩から買いました。値段は250ドル。大学に入るまで毎日乗ったし、今も東京の家に飾ってある自慢の「仲間」です。
さて、自転車で新聞配達を終え、学校に着くのは6時半くらい。授業が始まるのは7時過ぎだったので、それまで30〜40分、廊下で仮眠をとっていました。さすがにマットレスやブランケットは難しかったけど、枕だけはロッカーに入れてありました。
当時、僕の太ももの筋肉は競輪選手並みに発達していました。今も太いほうだと思いますが、これは間違いなく自転車で新聞配達をしていた名残りです。何しろ住宅街とはいえコロラド州の起伏の激しい道を毎朝、走り回っていたのだから。
上腕の筋肉も、新聞配達のアルバイトの名残り。アメリカの新聞配達人は、丁寧にポストに入れたりしません。「戻ってこないブーメラン」の要領で、自転車から各家のドアに向かって新聞を放り投げるから、自然に上腕の筋肉がつくのです。
そんなわけで、太ももと上腕の筋肉は、かつて新聞配達をがんばった証であり勲章でもある。僕は勝手に「がんばり筋」「努力筋」と呼んでいます。
最初は新聞配達だけでしたが、13〜14歳になると選択肢が広がり、ほかにもいろいろなアルバイトをしました。
それでも僕にとって「仕事」といえば、やっぱり何と言っても毎日続けていた新聞配達。これは、いわば僕、「パトリック・ハーラン」という人間の基礎となっている部分なのです。
もちろん、すごく大変だった。でも「自分でがんばってお金を稼いでいる」「お母さんの助けになっている」という達成感や充実感もありました。
これは、子どもが本来、味わう必要のない苦労だとは思います。でも置かれた境遇でベストを尽くすという意味では、今の僕につながる貴重な体験だったことは間違いありません。
とにかく人とは違う分野で勝負する
貧乏でなくても成功している友人はいるので、「貧乏だったからこそ、今くらい豊かになれた」と言い切ることはできません。ただ、もし貧乏な幼少期を送っていなかったら今の僕はいない、それはたしかです。
幼いころの僕にとって一番重要だったのは、お母さんを困らせないこと、お母さんを喜ばせること。その気持ちがなかったら、バイトに勉強に部活にと、あれほど一生懸命に取り組むことはできなかったに違いありません。
それに加えて、誰にも負けたくないという競争心。英語に「chip on your shoulder」という言葉があります。バカにしているのかと、すぐイラッとする「ケンカっぱやい」といった意味なのですが、十代のころの僕は、まさにそんな感じでした。
とにかくどんな分野でもいいから、勝ちたいという気持ちが強かった。アメリカンフットボール部を諦める代わりにバレーボールや飛び込み競技、体操などのマイナースポーツを選んだのもそう、「何でもできるオールラウンダー」になろうとしたのもそうです。
ぶっちゃけ、僕は勉強がよくできました。でも、それだけではなく、合唱団ではソロパートを振られ、演劇では主役を任される。加えて、歌や演劇ができるうえにスポーツもうまい。
すべて一番ではないけれど、スポーツが得意な人がいたら「成績表を見せてみろよ」、歌や演劇が得意な人がいたら「僕くらい速く走れるか?」、自分より勉強ができる人がいたら「歌はどうだ、演技はどうだ」と違うカードを切る意識をもっていました。
まとめていえば、「ほら、お金がなくても負けないぞ」と睨みを利かせていたchip on your shoulderな少年だったのです。決して虚勢ではなく、そんな強い精神力と実力が養われたのは、間違いなく貧乏だったからこそ。財産だと思っています。
ただ、僕の優越感のせいで人を傷つけてしまったこともあります。
高校の演劇部では振付師も担当していました。自分は何でもできる気でいたから、ダンス経験者もいるなかで「はいはい、僕がやる!」と申し出たのです。そして振付の覚えが悪い人をからかって、みんなの笑い者にしてしまった。その人は、みんなが帰ったあとでひっそり泣いていたそうです。
「パトリック、あなたは自分で思っている以上に、みんなの憧れの存在になっているの。あなたは楽しんでいるだけかもしれないけど、あなたの言葉には重みがあって、からかわれたりすると傷つく人がいるのよ」
忘れもしない、演劇部のウィザースプーン先生にこう諭されて以来、優越感をひけらかすのはやめました。周りの人にもっと感謝し、優しくしようと方向転換したのです。17歳くらいのころのことでした。
貧乏の反動で人を傷つけ、その反省から、周りに感謝すること、優しくすることの重要性を学ぶことができた。「怪我の功名」というのもおかしいけれど、これも貧乏の財産といえるのかもしれません。
【次のページ】「死ね」「バカ」と暴言を吐く子どもも居場所があれば変われる。