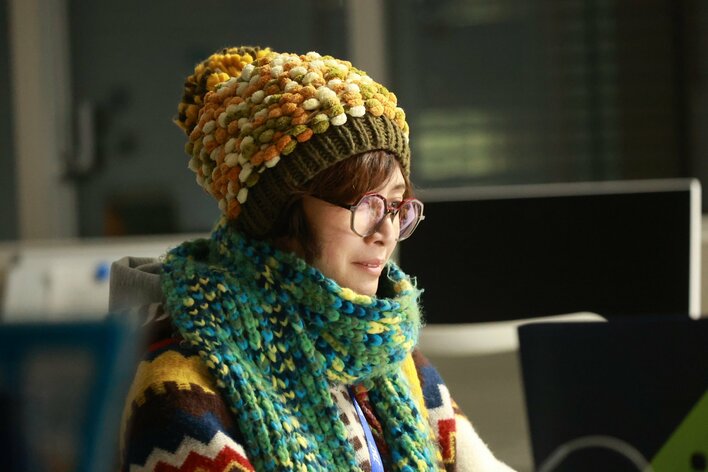真矢ミキ主演の大人気シリーズ、オトナの土ドラ『さくらの親子丼』が、10月17日よりスタートした。
『さくらの親子丼』関連記事はこちら!
2017年10月にシリーズ第1弾、2018年12月に第2弾が放送され、第3弾も前作に続き民間の子どもシェルターを舞台に、真矢ミキ演じる九十九(つくも)さくらが温かい料理を通じて傷ついた子どもたちと心を通わせていく。
真矢にとって連続ドラマ主演作がシリーズ化するのは、本作が初めてのこと。そんな真矢に、『さくらの親子丼』についての思いを聞いた。
<真矢ミキ インタビュー>
――撮影も快調に進み、「さくら」として生きる忙しい日々が続いていますね。
さくらを演じるほど、自分と一体化してくる気がします。私自身もどこまでがさくらで、どこまでが自分かわからなくなってきたと思うことが多いですし、この役は、撮影現場でさくらを演じているだけでは、視聴者のみなさんに何か見えてしまうものがあると思います。
『さくらの親子丼』は、どこか私を正してくれますし、定期的に“人生のバイブル”のように台本がやってくる(笑)。さくらのように本職以外で、何かの役に立てないかと思うことも多くなりました。
さくらに関してはどんな映り方をしていても、どう見られてもいいと思っています。逆に言うと、自分を知ることができる時間のような気もしています。
それはいいことばかりではなく、「年を重ねた顔つきになってきた、私って今こんな感じなんだ…」と思うことも(笑)。カメラの中のさくらは、生身の自分のような感じがします。
――シリーズ化にあたり、どのようなところが視聴者に共感、支持されていると感じますか?
時代と合致していることだと思います。平成から令和、コロナ禍でさらに虐待や育児放棄などのニュースを拝見するたびに、またさくらに出会えることの必然性を感じています。シリーズを通して、さくらも私もお互いに成長させていただいていますし、それが色濃く見える作品です。
――前作と違うと感じたところはありますか?
今まで以上に描かれている世界が広がっていて。さくらは法廷にも行き、社会が直面している児童虐待の実状をより深く知り、今までのように正義感だけでは走れない。今回のさくらは、とても迷っているように感じます。
時代も変わり、子どもたちとの普通の会話がより難しくなってきて、もしかしたらさくらは、今の時代とは逆行したウザさがあるのかもしれません。
でも「それでも言わせて、守らせて」と、愛のあるしつこさみたいなものを、痛い思いをしながら演じています。
――真矢さんにとって、さくらはどういう存在ですか?
愛着がありますし、さくらのように見過ごせないところも似ていると思います。さくらに出会ったことにより、直線的な正義ややさしさだけが全てではなく、いろんなやさしさがあっていいことも学んでいます。
正義感も出し方によっては、その人の人生を大きく変える出来事も起きてしまう。“善人”とは、とてもいい言葉だと思って生きてきましたが、単純にとらえてはいけない、とてもセンシティブな言葉だと思いました。
――子どもたちに伝えたいことは何ですか?
シェルターのようにかくまってくれるところ、自分たちを守ってくれる場所があるということを情報として目から耳から入れていただきたいです。
視聴者の中にはお子様もいらして、前作の時には「さくらさんでしょ?」と声をかけていただいたり、若い方からお手紙をいただいたりということがありました。
このドラマは大人の方が見ていると思っていたので驚きましたが、お子様にお声がけしていただくような機会を持つと、何かしらの影響はあるのかと感じます。能動的になりたいと思います。
――視聴者のみなさんにメッセージをお願いします。
厳しい状況の中ですが、コロナ禍で虐待のニュースを私たちは日常的に目にし、耳にし、さらに増加している気がしていて、この物語は決して遠い話ではないと思っています。
説教がましくはなりたくないですが、できる範囲のことでいいので、みなさんが思う目線で子どもたちを応援し、私たち大人も子どもたちと変わらずぶつかりながら生きているというところを見ていただききたいと思います。