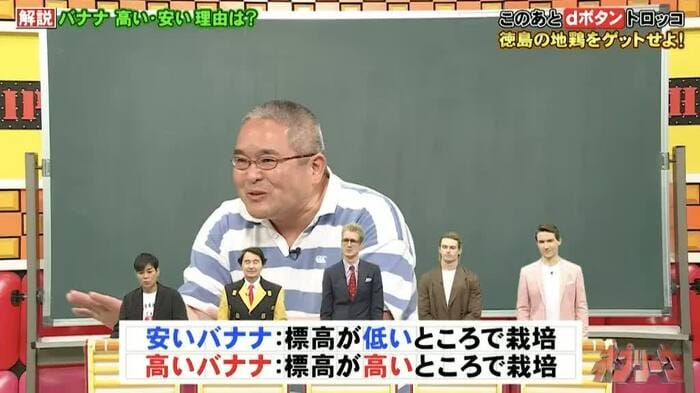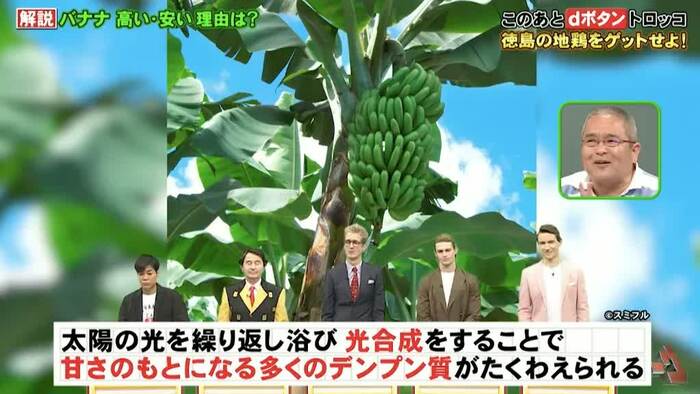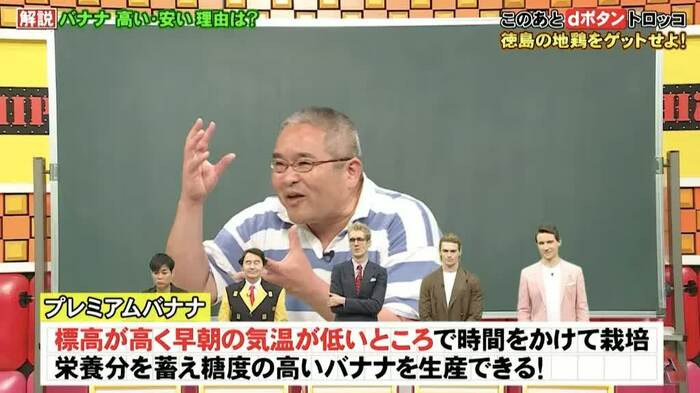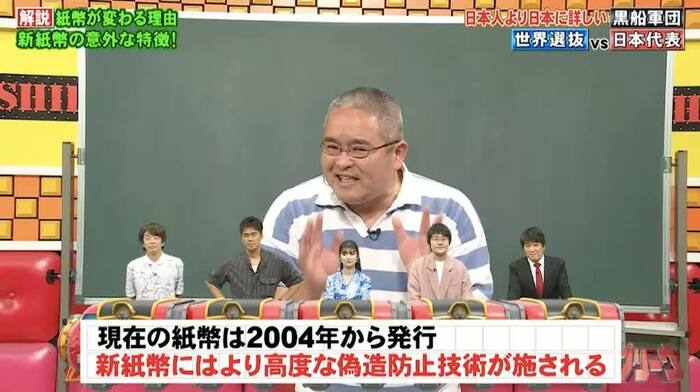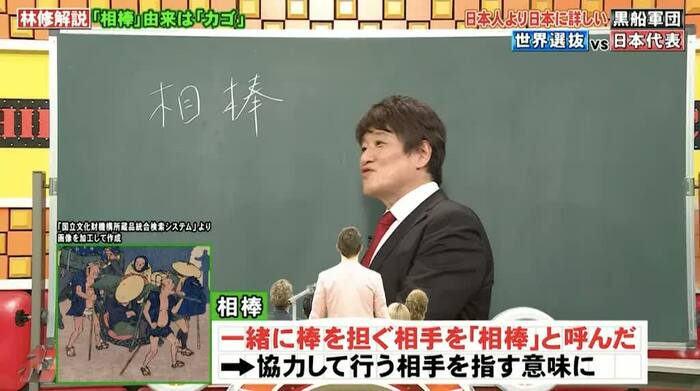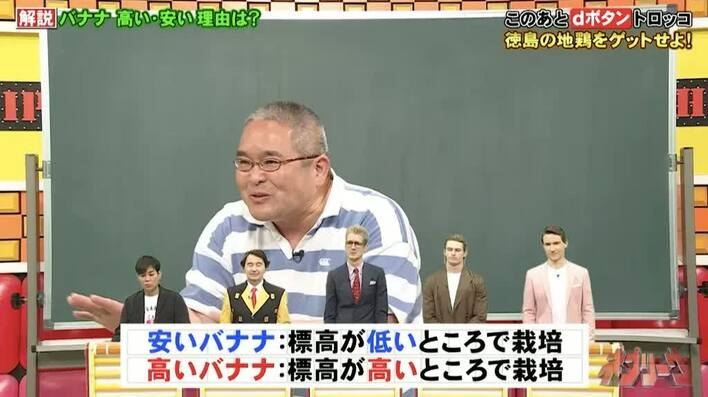5月29日放送の『ネプリーグ』に登場した、“ウンチク”や“豆知識”をおさらいします。
品目ごとの日本が輸入している国の1位を当てる問題では、問題に登場した「バナナ」の値段について、地理担当の村瀬哲史先生が解説を加えてくれました。
日本がバナナを一番多く輸入している国はフィリピンですが、安価なバナナとちょっと高級なバナナは何が違うのでしょうか?
村瀬先生によると、安価なバナナは標高が低い場所で、高級なバナナは標高が高いところで栽培されているそうです。
バナナは太陽の光を繰り返し浴びて光合成をすることで、甘さのもとになるデンプン質が多く蓄えられるのですが、標高の高い場所は気温が低いためバナナの成長が遅く、その分、太陽が当たる時間が長くなります。
標高の高い場所のバナナは時間をかけて育てられるので、甘くてもっちりとした味になり、その分、高い値段で取り引きされているのだそうです。
2024年から新しくなる紙幣の変更点は?
2024年から流通する予定の北里柴三郎さんの肖像が描かれた新紙幣について答える問題では、村瀬先生が紙幣のデザインが変わる理由について教えてくれました。
紙幣のデザインが変更される目的は、偽造防止。日本ではだいたい20年ごとに紙幣のデザインが変更されていて、現在使われている紙幣が発行されたのは2004年。新紙幣には、それよりも高度な偽造防止技術が施されています。
ちなみに北里柴三郎さんの肖像が使われるのは新1000円札ですが、新紙幣で変更になるのは肖像部分だけではありません。
新紙幣には誰もが使いやすいように「ユニバーサルデザイン」が導入され、金額の表示がすべて算用数字に。文字の大きさも大きくすることで、外国から来た人にも使いやすい工夫をしているのだそうです。
「アーモンド」を漢字で書くと?
漢字を書く問題では、「アーモンド」という漢字について、林修先生が解説してくれました。
「アーモンド」を漢字で書くと「扁桃」。一般に「扁桃腺(へんとうせん)」と呼ばれている「口蓋扁桃(こうがいへんとう)」の部分がアーモンドの形に似ているので、アーモンドを表す「扁桃」が体の名前に使われるようになりました。
ただし、「口蓋扁桃」は正式には「扁桃腺」とは呼ばないのだとか。「腺」というのは、分泌機能を有する細胞の集合体を表す言葉なので、ただ「扁桃」と呼ぶのが正式なのだそうです。
「相棒」という漢字の語源は?
最近ではすっかりテレビ番組の名前として浸透している「相棒」という言葉がいつ生まれたのかも、林先生は教えてくれました。
「相棒」という言葉が生まれたのは、江戸時代。カゴやモッコなどを棒に吊るして運ぶときに、棒を一緒に担ぐ相手を「相棒」と呼ぶようになり、仕事などを協力して行う相手を指す意味になったそうです。
5月29日放送の『ネプリーグ』は、フローラン・ダバディさんら「世界選抜チーム」と、QuizKnockの鶴崎修功さんら「日本代表チーム」が、絶対に負けられない戦いに挑みました。