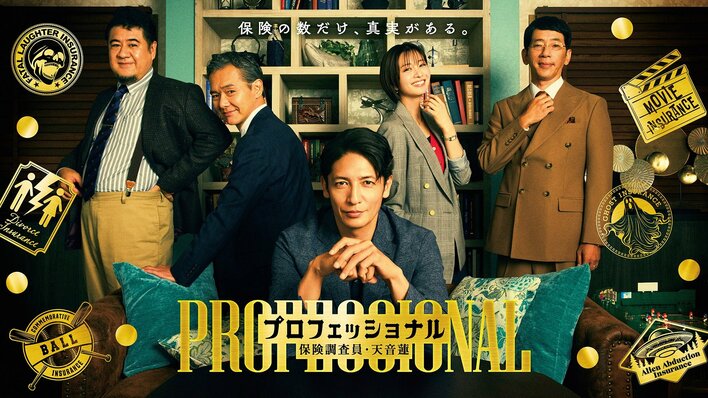木村拓哉主演のフジテレビ開局60周年記念特別企画『教場』が、2020年1月4日(土)、5日(日)21時から二夜連続放送となる。
本作はミステリー作家・長岡弘樹のベストセラー小説の実写化で、木村は冷厳な警察学校の教官の役を務める。先日解禁された木村演じる“風間公親”のビジュアルは、原作を再現した“白髪教官”の風貌で大きな話題となった。
「希望や夢、そして人間だから持ち得る恐怖など、さまざまな感情が入り混ざった作品」と評する木村は、「リアルと作品との“誤差”」を意識しながらいかにノンフィクションのように作り上げるか、という部分にエネルギーを注いだという。
30名にも及ぶ共演者たちと高い熱量で挑んだ本作品の撮影エピソードを聞いた。
<木村拓哉インタビュー>
――警察学校の“リアル”を感じるうえで、具体的にしたことはありますか?
撮影前に、プロデューサーや監督と実際の警察学校にうかがいました。リアルな空気を感じて来たからこそ生み出せるものが今回の作品にはあるように思います。
――実際の警察学校と作品の違いはどのようなところでしょう?
実際の警察学校は、いかに入校した全員を卒業させて現場へ送り出すか、ということに力を入れているそうです。一方、この作品で学校は“ふるいにかける場”であり、正反対とまではいかないですが、120度くらい違うものになっているなと感じました。
何をやっても“モラハラ”や“パワハラ”と言われてしまうこの時代に、『教場』の“強い世界観”を映像化するということは、“筋力”のいることで。そんな中でも、「この作品を作るんだ」という意気込みが僕の中にはありました。
それは、他のキャストもですし、監督をはじめとしたスタッフも感じていたのではないでしょうか。だからかもしれませんが、「リアルと作品の“誤差”」はすごく楽しかったです。…楽しいって、僕だけが感じていただけかもしれないけど(笑)。
カメラの前に立っている出演者一人一人がそこをうまく理解して、いかにノンフィクションのようにパフォーマンスできるか。その意識をみんなが持って真剣に取り組んでいたので、楽しく感じたのかもしれないですね。
“風間”の魅力は「絶対に逃げないところ」
――実際に役を演じられて“風間”をどのような男だと捉えていますか?
もともと刑事だったので、彼なりの正義感があるのでしょう。でも、現場で若い警察官の死を目の当たりにして、ずっと心のどこかに何かが引っかかっていて。その思いが拭い切れないから現場を退き、(警察学校で)世に出る前の生徒たちを強くすることに身を投じた人だと思います。
非常にストレスに満たされている人でもあると思うし、彼の“幸せ”ってどこにあるのだろうと原作を読んでいる時からずっと探していましたね。「あ、この瞬間かもな」と感じることもあったので救われましたが…根本的に自分の幸せのために生きている人ではなくて、すごく重いものを背負った男なのだと感じています。
――木村さんご自身、“風間”に惹かれる部分はありますか?
人としてすごく魅力を感じる部分と共感できる部分は、絶対に逃げないところです。もちろん彼は、逃げられない立場にいるわけですけどね。
“特別な絆”が生まれた一体感のある撮影現場
――非常に厳しい世界が描かれていると思いますが、撮影はどのような雰囲気でしたか?
現場自体は、すごく生き生きしていたと思います。チームで集まって演じていても、一対一で演じていても、高い熱量を感じられて良い現場でした。
――生徒役の皆さんとのエピソードを教えてください。
撮影が本格的に始まる前に、三浦翔平が「主要メンバーでパーソナルな時間を作りませんか?」と提案してくれました。その際にキャストみんなが思っていることや感じていることを言ってくれて。僕からは「カメラの前に立つ状態が10だとしたら、みんなは今いくつ?」って一人一人に聞いてみたんです。
そうしたら、普段は「2」とか、それほど高くないという声が多かったので、普段の生活から「5」になるように意識しようと話をして。その時、急に大きな声で「はいっ!」って全員にスイッチが入ったことが印象的でした。
撮影に入ってからは、自分自身もっと“風間”という役に入るべきだなと感じていたので、“風間”に非常に近い状態で現場にいるようにしました。自分がそうすることで、みんなのアンテナが立ってきて…これは少しかわいそうだったんだけど、待ち時間に背もたれを使う人が誰一人いなくなって(笑)。それくらい緊張感のある現場でした。
また、撮影が終わったあと、「みんな帰っていいよ」と言ってもすぐに「お疲れさまでした」って帰る人はいなかったんですよね。「(お芝居の練習に)付き合っていただけますか」と、みんなが現場に残っていて。男女問わず全員が納得いくまで、ひたすら練習をしていました。
警察学校としてやっているけど、「ああ、学園モノなんだな」と思ったのが、そういう思いは派生していくんですよ。学生役を演じているキャストの間に、できない人を鼓舞するシチュエーションが増えてきて。相手を思うことのできる大人同士だからこそ、建設的な場になったのだと思います。
――「ここまでやるか」と感じたようなエピソードはありますか?
全員のシーンで、たった一人が失敗しただけで何度もやり直すこともありました。現場では、自分以外の全ての人(の芝居)を感じられる一体感が生まれていたと思います。本作をきっかけに「あいつとは(これからも)連絡を取り合います」という人生を通した“特別な絆”が、最終的にキャストの間で生まれたのではないでしょうか。