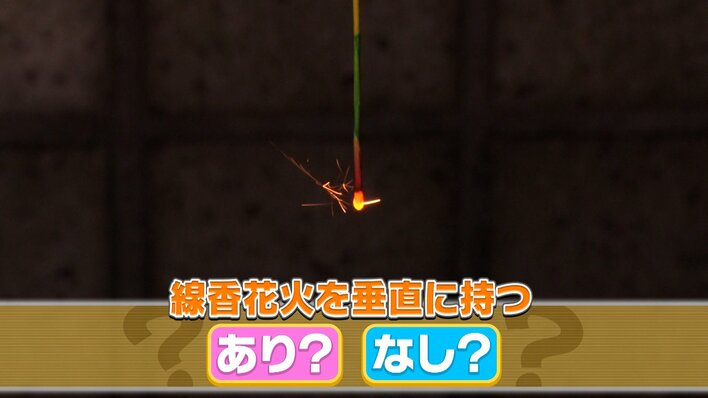親の最期の時にカメラを回すのはどんな気持ちなのか、ドキュメンタリー映像作家の信友直子さんに聞きました。
2018年、信友直子さんが、広島県呉市で暮らす認知症の母(80代)と、老々介護をする父(90代)の姿を記録した映画「ぼけますから、よろしくお願いします。」が公開。
コロナ禍にも関わらず、ドキュメンタリーとしては異例の20万人を動員しました。その後の両親の絆と、母の看取りまでを映した続編映画「ぼけますから、よろしくお願いします。~おかえり お母さん~」が、現在公開中です。
そして、映像に映らなかった娘の胸中を綴った1冊目の書籍(2019年)に続き、新作映画の公開に合わせて、新刊「ぼけますから、よろしくお願いします。おかえりお母さん」(新潮社)が発売。
監督で著者の信友さんに、映画の製作秘話や書籍に込めた思い、そして、ユーモラスな母から受け継いだ「前向きに生きるコツ」と「幸せの感じ方」について聞きました。
両親の老老介護を綴った信友直子監督「このプロジェクトは両親からのプレゼント」
<信友直子 インタビュー>
――1作目の映画では、妻が認知症になっても変わらぬ愛を注ぐお父さんの姿が深い感動を呼びました。映画の公開後、お父さんはすっかり人気者になられたとか。
「100歳を超えてこんなに、みんなに『お父さん、お父さん』言われるようになるとはのぉ。もう信じられん」とか言って(笑)、喜んでいます。おかげさまで人気者になって、父がちょっと浮かれているのは、娘の私にとっても嬉しいことです。
母が元気なときは、母が父の世話を何くれとなく焼いていたのですが、今は、私が父の好きな料理をつくって、「おいしい」と言われたら嬉しかったり、父に「コーヒー淹れたよ」と呼ばれたら、母の代わりに私が行って一緒に飲んだり。なんとなく、かつての母のポジションに、私がきたような感じになっています。
――大好きな娘さんとそんなふうに過ごせるのは、お父さんにとって本当に幸せなことなのでしょうね。
まぁでも、恋女房には勝てないと思いますけど(笑)。
――1作目の映画では、娘としてはカメラを回し続けることを躊躇するようなシーンが、撮影者としては望んでいた映像だった、という経験をしたと書かれていました。今回の映画でも、娘であり撮影者であることを、自覚したシーンはありましたか。
病院で母を看取ったときの、父と母の別れのシーンは、私も泣きながら撮りましたし、何か神々しい感じすらして、ホントに鳥肌が立ちました。
母が危篤状態になってからの2週間、父は最初こそ、「わしは別れの挨拶なんかせんぞ」と言って、いつものように、「おっ母、早う帰ってこいよ。またコーヒー淹れちゃるけん」と励ましていました。でも、いよいよ最期という夜、父は母の手を握り、「あんたが女房でよかった。ありがとうね」と絞り出すように言ったんです。
それは、ヨボヨボの年寄り二人のお別れなのに神々しい、粛然とした気持ちになるようなシーンだったので、すごい場面に立ち会ったなぁという気がしました。
――家族として立ち会った最期というものも、カメラを通して見ると、また違うものなのでしょうか。
そうですね。これは父に確認していないからわからないですけど、たぶん父も、カメラがいたから、「あんたが女房でよかった」というセリフを言ったというのは、なくはないと思います。私が家族としてだけその場にいたら、あのセリフを言ったかどうかはちょっとわからない。
それは、私に対するサービスということでなくても、撮られているからこその高揚感みたいなのもあると思うので。
そして私も、カメラを持っていなかったら、たぶん、母が逝ってしまうということにすごく気持ちがいって、もっと母に寄って、「お母さん逝かないで!」というふうになっていたかもしれない。
けれど、カメラを持っていたことで、ある種、観察者になれたんですよね。だからこそ、父と母のお別れを、粛然とする気持ちで見ることができたというのはあったと思います。
“人生、楽しまんと損”母のメンタリティが私の中に生きている
――信友さんは以前、もしご自分が認知症になったら、「自撮りで撮影する」とおっしゃっていましたね。
はい、それは思っています。母はアルツハイマーになりましたが、母方の祖母もアルツハイマーだったので。遺伝するのかどうかはわかりませんけど、そういうこともなくはないなと。
だとすると、私も認知症になったら怖いなと思っていたんですけど、あるときふと、もしそうなったら、「私、自分で自分を撮ればいいんだわ!」って気が付いたんです。
それを、この映画を編集してくれている編集さんに話したら、「じゃあ、もうギリギリまで撮ってくれたら、あとは俺が編集するから任せて」と言ってくれました。
子どもが親の認知症を撮った作品は世の中にあっても、認知症の人が、認知症の自分を自撮りした作品というのはいまだかつてないので、これは初めてだなと思うと、ちょっとワクワクしてきて(笑)。もしそうなったら、ホントに作ろうと思っています。
――その前向きなメンタリティは、どう養ってこられたのですか。
母がそういう考え方をする人だったんですよ。私が45歳で乳がんになったときも、私は初めてのがん宣告に動揺して、すごくメソメソしていたんです。
でも、上京して闘病を支えてくれた母は、私の前ではまったく涙を見せず、手術でおっぱいの部分切除をするのを不安がる私に、「お母さんの垂れたボインでよかったら、いつでもあげるんじゃけどね~」なんて、冗談ばっかり言っていて。
抗がん剤の副作用で髪が抜け始めたときも、「コントによう出てくる、ハゲのカツラかぶっとるみたいに見えるわ」とか、あまりにもずけずけ冗談を言うから、私も一回キレたことがあって。
「そんなふうにヘラヘラばかりして、私ががんなのがショックじゃないんね!?」ってちょっとキレたら、母が、「だって、お母さんが泣くことであんたのがんが消えるんならいくらでも泣くけど、そうじゃないんなら笑わんと損じゃない」と言ったんです。
それを聞いて、ああ、そうだよなぁと思って。それは、母なりのポリシーであり人生訓で、「人生、楽しまんと損よ」というのは、日頃からよく言われていました。そう思っているからこそ、母は、日常生活のホントにどうでもいいようなことでもすごく楽しんでいたし、楽しむことの天才だったと思うんです。
たとえば2本目の映画でも、母が近くの商店街で買い物をするシーンがあります。母は、いろんな商店の人と仲良しで、何かしら話をしているんですけど、いつも笑顔なんですよね。
近所に買い物に行くって、別に面白くもなんともないことのはずなのに、商店街を歩いたり、近所の人と話をしたりするだけで笑顔なんです。だから、ホントに生活を楽しんでいたんだなと思うし、これぞ母だなと感じました。
大切な人たちをより大切に思える、気づきの1冊になれば
――落ち込んだ気分をなかなか切り替えられないときは、どうすればいいですか?
落ち込むときは、もうとことん落ち込んでいいと思うんです。そしたらいつかは底を打って、浮上するときがくるので。私も乳がんになったときは、とことん落ち込んでやろうと思い、これでもう私は、この先の人生でどんなに楽しいことがあっても、心の底から笑うことはないんだわ…と思いました。
自分はがんを患ったということが、常に頭の片隅にあって消えることはないんだろうなと思いましたからね。
でも、そんなことは全然なく、手術から半年後ぐらいには、すっかり乳がんのことを忘れていました。最初のうちは、「あ、今日一日忘れてたな」って、自分でもビックリしたんですけど、そのうちそういう状況にも慣れてくる。
だから、落ち込んだり悩んだりしたときは、悩むということを全力でやるのがいいんじゃないでしょうか。そうすると、きっとどこかで、落ち込む自分にも飽きてくるように思います。
――2冊目の御本には、信友さんが旅先のインドで列車事故に遭って大けがをし、そのあと乳がんに罹患され、お母さんの認知症と向き合っていく姿も詳細に綴られています。どんな状況も受け入れ、前進する信友さんのパワフルさの源はなんですか?
こうして事象だけを見ると不幸な感じもしますけど(笑)、やっぱり全部楽しめたんですよね。乳がんも、列車事故も、母の認知症も、おもしろいこともいっぱいあったし、そうならなければ気が付けなかった大切なこともあった。
乳がんになったからこそ気づけた母の愛や、父の愛もそうです。そう考えると、波乱万丈ありましたけれど、楽しむ気持ちや好奇心が原動力なのかなと思います。
ホントに“禍福はあざなえる縄のごとし”で、大変さの中にはいろんないいこともあるので、いいところを少しでも見たほうが、人生楽しいと思うんです。人間、幸せかどうかって、すごく主観的なもので、結局は自分が幸せだと思えるかどうか。
はたから見て、「あの人、何もかも持っていて本当に幸せそう」と思っても、本人が幸せだと思っていなければ幸せじゃないわけで。だから、幸せだと思って生きないと、それこそ損ですよね。
私もマイナスの要素はいろいろあるけれど、それでも自分がニコニコできていれば幸せで。そう思えちゃっているのは、やはり母の影響だなと感じます。
――映画同様、今回の書籍も、手に取った人が自然と、自分の親や自分自身と重ね合わせて考えさせられる場面が多そうです。
私もそうでしたけど、若い頃は仕事のキャリアをつくっていくことに必死だったり、恋愛に気持ちがいきがちだったりで、親が元気なうちは、親のことなんて気にもしないものですよね。
でも、こうして親が弱っていき、亡くなって感じたのは、「すごく大切なものは、すぐそばにあるな」ということ。
振り返ってみると、若いころに、自分のやりたいことだけに突っ走れたのは、親が自分のことをとても愛し、支えてくれていたから。だからこそ、若いころの私は、何も心配せずにいろんなことができたんだなってすごく感じました。
なので、今回の書籍も、本当に大切な人たちのことをより大切に思うような、ひとつの気づきのための本になってくれるとうれしいなと思います。
©萩庭桂太
取材・文:浜野雪江