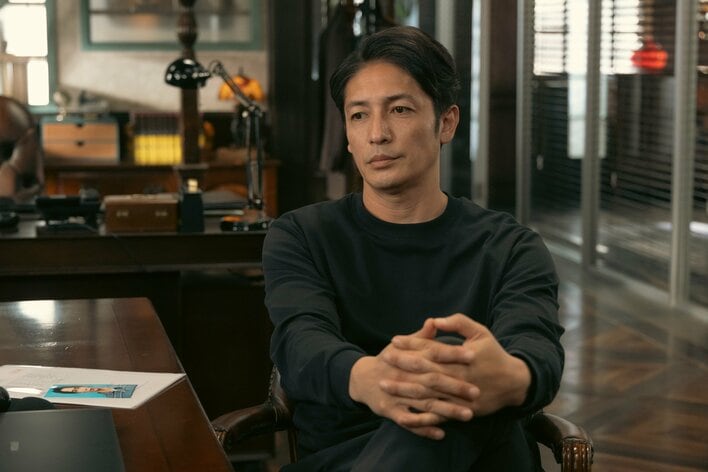「物語を追わずに、“心の弱さ”や“心の天秤”について考えながら見ていただきたい」──春本雄二郎監督が語ったこの短い言葉通り、見る者の心を揺さぶり、正しさの基準を揺るがせ、そして、「あなたならどうする?」と強烈に問いかけてくる。そんな映画が、「由宇子の天秤」だ。
9月17日(金)から公開される本作は、第4回平遥国際映画祭でクラウチングタイガー(新人監督コンペティション)部門の日本作品初となる審査員賞と観客賞をW受賞。第25回釜山国際映画祭でニューカレンツ(新人監督コンペティション)部門の最高賞・ニューカレンツアワードを受賞。また、アジア映画のアカデミー賞といわれるアジア・フィルム・アワードの最優秀新人監督賞候補にノミネートされるなど、世界各国の映画祭で絶賛されている。
初長編映画「かぞくへ」で、家族の温もりを知らない青年が、養護施設で共に育った親友と婚約者の間で、次第に追い詰められていく不器用な生き方を描き、大きな反響を呼んだ春本監督。
そんな彼の長編2作目となる「由宇子の天秤」で描いた主人公は、“常に真実を明らかにしたい”という信念を持つドキュメンタリーディレクター・木下由宇子。
由宇子を演じた瀧内公美は、「かぞくへ」を観て、本作への出演を希望したという。瀧内は、「火口のふたり」でキネマ旬報主演女優賞、ヨコハマ映画祭最優秀新人賞を受賞。最近では、ドラマ『恋はつづくよどこまでも』(TBS)『大豆田とわ子と三人の元夫』(フジテレビ)『共演NG』(テレビ東京)などに出演し、高い演技力を評価されている。
本作では、正義感の強いドキュメンタリー監督が、自身の価値観を疑わなくてはならない状況に追い込まれる複雑な心理を巧みに表現している。
超情報化社会となった現代が抱える問題やゆがみを真っ正面からあぶり出す
3年前に起きた「女子高生いじめ自殺事件」を追っている由宇子は、テレビ局の方針と対立を繰り返しながらも真相に迫りつつあった。その矢先、学習塾を経営する自身の父親(光石研)から、ある生徒との間に起きた“衝撃の事実”を聞かされる。
大切なものを守りたい。しかし、それは同時に自分の“正義”を揺るがすことになる──カメラを通して、真実を世に送り出したいという信念に突き動かされてきた由宇子は、仕事と私生活、この2つの問題の狭間で究極の選択を迫られることに。
由宇子の前に立ちはだかる問題は、父親から告白された出来事だけではない。女子高生の自殺に関して、食い違う学校側や被害者家族の言い分。自殺した女子生徒との交際を疑われ、自らの死をもって潔白を叫んだ教師。そして、加害者家族として世間からネットリンチにさらされている教師の遺された家族──。超情報化社会となった現代が抱える問題や“ゆがみ”を、真正面からあぶり出している。
本作を作るきっかけになったのは実在のネットリンチ事件
公開直前に都内で行われたシンポジウムに登壇した春本監督は、「由宇子の天秤」を作るきっかけとなったのは、「あるいじめ自殺事件で、加害者少年の父親と同姓同名の、事件とはまったく無関係の人がネットリンチを受けているニュースを見たこと」だと語った。
本作の中で、由宇子たちが自殺した教師の母親・登志子(丘みつ子)のアパートを訪れ取材するシーンは衝撃的だ。登志子は、いまだに続く誹謗中層におびえながら、窓に新聞紙を貼った真っ暗な部屋で、声をひそめ気配を消して生きている。
毎朝、2時間かけて自分の住所がネットに書かれていないか確認し、書かれていなければ初めてその日1日が始まると語る。いつでも引っ越せるように荷物は最小限。壁には、「私には娘がいる。可愛い孫がいる。だから私は幸せだ」という、現実とは相反する文言を貼り、それを呪文のように唱えて、ただただ1日が過ぎていくのを耐える。
春本監督が「今は超情報化社会で、誰もがSNSで情報を発信できる時代。まったく身に覚えのないことで、誹謗中傷されたらどうなるか。逆に、正義を振りかざす人たちには、ある種の危うさと、人間的に欠けているものがあると感じている。そこを掘り下げたいと思った」と語る通り、ヒリヒリするような画面を作ることで、そのメッセージが伝わってくるかのようだ。
マスコミの大罪とは?自分が当事者になって初めて真実を語ることの難しさを知る
その一方で、春本監督は「マスコミが発信していることが、SNSでバッシングを助長することもある」とも語っており、マスコミ報道への強烈な批判も随所に挟み込んでいる。
その最たるものが、由宇子が取材したVTRの試写を見ているテレビ局のプロデューサーが、自分たちに不利になる映像やナレーションをすべてカットし、報道部に影響が出ないような編集と、構成への練り直しを指示するシーンだ。
ほかにも、「報道が殺したんですよ」「お前、どっち側なんだよ?」「俺たちがつないだもん(映像)が“真実”なんだ」と、それぞれの立場の登場人物に語らせることで、報道のあり方を問いかける。
由宇子は「私は、誰の味方にもなれません。でも、光を当てることはできます」と、取材対象者に語る。だが、真実を報道しようと正義を振りかざしていた由宇子もまた仕事でも私生活でも“当事者”になり、結果的にいくつもの罪を犯してしまうことになるのだ。
春本監督は、本作に込めた思いを「社会の闇に光を当てることができると思っている主人公が、自分自身の闇に光を当てることになったとき、個人なのか?報道なのか?どちらを尊重するのか?そこではじめて真実を語ることの難しさを知る。情報の代表者である主人公が当事者になる。観客に当事者になることを体感してほしかった」と語る。
いくつもの選択を迫られ、右往左往する由宇子の狼狽ぶりは、リアルな人間の姿として心に迫ってくる。
貧困が招く悲劇。大人の犠牲になるのはいつも子どもたちという現実
また、現代日本の貧困、その被害者となる子どもの境遇も重要な要素として登場する。ドキュメンタリーディレクターの傍ら、夜は父親の学習塾で講師の手伝いをしている由宇子。
塾で体調を崩した女子高生の萌(めい・河合優美)を団地に送り届けるシーンでは、部屋に足を踏み入れると、息をのむ光景が飛び込んでくる。定職についていない父親と2人で住むその室内は、物やゴミであふれかえっている。娘を嘘つき呼ばわりし、反抗すると手を上げる父親。その光景を目にした由宇子は、これまでの萌の生活を想像し、言葉を失うのだった。
自身も父子家庭で育った由宇子は、自分と萌との境遇の違いを目の当たりにし、萌に対して特別な感情を持つようになる。萌も、徐々に由宇子に心を開き、2人は心の距離を縮ませていく。
だが、まだあどけなさが残る萌もまた、ある秘密を抱えていた。それは、貧困の中で生きるために彼女ができる唯一の手段なのだが、それを知った由宇子は萌を傷つける言葉をぶつけてしまう。
「なんだよ、先生もかよ…」。吐き捨てるように言う萌の表情は、唯一信じていた大人に裏切られた悲しみと怒り、絶望に満ちている。いつでも大人の犠牲になるのは子どもたちなのだ。そして由宇子は、この後、大きな間違いを犯したと突きつけられることになる──。
正しさを問い、人間の弱さを描く。見る側の心のバランスをも揺るがす圧倒的な作品
脚本執筆に6年、10回もの改稿を重ねて作られた本作は、驚くほど緻密に構成されている。真実を追う仕事、取材者との信頼関係、父親の罪、少女と共有する秘密、最後に明かされる衝撃の事実…物語の経過と共に、それらすべてが融合し、由宇子の正義や公正さはグラグラと揺らいでいく。
本作の英題は「a Balance」。まさに、由宇子は、必死にバランス(公正さ)を保とうと試みるが、その難しさを突きつけられる。
春本監督は、「真実は多面的。人は、状況によって間違った選択をしてしまうこともある。つまずいたとき、どういう社会だったら立ち上がれるのか。立ち上がるためにどういう社会にするべきか。そのためには、思考を停止しないことだと思う。学校や社会で正しいと刷り込まれていることは、本当に正しいのか?与えられた答えを、あたかも自分の言葉で語っている人が多いと感じる今だからこそ、みなさん自身の言葉で考えてほしい」と呼びかける。
ラストは、明確な答えを描かずに終わる。春本監督は、「見終わった後、この映画を言葉で言い表してほしい」と語っている。だが、いまだにピタリとくる言葉が見つからない。2回試写を見たが、同じシーンでもまったく違う感情が湧くほど、見る側の心のバランスをも揺るがす圧倒的な力があるからだ。
“正しさ”とは何なのかを問うと共に、人間の弱さを描いた本作。正義や真実は1つではない。それを教えてくれる作品ではないだろうか。
text by 出口恭子(ライター)
©2020映画工房春組 合同会社
「由宇子の天秤」は9月17日(金)渋谷ユーロスペースほか全国順次ロードショー
配給:ビターズ・エンド
最新情報は「由宇子の天秤」公式サイトまで。