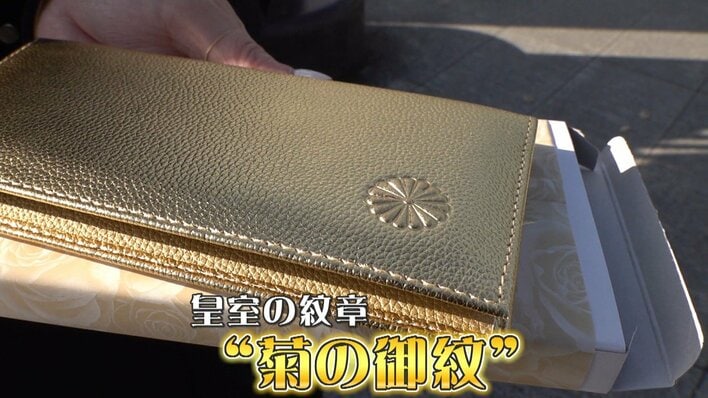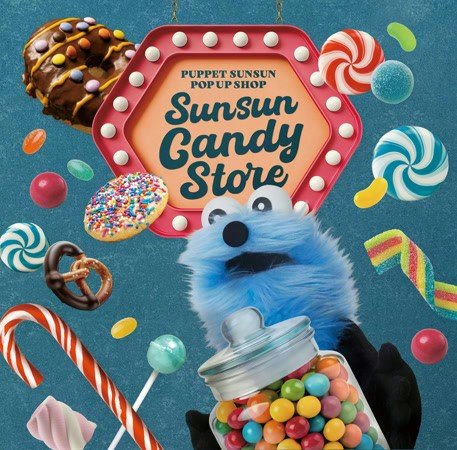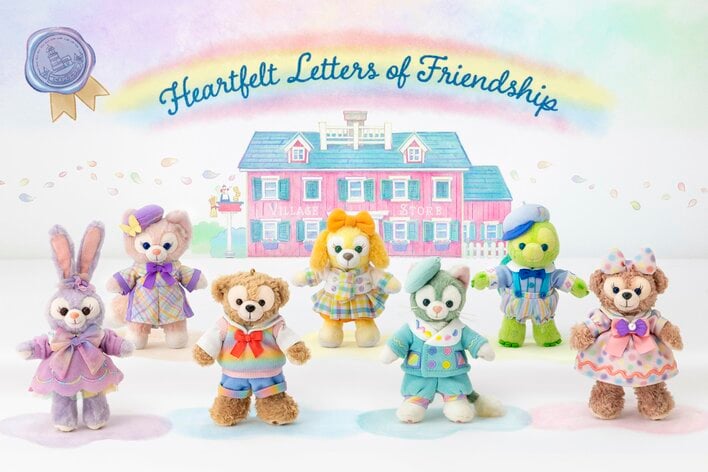第164回直木賞に、加藤シゲアキの「オルタネート」(新潮社)がノミネートされたことが明らかに。12月17日(木)、加藤がメディアの取材に応じた。
「オルタネート」は、架空の高校生限定マッチングアプリをテーマにした青春群像劇。出版記念イベントの際に、加藤本人が「アンバランスさが同居する十代の心情を、自分自身のさまざまな内面と重ねながら執筆した」と語った意欲作だ。
その作品が直木賞候補となったことで、会場には多くの報道陣が集まった。「本日は寒い中、お越しいただきありがとうございます。短い時間ではありますが、よろしくお願いいたします」という挨拶のあと、まずは写真撮影をすることに。
「笑顔で」「ガッツポーズしてください」などとカメラマンの声が飛ぶ中、「ピースしてください」というカメラマンからのリクエストに「恥ずかしい…」と、照れながら応じる場面も見られた。
撮影を終え、取材会がスタート。ここでは、取材会の模様をほぼ全文でお届けする。
まさかの知らせに「驚がくです(笑)」
──ノミネート、おめでとうございます。
ありがとうございます。
──ノミネートの話を聞いた時はどう思いましたか?
びっくりしましたね。やっぱり作家にとって憧れの賞ですので。もちろん「いつかは候補に」と思っていましたが、今作でとは思っていなかったので、本当にびっくりっていう感じです。
──ご自身で分析してみて、どの部分が今作で選ばれた要因だと思いますか?
まったくわかりません(笑)。本当にわかりません。今までの作品では違ったのかというと、いつも全力でやってきたので(そういうわけじゃないと思うし)、(今回は)本当に運が良かったと、自分では受け止めるようにしています。
──直木賞の基準は、一定のキャリアがあって、人気があるというところのようですが、そこが評価されたのでは?
そうですか?僕も小説を書いている側ですし、読むのも好きなんですけど、ずっとノミネートされている作家さんもいますし。それでもなかなか…「この方がとられないんだ」とは、いつも思うので…。その方々と並んだとは思っていませんが、ある程度の部分は認めていただけたのかなと思います。
──いつぐらいから、「いつかは賞を」と思い始めましたか?
ずっと思っていました。ずっと思っていたのは、「賞がほしい」ということではなくて…自分はジャニーズ事務所所属という立場だから、デビュー作「ピンクとグレー」から本を書かせていただいていて。普通の作家だと、新人賞をとってから作家になるのが通例なのにもかかわらず、自分はジャニーズ事務所のタレントだからという立場で本を出させてもらっているというところがあったので、そうした引け目というか、文学界にお邪魔しているという感覚があって…。
(会場の外を宣伝カーが通る)
…(映像媒体もいるため)ちょっと待ちましょうか(笑)。(静まったことを確認し)そうですね…、ちゃんと“作家”と名乗っていいのかという迷いがずっとあったので、直木賞の候補になっただけでも、本当に多少は認めていただけたのかなと思っています。
──先ほど、「びっくりした」と言っていましたが、作家風に言うと?
驚がくです(笑)。ははは!本当に、イマイチ信じられなかったというか。ピンと来なくて。
ご心配をおかけしていましたが、僕、新型コロナに罹っていまして。外出ができない期間があって。一応、1回目の陰性が出たタイミングだったので、体調としては万全だったんですけど、まだなかなか仕事の目途が立たなかったり、かけてしまった迷惑を感じる日々だったりしたので、気落ちしていた部分があって。
そこに直木賞候補の知らせがあったので、なんていうかね…フットボールアワーの後藤(輝基)さん風に言うと、「高低差ありすぎて耳キーンとする」っていう(笑)。本当にキーンとしました。「何これ!?」っていう感じでした。
──まだ、この取材会時点では、情報が公開されていないので、まだどなたにも伝えていないですか?
基本的には知らせていませんが、皆さんと同じタイミングでメンバーが知るのも、ちょっとアレかなと思って昨日、メンバー2人だけにはマネージャーを通して伝えさせていただきました。
──その返事は?
自分で言うのが恥ずかしかったので、マネージャーさんに伝えてもらったんですけど、マネージャーさんから聞くと、増田が、「僕は本を読まないので分からないですけど、すごいことなんですよね?」っていうことは言っていたみたいです(笑)。小山も「すごいな…」と。
(ここで地震が起き、少し待つことに)
(立っているため)全然感じない…。ちょっと待ちましょう。…メンバーの話はするなってことですかね(笑)。
──震えが来るくらい、うれしいのかも!
ありがとうございます(笑)。それで、小山も「すごいね」と、噛みしめるように喜んでくれたと聞いています。
──直接の報告は、この後するということですね。
照れ臭いんでね。いつもこういう祝い事があっても、いちいち言わないんですよ。基本的には。僕自身も、すごくうれしいことですけど、あくまでも候補だし、はしゃがないように、粛々と受け止めようという気持ちでいます。
──何かおねだりしますか?
どうなんですかね。きっと逆にされるんじゃないですかね(笑)。この前、小山くんは番組で21万円払っていましたから。「おごってくれ」って言われるかもしれないですね。
受賞できるかどうかは、あまり考えない「ここまで来れただけで十分」
──先ほど、引け目があるというお話をされていましたが、その中でも書き続けるパワーの源は?
初めて小説を書いた時は、「グループにとって何かできないか」という思いもありましたし、「自分自身を試してみたい」という思いもありました。でも、ここまで書き続けてこられたのは…ファンの皆さんの支えもありますし、「ピンクとグレー」を出した時に初めて書店を回って、その時に、「1作目は応援できるけど、書き続けないと応援し続けられないから、書き続けてください」と言いわれたのが印象的で。
僕自身、いっちょ噛みしたとは思われたくなかったし、本気で小説を書くという覚悟を伝えたいと思っていたので、続けることが自分を受け入れてくれた小説界への恩返しなのかなと。続けているうちに、すっかりルーティンというか、ライフワークというか、小説を書くのが当たり間の生活にいつしかなっていましたね。
──直木賞の受賞が発表される1月まで、どんな気持ちで過ごしますか?
あまり考えないようにしたいなと思っています。今までも、イチ読者として直木賞と芥川賞の選考は楽しみで、作品を読んで予想をしたりしていましたが、まさか自分が予想される側になるとは思っていなかったので、考えれば考えるほどドキドキしますし、選考委員の方々の評価が厳しいのは知っているつもりなので、ここは「煮るなり焼くなり」という覚悟ではあります。
ここまで来れただけで十分。淡々と過ごしたいと思っています(笑)。
──とはいえ、狙いたいですよね?
でも、本当に考えていないです。なんというか、あんまり考えないで、はしゃがず。もう本当に十分!
──先ほど、候補に選ばれた理由が分からないと言っていましたが、そういう説明はないんですか?
説明みたいなものは、ないです。今まで関わってくれた編集の方々から「こうなんじゃないか」という話はあるんですけど。なぜ選ばれたのかっていう理由は、僕は聞いていないんです。
──周りからはどんな話がありましたか?
自分で言うのは照れ臭いんですけど、「今までで一番いい作品だった」と編集の方々からは言っていただけました。今年偶然、コロナの影響でリモートやデジタル化が進んだタイミングだったし、マッチングアプリやSNSという題材が多少時代に合ったところもあるのかなと思います。
選考委員の方々が候補を選ぶ段階でかなり厳しい…何度か審査があったうえで、(今作が)候補になったとはうかがっていますので、認めてくださる方がいるだけで、僕は十分かなと思っています。
──今作の特徴というか、これまでの5作との違いはありますか?
今までは自分が読んで楽しい作品を、読者を自分と想定して書いてきましたが、今作は自分ではなく広く愛される作品を書いてみようと思っていました。
読んでいる間ずっと楽しい作品、とにかく楽しく小説を読んでもらいたい。今、若い方は本を読まないと思うので、「読書の楽しさが伝えられたら」ということが、実は一番意識していたことでした。
文学賞を狙う意気込みよりは、楽しい作品を書こうという意識がすごくあったので、すごくびっくりしました。
──今までの直木賞のイメージはどんなものでしたか?
芥川賞の純文学に比べると、より広く愛される娯楽小説的な部分が多い。かつ、最近の傾向としては社会的な目線が含まれているという印象があります。
本当に話題になる文学賞…(文学界の)中にいると、自分はいろんな文学賞を知っているし、どの文学賞も素晴らしいものだと思っているので、直木賞はもちろん憧れではありますが、だんだんわからなくなってくるんです。
この知らせを聞いたうちの…弊社の人間の喜び方が異常であったりとか(笑)、発売イベントよりも今日たくさんの方が集まってくださっているので、「これが直木賞の力か!」と、正直今、改めて実感させられています(笑)。
──会社の方はどんなふうに喜んでくれたんですか?
「すごいなー!」って。「すごい」としかみんな言わないです(笑)。ちょっと紛らわしかったのは、僕が(コロナからの)仕事の復帰の時に、事務所に行ったタイミングで、(スタッフが)「おめでとう」と言ってくれるんですけど…その「おめでとう」が、「復帰おめでとう」なのか、直木賞候補に選ばれたことを知っていての「おめでとう」なのか分からなくて、「何がですか?」と毎回聞いて(笑)。
数名はこの知らせを受けた方がいたので(お礼を言いました)。こんなに「おめでとう」と言われることは、正月前にないなと思って。影響力のすごい文学賞なんだなと、実感しましたね。
──小説に出てくる、ドラムを見せてくれた関ジャニ∞の丸山隆平さんは、本を読んでくれましたか?
どうなんでしょう。前回、発売イベントでそのお話をさせていただいたので、「名前出してくれてありがとう」「本読むね」とか(連絡は来た)。あと、(発売の)翌日に「5冊買った」と言っていました。
──えぇー!
あ、違う!5冊買おうと思ったら、「1人1冊までです」って言われたって。売り切れが近かったのかもしれないですけど。書店では1人1冊と言われて、「5冊買えなかったよー。だから今度買って、みんなに配るね」って言ってくれたまま話が終わっているので、この話が公になったタイミングでまた連絡しようかなと思います。お礼も言いたいなと思います。
「若い読者の方に、本の楽しさを実感していただけたら」今作への思い
──改めて、今作でSNSやマッチングアプリをテーマにしようと思った経緯を聞かせてください。
高校生に限らず、SNSはいろんな方がいろんな考え方を持って使用している物でもあると思います。
始まりのきっかけは、僕がやらせてもらっている番組で、マッチングアプリに関する是非を討論する機会がありまして。マッチングアプリで出会って結婚された方のいい話をうかがう中で、とはいえ危ないんじゃないのというネガティブな側面を話す方もいて。かなり白熱した議論を目撃して。
いろんな方がいろんな意見を持つものですし、これは何か物語が生まれるんじゃないかなと思ったのがきっかけで。
自分、30歳をすぎたくらいだったので、そろそろ高校生を書くには今が一番いいかなと。近すぎず、遠すぎず。青春群像劇とSNSのマッチングアプリというものを掛け合わせて、物語が生み出せるんじゃないかなと思ったのがきっかけです。
──読む人にどんな心の動きが生まれたらうれしいなと思いますか?
僕、書いていて思ったのは、SNSやアプリというのは、あくまでツールの一つにすぎないなということ。そこを通して、やっぱりつながっているのは人なんだと。
文面ばかり読んでいると、相手が記号であったり、人間ではないように感じる瞬間もあるんじゃないかなと思うんですが、やっぱり人と人なんだと。そこにいるのは全員、人なんだということを忘れがちですよね。
あくまでSNSは、ハサミや定規と変わらないツールなんだと。ある程度冷静に、ドライに向き合えていたほうが、より効果的に使えるんじゃないかなと僕自身は感じています。
──SNSを使い、もどかしい思いを抱えている方も多いと思います。アイドルの立場上、加藤さんにはSNSでたくさんの言葉が向けられているかと思うのですが、そういう立場だからこそ若い人たちに言えることはありますか?
僕は、小学生の頃からジャニーズ事務所で活動させてもらっていて、いろんなお言葉をいただいて、ここまでやってきたので。厳しい言葉も。やっぱり苦しいですよね、傷つきますし。でも、それをどう受け止めるか。
必要以上に、そのコメントに敏感にならなくてもいいということとか…僕自身の言葉で言うと、厳しい言葉はすごく残るので。作品のレビューを読んでも、100褒められても、1厳しい意見があると、そっちのほうが印象に残ってしまいますよね。人間というのは、そういうものかなと僕自身は思っているんです。
その厳しい言葉が“すべて”のように受け止めてしまうけど、でも、「100分の1だよね」っていうドライな目で見ることが大事かなと。そういうものをどう受け止められるかっていうのが、気にしなくて済むところかなと思ったりしますし。
本当に、あくまでツールみたいな。もっとたくさんの…厳しいコメントをする人以上に、興味のない人はたくさんいるし。それが人生のすべてにならないように、うまい距離感での向き合い方が大事だよなとは思います。
今作では、SNSの闇というところにスポットは当ててないんです、そういう理由で。個として、人と人がどう出会うか。出会いの中で人間がどう成長していくかというところがあると思いますし。直接で会うことがすべてとは思いませんが、そこで成長する部分がきっとあるんじゃないかなと思います。
今作の帯に「私は私を育てていく」っていう言葉があって。SNSに出る情報は、自分という種に対して、水であったり、肥料であったり、時には害虫かもしれませんが、あくまで外的な要素じゃないですか。育つのは自分なので。自分がどういう花を咲かせるか。それを大事にするために、SNSとどう向き合うかが大事かなと思います。
──加藤さんは、ジャニーズ事務所に所属しているということで、小説を読む人の間口を広げたかと思いますが、その意味で、自身の役割はどのように考えているか、最後にお聞かせください。
それは初めて小説を書いた時から思っているんですけど、小説界にお邪魔するということは、今まで本に触れなかった方々の触れる機会になるだろうと。その責任というものはずっと背負ってきているので、今改めて不安かというと、実はあまりないです。それは、生意気ですけど、ここまで続けてきたということで培った自信があるかなと。
作品に対しては…直木賞を受賞できるかと言われると自信はありませんが、作品に対してはすごく自信があるので。特に、この作品は、若い読者の方に本の楽しさを初めてでも実感していただけたらという思いが、強くあったので、そこを意識して書いていました。やっぱり楽しくないと読みたくない、面白くないと読みたくないと思いますので。
とにかく面白く本を読み、気づいたら、読む前とあとで少し人生が、景色が変わって見える。そんな作品になるように心がけて書きました。今日はお忙しい中ありがとうございました。