
2023年に埼玉県所沢市に誕生した「就労移行ITスクール所沢校」。
ITやクリエイティブ分野も学べる就労移行支援事業所として、障がいのある方を対象に、職業スキルと社会性の両面から「働く力」を育んでいます。
そんな中、就労支援を担うのは、支援員の中村さん。
学べるだけでなく、【IT・クリエイティブ職×障がい者雇用】を数多く叶えています。
企業様とのマッチングや、利用者の方が自信を持って就職へと踏み出せる仕組みについて話を伺いました。
IT特化型だからこその3つの強み

── 「就労移行ITスクール所沢校」は、一般的な就労移行支援と比べてどんな点が“特化型”だと言えますか?
中村:当事業所が"特化型"だと言える理由は、大きく3つあります。
1. 現場で活かせる環境が整っている
まず1つ目は、クリエイティブ職に欠かせないツールや環境が整っているという点です。たとえば、Photoshopや Premiere ProなどのAdobeソフトや、実際に職場で使われているようなプログラミング学習アプリを導入しています。「やってみたい」と思った方が、一歩踏み出し、触れてみることが出来る環境を整えています。そこから適性をみながら本格的な学習も進めていくことができます。
2. プロフェッショナルから学ぶ支援体制
2つ目は、プロの講師が在籍していることです。プログラミング・動画制作・webデザイン全ての分野で、現場経験豊富なプロが揃っています。そのため、「資格を取る」「操作を覚える」「好きなものを創る」だけでなく、実際の仕事で使えるスキルを身につける支援ができていると自負しています。実際に企業様には、スキルの高さに驚いていただくことも多々あります。
<各講師紹介>
・プログラミング:SE歴34年の現役プログラマー。加えて、産業カウンセラーとキャリアコンサルタントの資格保有者
・動画制作、編集:広告代理店で映像ディレクターの経験有。大手食品メーカーや製薬会社、大手インフラ系などの動画制作も手掛ける。映像美術やカメラマンの経験も持つ。
・webデザイン、グラフィックデザイン:大手車会社の社内ネット、大手PCメーカーのキャンペーンページ、楽天アパレル部門上位常連のネットショップなど様々なWEB担当歴あり。
3. 実践力を養うアウトプットの機会
3つ目は、実務経験につながる"実践の機会"が豊富な点です。たとえば、毎月テーマを決めて、実践でバナーやチラシの制作講座を開催したり、実際に「企業様から依頼をいただいて創る」という環境を整え、動画やポスター、ロゴ制作に取り組んだ実績もあります。
さらに、事務職希望の方に向けては、体調管理表や学習タスク表を自分で作る習得をつけてもらったり、在宅勤務を希望する方にはZoomでの就職相談やビジネスマナーを実践的に学べるように、専門の支援員が個別に対応しています。
こうした一つひとつの工夫と実践が、就職のための学習だけでなく、「職場で活きる力」を育てる支援につながっていると思っています。
── 未経験からクリエイティブ職についた方についてお話しを伺いたいです。目指せた理由はどこにあるのでしょうか?
中村:先ほどお伝えしたような、【この環境だからこそできる支援】がベースになっていますが、それ以上に大きかったのは利用者さんの「チャレンジしてみたい」「頑張ってみたい」という前向きな気持ちだったと感じています。テキストで学ぶだけでは、いざ仕事に取り組んだときに「思っていたのと違う」と感じることも少なくありません。仕事で必要なスキルとは、「ツールが使える」「創れる」だけではないからです。
そういった学びと現実のギャップを、通所中に実際に体験したり、企業様からの依頼を受けて何かを制作したりといった実践の積み重ねが自信につながって、結果的に「未経験でも挑戦してみよう」という行動へと結びついたのではないでしょうか。
「専門スキル×汎用スキル」で働き続ける力を習得
── 実際にどんな職種に就いた利用者がいらっしゃいますか?
中村:これまでに事務職や動画編集職、ライティング職、ゲームプランナーなど、さまざまなIT・クリエイティブ系の職種に就かれています。障がい者雇用でも多くの職種、企業様での就労を実現しています。また、事務職として入社後にデザインスキルを活かした業務を担当されている方もいて、ご自身の得意や特技を活かして、幅広い職種での就職実績があります。
初めて当事業所に来所いただいたときは、「本当に自分に就職なんてできるんだろうか」と、不安な気持ちを抱えていらっしゃる方がほとんどです。過去のご経験やご職歴から、自信をなくしていたり、未来が見えづらくなっていたりする方も少なくないんです。
でも、就職が決まった頃には自分から、自分の言葉で「自分のこと」「できるようになったこと」「やりたいこと」を語れるようになってる皆様の姿が印象的です。、「できること」が増えていて、内面的に変化されていく様子には、いつも感動します。
── 就業先からはどのような評価をいただいていますか?
中村:特に評価されているのは、制作と業務への姿勢のレベルの高さです。ただ趣味・興味レベルではないね!というお褒めのお言葉をいただきます。好きな作品を作ったのではなく、実際に企業様と関わりながら、しっかりとヒアリングや打ち合わせを重ねて制作を行った実戦的経験は企業様側からも高く評価され、「本当にここまでできるんですね」と驚かれることが多いと感じています。
<利用者さん作成動画事例>
企業様からは即戦力としてのスキルをかなり求められているのも事実です。クリエイティブ系の職種では、入社後すぐに動画制作や記事のライティングなど、実務に関わるケースが多く、研修期間があっても、早い段階で現場に出て成果を出すことが期待されています。加えて、ポートフォリオなどの制作物の有無はもちろん見られますが、それ以上に重要視されるのが「ビジネスの現場で、実際に相手とコミュニケーションを取りながら制作物を作った経験があるかどうか」ということです。
そういう意味では、やはり、「創ることができる」だけでは不十分さを感じ、そういった特化スキルを活かすための土台や基礎つくりも大切にしています。
、特化スキルに加えて、OfficeソフトやGoogleアプリケーション等汎用性の高い業務スキルも身に着けることを必須にしています。、動画編集職として採用された方が業務報告書や進捗管理など事務作業で高評価されているケースもあります。逆に、事務職採用された方が、ポスター制作などデザインスキルを活かして活躍しているケースもあり、企業様からも実務性の高さを評価いただいています。
もちろん、障がい理解や自己理解、ビジネスマナーも必須で支援しています。
企業理解の促進とスキルの棚卸しで最適なマッチングを意識
── 利用者と企業のマッチングで大事にしていることは何ですか?
中村:「就職=ゴール」ではなく、利用者の方々が「これまでよりできるだけ過ごしやすく、、無理なく、長く働ける環境か」という視点をとても大事にしています。
そのうえで、これまで利用者さんが学んできたスキルが、実際に企業の中でどう活かせるのかという点をしっかり整理し、見える化することを意識しています。特に「事務スキル」といった大まかな表現だと、企業様側には具体的に伝わりにくいので、「Excelで関数が使える」「Wordで文書作成ができる」「〇〇の資格を保有している」など、細かく分けて提示するようにしています。そうすることで、企業様側の理解度や納得感が高まり、より良いマッチングにつながると思っています。
加えて、利用者さんにも「今回の就職で何を大事にしたいか」を一緒に考えてもらうようにしています。 「通勤の負担を少なくしたい」「達成感のある仕事がしたい」など、通所を通して自分の中の優先順位を整理していくことが、就職後の安定にもつながると思っています。
また、配慮事項に関しても大事な要素です。障がい者雇用で働く場合、企業様側に配慮してもらいたい内容があることが一般的ですが、それを一方的に伝えることはしません。自分でできる対処法はなにかもしっかり実践と整理をし、伝えるようにしています。そのうえで企業様がその配慮内容をきちんと対応していただけるかどうかを見極めてもらうことを大切にしています。
企業様にとっても、現実的に受け入れが難しい配慮内容を無理に対応してしまうと、結果的にお互いにとって良くない状況になってしまうため、事前にしっかり話し合い、双方にとって無理のない形で合意点を見つけていくことが重要だと考えています。こうした点については、定着支援の面談の中でも企業様側・利用者ご本人の両方にお話しています。
それとは別にスキルに応じた職種紹介も行っています。たとえば「この方はデザインスキルが高い」と感じた場合には、それに関連する求人をご紹介するなど、個人の得意分野や適性に応じてマッチングを行っています。そういった意味でも、スキルの棚卸しや見える化はとても重要なことだと思いますね。

就活軸の明確化と信頼関係を重視したフォロー体制で驚異の定着率100%を実現
── 利用者の方々における就労支援に対しては、どんなサポートを行っているのでしょうか?
中村:就活に入ったらまず最初に、ご自身が就職において大切にしたい価値観や目標、譲れないポイントなど、就活の軸を明確にしていただくようにしています。通所を通して積み重ねた自己理解や障がい者理解、そしてスキルセットを最終整理しながら決めていきます。
そのうえで、企業様のミッション・ビジョン・バリューを調べたり、会社説明会に参加してもいながら、企業様の方向性や文化が自分の考え方や軸にどの程度マッチしているかを見ていきます。
企業様が当事業所向けに説明会を実施してくださることも。
もちろん、すべての希望が完璧に一致する企業様を見つけるのは難しいですが、その中でも自分にとって特に大切な点がどれだけ叶えられるかを確認していくというアプローチを行っています。就活を進めていくなかで、自分の軸に合った企業様を選ぶことが、長く働き続けるためにもとても重要だとお伝えしています。
── 障がい者雇用定着率100%と伺いました。このような高水準を保てている理由をお聞かせください。
中村:どうしても「仕事=つらいだけのもの」というネガティブなイメージを持っている方が多い印象があります。特に、過去に仕事で挫折を経験された方やファーストキャリアの方、その傾向が強いように感じますね。
ただ、実際に働いてみると、仕事は単にお金を得る手段だけではなく、自己肯定感の向上や、人とのコミュニケーションを通じたやりがい・楽しさなど、働くことで得られる価値も大きく、多くの方が就職後に「思っていたより楽しい」と話してくれて、定期的に近況報告をくださる方も多いんです。
その背景には、日々の訓練や模擬オフィスとしての取り組みがあると思います。仕事中に悩んだ経験を振り返りながら、「今だったらどう対応するか」といったケーススタディを通して、自分なりの対処法を身につけていくことができています。
実際に社会に出てからも、その経験が大いに活かされており、悩みへの耐性や対応力に繋がっていることが、結果として定着率の高さにも表れていると考えています。
そのほか、具体的なサポートとして卒業生の方々と月に一度、対面またはオンラインで定期的に面談を行っています。企業様によっては担当者が間に入って、三者面談を行うこともあり、その場で体調や業務の進捗などを確認しています。もし企業様側に直接伝えづらい悩みがある場合は、私たちが間に入って調整・支援する形をとっています。
なかでも、特に心がけているのが「信頼関係の構築」です。他の事業所では、定着支援を別のスタッフが担当するケースもありますが、私たちは一貫した体制で支援者が関わるようにしています。そうすることで、ちょっとした悩みや困りごとも通所時用に話しやすくなり、安心して相談できる環境をつくるよう心がけています。また、事業所内での交流会などを定期的に開催し、卒業生同士が近況を話したり、励まし合える機会を設けています。
「この場所なら頑張れる」。失敗しない就労移行支援の選び方
── 今、“自分にできる仕事がわからない”と思っている人に、どんな言葉を届けたいですか?
中村:これまでに辛い経験や挫折をしてきた方は、きっと大変だったこともたくさんあったのではないでしょうか。そのような出来事の中にも、実はたくさんの経験やスキルが積み重なっていると思うんです。
なので、辛い記憶ばかりに目を向けるのではなく、そこから得られたことや身についた力にもぜひ目を向けてほしいですね。そうしたスキルや経験が、これからどんな一歩を踏み出してみたいかといった未来の行動につながっていくことを、私たちは一緒に考えていきたいと思っています。
「自分にできる仕事が分からない」と感じるのは、悪いことではありません。むしろ、そこから可能性を探していくことが、前に進むための大切な第一歩だと思います。今、不安を感じていたり、自信が持てなかったりする方がいれば、ぜひ一緒にその一歩を踏み出していけたら嬉しいです。
── 就労移行を選ぶときの見るべきポイントがあれば教えてください。
中村:ご自身が希望する支援がきちんと受けられる場所かどうかは、ぜひしっかりと見ていただきたいポイントです。多くの事業所では、見学や体験の機会が設けられていると思いますので、そういった機会を活用して、自分に合った環境かどうかを確認していただくことをおすすめします。
模擬オフィスのような実践的な環境が合う方もいれば、学校のような場所で支援を受けたいという方もいると思うので、支援内容だけでなくその場所の雰囲気や職員の関わり方なども含めて、自分が安心して取り組める環境かどうかを見極めていただくのが大切です。
また、就労移行支援は原則2年間利用できる制度ですが、その期間が辛いだけものになってしまうと、かえって体調を崩すきっかけにもなりかねません。だからこそ、自分のやりたい方向性や、心身の安定を保てるような環境かどうかをしっかり確認したうえで、納得してスタートできる場所を選んでいただけたらと思います。
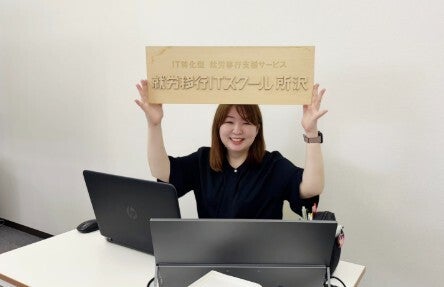
「配慮が必要=戦力にならない」ではありません。
── 障がい者雇用を検討されている企業様へ、どんな言葉を届けたいですか?
私たちは、ただの“マッチング”ではなく、「長く働いていける」を企業様と一緒に叶えたいと考えています。
ビジネスマナーや実践的なスキル、障がい理解と働く意欲を備えた方々が、貴社の力になれるよう、支援機関としての伴走支援・定着フォローも万全の体制でご用意しています。
「こんな仕事できそうな方いる?」「もっと障がい者雇用を進めていきたい」「配慮方法が分からない」等、お気軽にご相談いただければ幸いです。
行動者ストーリー詳細へ
PR TIMES STORYトップへ