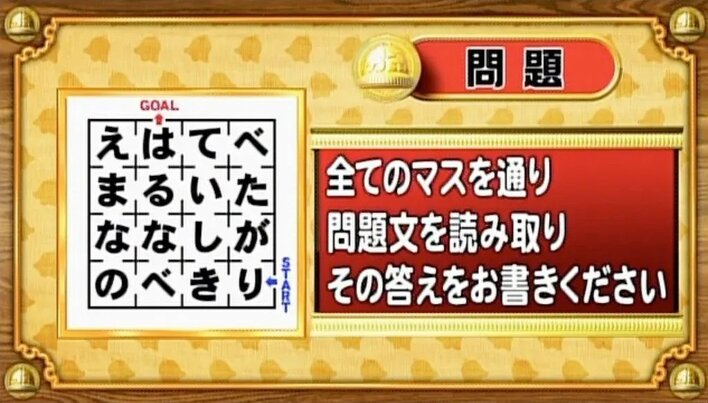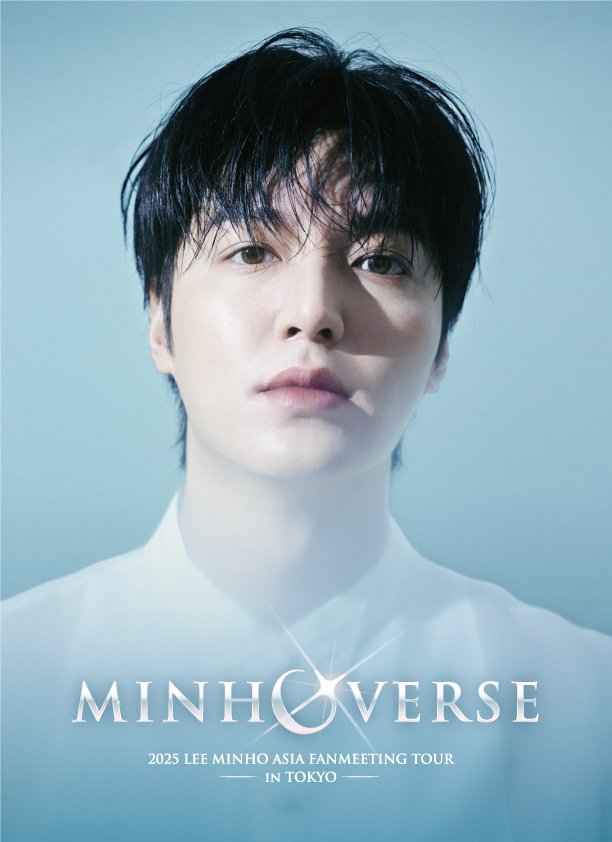視聴者が“今最も見たい女性”に密着し、自身が課す“7つのルール=こだわり”を手がかりに、その女性の強さ、弱さ、美しさ、人生観を映し出すドキュメントバラエティ『7RULES(セブンルール)』。
12月8日(火)放送回では、「天才を育てるルールSP」として、ディリーゴ英語教室代表・廣津留真理(ひろつる・まり)と、娘のバイオリニスト・廣津留すみれに密着。
ハーバード大学とジュリアード音楽院を首席で卒業したすみれと、そんな彼女を育て上げた母・真理。これまでの常識を覆す母の教育法、そして娘の実践法など、2週にわたって紐解かれる廣津留親子のセブンルールとは。
母のルール①:とにかく音読させる
別府や由布院など、全国屈指の温泉地を有する大分県の中心地である大分市に、母・真理の教室がある。彼女の他に、外国人を含むおよそ30人の講師が在籍。コロナの影響でオンライン授業を行う現在は、全国からの入会申し込みが1日100人を超える日も。
ある日、英語に初めて触れる小学生の授業を行う彼女。まだアルファベットもままならない子どもたちだが、最初におこなったのは、英単語と日本語訳のなぞり読み。「Bag、バッグ、Game、ゲーム、Book、本…」と、英単語とその和訳を順に音読していく。
「アルファベットはたった26個しかなくて、(単語は)その組み合わせでできているだけなので、いちいち書かずに読みながら、目で覚えたほうが効率がいい」と、真理は話す。
英単語を読み終えると、授業開始からわずか25分で英会話文を教え始めた。「英語はとにかく、はじめは音読する。これに尽きます」という彼女は、やはり授業中、生徒に何度も音読をさせる。
「日本で国語を習うときに『助詞は“てにをは”』『リピートアフターミー』とか言って習ってないですよね。聴きながら真似して文字と一緒に読んで、勝手に覚えていることを英語で適用してる」と、指導法の理由を明かした。
そんな彼女の指導を受け、75分間の授業が終わる頃には、英語に初めて触れた子どもたちが、中学2年生レベルの英文を音読できるようになっていた。
「子どもは出来ないんじゃないかと心配して、先にbe動詞を教えたり、Aから書かせたり…そういうのは、逆に子どもを“ディスっている”と思うんですよね」と、彼女は言う。
「心配というのは、信用してないっていうことの裏返しなので。『子どもを100%信じよう』と、常に言っています」と、語気を強めた。
娘のルール①:毎日todoリストを手書きする
真理の英語学習法で学んできた娘・すみれが、英語とともに、幼少期から夢中になっていたのがバイオリン。高校生になると、国際コンクールへ出場するほどの腕前に。アメリカでのコンクール出場後、ハーバード大学を見学すると、その校風に惹かれ、進学を志すようになった。
「バイオリンの練習もちょっとしつつ、英語の単語を死ぬほど覚えて、ハーバード用に書かなきゃいけない小論文を書いたり」と、受験当時を振り返る。
大分県の公立高校に通っていた彼女は、塾に通うことなく、家庭学習だけでハーバード大学に挑み、現役合格を果たした。大学では応用数学や社会学を学び、首席で卒業。
コロナの影響で、拠点のアメリカから帰国中の現在、主におこなっているのは、バイオリニストとしての演奏、作曲、そして書籍の執筆や、講演活動だ。 多岐にわたる仕事をこなす上で、彼女が徹底しているのが、毎日「todoリスト」を手書きすること。
「『これ忘れないようにしなきゃ』と思っているだけで、頭の中のスペースを食っちゃうので、書き出しちゃう。全部チェックして捨てるっていうのが快感です。達成感が目に見えるので」と、その理由を説明する。
子どもの頃から続けているこのルールが、学力向上にも繋がったという。
「時間とか学力とかって、たぶんスタートのポイントは万人同じだと思うんですけど。それをいかに、人よりも速く、効率よくできるかということに集中してきたというか。あくまでも、私がやっていたのは、目の前のことを効率的にこなすだけ」。地道なことの積み重ねが、今の彼女を作っている。
母のルール②:自宅をイベント会場として使う
英語教師の父のもと、大分県で生まれ育った真理。小学生の頃、テレビから聞こえた「ソニー」という音と、画面に映った「SONY」という文字が、頭の中で一致したことが、今の指導法の原点となった。
言葉への興味を持った彼女は、早稲田大学で文学を専攻。バブル全盛期の大学生活を送ると、卒業後は翻訳業で生計を立てながら、イタリア、ドイツなどヨーロッパを転々とし、20代後半で地元・大分に戻って結婚。娘・すみれが誕生した。
そんな彼女の自宅には、娘のために作った手作り教材の数々が。英単語の裏面に、それを意味するイラストが描かれた画用紙は、音と文字を一致させようと、活用していたものだという。
1歳、あるいは0歳の頃からおこなってきた、音読中心の学習法によって、娘はわずか2歳で英語の絵本を母に読み聞かせ始め、4歳で英検3級に合格。中学3年生レベルの英語がしゃべれるようになったという。
そして8年前、娘がハーバード大学に合格、渡米すると、娘への学習法を元にした英語教室を起業し、多くの子どもたちの才能を育んできた。
現在、自営業の夫と2人で過ごす自宅は、リビングの隣に食事をするためのサンルームが、さらに、地下へ降りると、音楽を流す防音ルームがある。娘が幼い頃から頻繁に、外国人も含めた客人を招き、自宅でパーティーを開催していたという。
イベント会場のような自宅で、さまざまな人と触れ合う環境が当たり前だった娘のすみれは、小学校に入るまで、日本の公用語は英語だと思っていたのだとか。
そんな過去を振り返る真理は、「アメリカには、いろんな人種の人がいるので。そういうことに小さい頃から慣れていてよかったのかもしれないですね」と語った。
娘のルール②:夕食は人と食べる
幼い頃からさまざまな人に触れ、成長してきた娘のすみれは、ハーバード大学を首席で卒業後、バイオリンの道に進むため、ジュリアード音楽院へ進学し、こちらも首席で卒業した。
コロナ禍の今、初めて日本を拠点に活動し、講演会などで自身の経験を伝えている。そんな日々を送る中で、ある日の夕食は、彼女の呼びかけで集まった、高校時代の友人と。そしてまた別の日の夕食も、学生時代の友人ととっていた。
ハーバード時代は、寮生活をともにする仲間と食事をするのが普通だった。「自分の知らない分野を研究している仲間から、その情報を得るのが楽しかった」と話す彼女。「せっかく食べるなら」と、夕食は人と食べるようにしているという。コロナ禍で大人数とはいかないが、人と触れることが彼女の糧になっている。
母のルール③:娘には本音で話さない
仕事のため、月に2回ほど上京するという母・真理が、仕事の合間に会ったのは、およそ2ヵ月ぶりの再会だという、娘のすみれ。娘が幼い頃から、さまざまな場所に出かけたり、いつも一緒に過ごしてきた2人は、食事の際も友達のように終始楽しげだ。
しかし、彼女にはずっと、娘の前で心掛けていることがあるという。それは、娘には本音で話さないということ。
「なんでかというと、娘に一生モテていたいから」と、その理由を明かす。「思ってること全部言っちゃうのが本音だとしたら、それは聞いている人が苦しいですよね。そうじゃなくて、一緒にいたらワクワクできる存在、それが理想のお母さん」。
娘にモテる「理想の母親」でい続けるためのこのルールは、「娘を1回も怒ったことがない」というまでに徹底している。コンクールが近いのに練習が足りないと思うときは、「また今日も練習していない」とは言わず、「このあと、コンクール行く時の服装とか楽しいこと一緒に考えよう」などと声をかけるのだそう。
怒りや嘆き、本音を隠し、娘を育ててきた母だが、それを知った娘は、「全然『裏切られた』とかじゃなくて、『やりそうだな』って感じです」と笑った。
娘のルール③:わからないことは即ググる
ある日、バイオリンの演奏と講演会のため会場に向かう道中、道に迷いかけるすみれ。方向音痴だという彼女の頼りはもっぱらGoogleマップだ。
さらに別の日には、道すがらに見つけた、興味を惹かれたブランドを、その場で検索。友人との食事中も、話題に上がった「エンロン事件」がわからないからと、即検索した。
小さい時から、わからないことがあったら聞くというのが癖だったといい、わからないことはすぐさま“ググる”のが、今の彼女のルールの一つ。それが、ハーバード受験も支えたという。
周りにハーバード受験者がいない環境下、募集要項や入試の日程など、すべて1人で調べ、入試に臨んだ。
「頭のメモリーって限られていると思うので、ググったらすぐに出てくる知識は、頭の中に詰め込む必要ないと思っていて。たくさんある情報を、どんどんさばいて処理するっていう力のほうが、重視される時代になったと思うので、そっちをひたすら磨いていく」と語った。
※記事内、敬称略。
次回、12月15日(火)の『7RULES(セブンルール)』は、廣津留真理・すみれ親子に密着した「天才を育てるルールSP」完結編。「公立からでもハーバードに入る術は必ずある」と語るすみれと、「満点がトップはダサい。その上がある」と語る真理。親子が何より大切にしてきた、「才能を開花させるルール」とは。